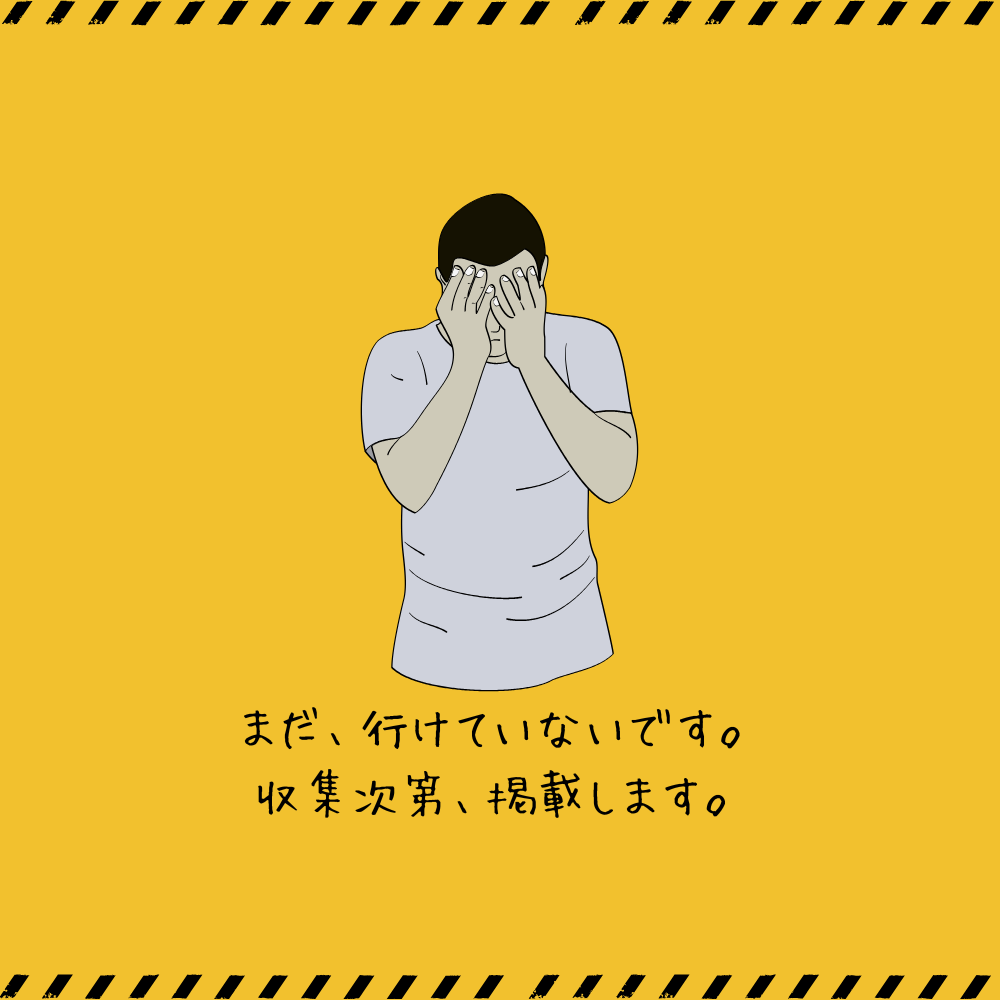192.角牟礼城
続100名城基本情報
| 住所 | 大分県玖珠郡玖珠町森 |
|---|---|
| 電話 | 0973-72-7151(玖珠町社会教育課) |
| 築城年 | 弘安年間(1278年-1288年) |
営業情報
| 開館時間 | 24時間(山城のため) |
|---|---|
| 入場料 | 無料 |
| 休館日 | なし |
1. 角牟礼城の概要と立地
角牟礼城は、大分県玖珠郡玖珠町森に位置する中世から近世にかけての山城です。標高577メートルの角埋山(つのむれやま)の山頂に築かれており、比高は約240メートルに達します。この城は豊後国から豊前国へ抜ける交通の要衝に位置し、天然の要害として機能していました。角埋山は切り立った岩山に囲まれた孤立丘で、おにぎり型をしたビュート地形の急峻な斜面が特徴的です。玖珠盆地を見下ろすこの立地は、古くから軍事的に重要な地点とされていました。
2. 角牟礼城の歴史
角牟礼城の築城は、弘安年間(1278年-1288年)に玖珠郡衆の一人である森朝通によって行われたと伝えられています。ただし、史料における確実な初見は文明7年(1475年)とされています。戦国時代には豊前の大内氏と豊後の大友氏との争いを背景に城が堅固に補強され、大友氏の境目の城として重要視されました。天正14年(1586年)の島津義弘による豊後侵攻の際には、玖珠郡衆が籠城して島津軍の攻撃に耐え抜き、最後まで落城しなかったため「難攻不落の城」として名を高めました。
3. 毛利高政による近世城郭への改修
豊臣秀吉の九州平定後、文禄3年(1594年)に毛利高政が角牟礼城主として入封しました。毛利高政は豊臣秀吉の大坂城築城に関わった経験を活かし、当時最先端の築城技術を用いて角牟礼城を織豊系城郭へと改修しました。この改修により、中世の山城から石垣や櫓門を持つ近世の城郭へと変貌を遂げました。特に二の丸周辺には、当時屈指の石工集団である穴太(あのう)衆による穴太積みの石垣が築かれ、現在でもその技術の高さを見ることができます。
4. 久留島氏の入封と廃城
慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦い後、毛利高政は佐伯藩へ転封となりました。その後、慶長6年(1601年)に伊予国から来島長親(後の久留島長親)が豊後森藩主として入封しました。久留島氏は瀬戸内海で活動していた村上水軍の来島水軍として戦国時代に名を轟かせた一族でしたが、石高が1万石余りであったため城持ち大名の格式を許されませんでした。そのため角牟礼城は廃城となり、山麓の現在の三島公園付近に森陣屋(久留島陣屋)を築いて統治の拠点としました。
5. 現在の角牟礼城跡と文化財としての価値
角牟礼城跡は平成17年(2005年)に国の史跡に指定され、中世城郭から近世城郭への変遷を示す貴重な遺跡として保護されています。現在の遺構は、本丸、二の丸、三の丸、水の手曲輪から構成されており、特に穴太積みの石垣が良好な状態で残存しています。伝搦手門跡の野面積み石垣は、安土城にも見られる近世山城の特徴を示しており、築城技術の発展を物語る重要な史料となっています。
アクセスマップ
関連リンク
散歩記録

御城印情報

くすまちメルサンホール
スタンプ情報