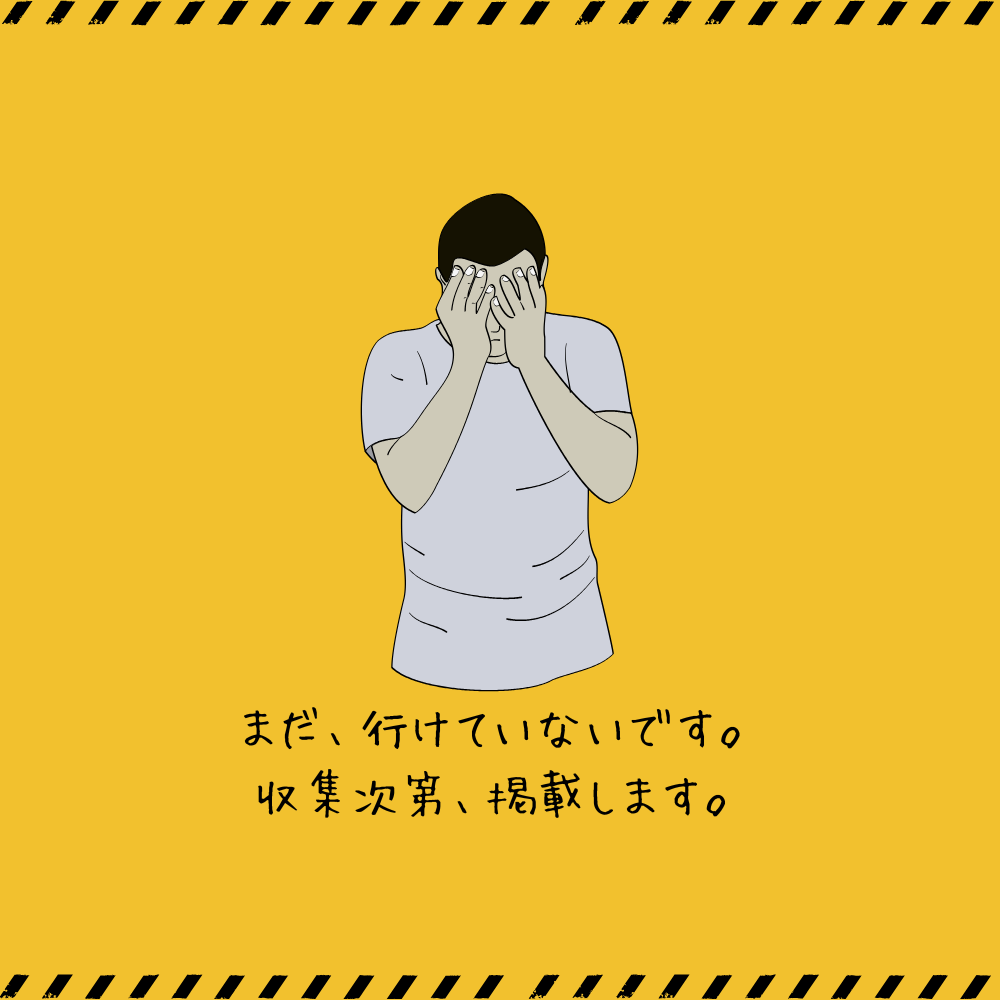76.徳島城
日本100名城基本情報
| 住所 | 〒770-0851 徳島県徳島市徳島町城内1-8 |
|---|---|
| 電話 | 088-656-2525(徳島城博物館) |
| 築城年 | 1585年(天正13年) |
営業情報
| 開館時間 | 9:30〜17:00(入館は16:30まで) |
|---|---|
| 入場料 | 一般:300円 高校生・大学生:200円 中学生以下:無料 ※博物館入館者は旧徳島城表御殿庭園もご覧になれます |
| 休館日 | 月曜日(祝日の場合は開館) 祝日の翌日(日曜・祝日の場合は開館) 年末年始、館内燻蒸作業日、特別展開催準備日 |
1. 徳島城の概要と歴史的意義
徳島城は、豊臣秀吉の四国平定後の天正13年(1585年)に、阿波国の領主となった蜂須賀家政によって築城された連郭式平山城です。吉野川河口付近の中洲に位置する標高61メートルの城山(別名:猪山)に築かれた山城と、その周囲の平城からなる特殊な構造を持っています。蜂須賀氏14代280年余りにわたって徳島藩25万石の居城として機能し、阿波国の政治・経済・文化の中心地でした。明治6年(1873年)の廃城令により建物は解体されましたが、石垣や堀などの遺構は良好に保存されており、昭和16年(1941年)に表御殿庭園が国の名勝に、平成18年(2006年)に城跡が国の史跡に指定されています。現在は徳島中央公園として整備され、日本100名城の76番にも選定されています。
2. 蜂須賀家政による築城と城下町建設
蜂須賀家政は、豊臣秀吉の四国平定軍の一員として阿波国に入り、既存の渭山城と寺島城を合わせて一つの大きな城郭として整備しました。築城にあたっては豊臣秀吉の命により、小早川隆景や長宗我部元親、比叡山の僧侶らが協力し、当時最新の築城技術が投入されました。家政は城の建設と並行して、職業や役割ごとに町を区画・配置し、計画的な城下町の整備を行いました。武家屋敷、町人町、寺院群を系統的に配置し、南北の二本の川(助任川・寺島川)と城山に挟まれた自然の地形を巧みに活用しました。また、阿波藍の生産と流通を奨励し、経済基盤の強化にも努めました。この城と町を一体として設計したアプローチが、後の徳島の繁栄へと導く礎となりました。
3. 城郭構造と山城・平城の特徴
徳島城は山城と平城が一体となった連郭式平山城で、山城部分は西から三の丸・西二の丸・本丸・東二の丸が段差を持って連続配置されていました。本丸には当初天守が建てられましたが、元和年間(1615年-1624年)に取り壊され、その後は東二の丸に天守代用の御三階櫓が建てられました。この御三階櫓が二の丸に建てられた理由は明確ではありませんが、景観バランスや防御上の都合などが考えられています。平城部分には表御殿が置かれ、藩主の居住空間と政務空間が集約されていました。城全体の防御は助任川と寺島川が天然の堀として機能し、さらに人工的な内堀・外堀で囲まれていました。特に内堀は海水を導入した潮入りの堀で、干満の差を利用した独特な防御システムを構築していました。
4. 阿波の青石を使った特徴的な石垣
徳島城最大の特徴の一つは、地元産の「阿波の青石」(緑色片岩)を用いた美しい石垣です。この青石は独特の青緑色を持つ変成岩で、野面積みで築かれた石垣は他の城にはない美しい色彩と風合いを生み出しています。特に注目すべきは「舌石」と呼ばれる構造で、石垣から舌のように突き出した支柱石が現在も6個残存しています。これらは屏風折塀という防御構造を支えるためのもので、塀を屏風のように折り曲げることで死角を作り、そこに開けた穴から矢や鉄砲を撃つことができました。この舌石は全国的に非常に珍しい遺構で、徳島城の軍事的特徴を示す貴重な史料となっています。石垣の技術的な完成度の高さと、地元素材を活かした美的センスが融合した、徳島城ならではの見どころです。
5. 天守の変遷と御三階櫓
徳島城には当初、本丸に天守が建てられていましたが、詳細な構造や外観については史料が少なく、不明な点が多いとされています。この天守は元和年間(1615年-1624年)に何らかの事情により取り壊され、その後まもなく東二の丸に天守代用の御三階櫓が建てられました。この御三階櫓は実質的に天守の機能を果たしており、外観も天守に類似していたと考えられています。なぜ本丸ではなく二の丸に建てられたのかは定かではありませんが、景観上のバランスや城の防備上の都合、あるいは幕府への政治的配慮などが理由として推測されています。この御三階櫓は明治6年(1873年)の廃城令により撤去されましたが、絵図や古写真により当時の姿を知ることができます。天守の変遷は、江戸時代初期の政治情勢や城郭建築の変化を物語る興味深い事例となっています。
6. 表御殿と庭園の造営
徳島城の平城部分には、藩主の居住空間であり政務の中心でもあった表御殿が置かれていました。表御殿は書院造の豪華な建物群で、藩主の日常生活から公的行事まで幅広く使用されました。表御殿に付属する庭園は、江戸時代初期に武将で茶人の上田宗箇によって造営されたと伝えられており、枯山水の庭と池泉回遊式の庭園が一体となった構成でした。この庭園の最大の特徴は、阿波の青石を多用していることと、数寄屋橋下から地下水路を通して内堀の海水を導入した潮入り庭園であることです。庭園内には全長10.35メートルの青石橋があり、この橋が中央で折れているのは、初代藩主蜂須賀至鎮が踏み割ったという伝説が残っています。現在この庭園は国の名勝に指定され、当時の姿を良好に保存しています。
7. 蜂須賀氏の治世と文化的発展
蜂須賀氏は家政以降14代にわたって徳島藩を統治し、阿波国の安定と発展に大きく貢献しました。特に阿波藍の生産と流通に力を入れ、「藍よりも青し」という言葉の語源となった阿波藍は全国的なブランドとなり、徳島藩の重要な財源となりました。また、阿波踊りや阿波人形浄瑠璃などの伝統文化も藩政時代に花開き、現在も徳島の代表的な文化として継承されています。蜂須賀氏は学問も奨励し、藩校の設立や儒学の振興に努めました。幕末には尊王攘夷運動にも関わり、最後の藩主蜂須賀茂韶は明治新政府でも活躍しました。蜂須賀氏の280年間の治世は、徳島の政治・経済・文化の基盤を築き、現在の徳島県の礎となっています。
8. 明治維新後の変遷と公園化
明治6年(1873年)の廃城令により、徳島城の建物は鷲の門を除いてすべて解体されました。その鷲の門も昭和20年(1945年)の徳島大空襲により焼失し、現在の門は平成元年(1989年)に市民の寄付により復元されたものです。城跡は明治後期に徳島公園として一般開放され、日露戦争の戦勝記念として本格的な公園整備が行われました。昭和16年(1941年)には表御殿庭園が国の名勝に指定され、戦後は徳島中央公園として再整備されました。昭和60年(1985年)には徳島城博物館が開館し、蜂須賀家や徳島藩に関する貴重な資料が展示されるようになりました。平成18年(2006年)には城跡全体が国の史跡に指定され、近年では発掘調査により縄文・弥生時代の貝塚なども発見され、より古い時代の歴史遺産としても注目を集めています。
9. 現在の徳島中央公園と観光地化
現在の徳島城跡は徳島中央公園として整備され、徳島市の中心部に位置する市民の憩いの場となっています。公園内には徳島城博物館、旧徳島城表御殿庭園、復元された鷲の門などがあり、年間を通じて多くの観光客が訪れています。春には250本を超えるソメイヨシノなどが咲き誇り、市内屈指の花見名所として親しまれています。夜間は桜や石垣がライトアップされ、水面に映る夜桜は幻想的な美しさを演出します。また、毎年4月には「徳島城 阿波おどり」が開催され、満開の桜とともに徳島の伝統芸能を楽しむことができます。夏には阿波踊りの練習場所としても利用され、有名連の練習風景を見ることができます。城山には遊歩道が整備されており、山頂からは徳島市街地を一望することができ、市民の健康づくりやレクリエーションの場としても活用されています。
10. 日本100名城スタンプと見学のポイント
徳島城は日本100名城の76番に選定されており、スタンプは徳島市立徳島城博物館の受付に設置されています。スタンプは入館料を支払わずに押印可能で、博物館の開館時間内であればいつでも利用できます。御城印は博物館のミュージアムショップで300円で販売されており、蜂須賀家の家紋がデザインされています。見学のポイントとしては、まず復元された鷲の門から入城し、下乗橋や枡形の石組みを観察することをおすすめします。続いて博物館で徳島藩の歴史を学び、隣接する表御殿庭園で阿波の青石を使った美しい庭園美を堪能しましょう。時間があれば城山に登り、本丸跡や石垣、舌石などの遺構を見学し、山頂からの眺望も楽しめます。所要時間は博物館と庭園で1時間程度、城山まで含めると2時間程度が目安です。徳島駅から徒歩10分という立地の良さもあり、阿波踊り会館や眉山ロープウェイなど周辺観光と合わせて楽しむことができます。
アクセスマップ
関連リンク
散歩記録

御城印情報

スタンプ情報