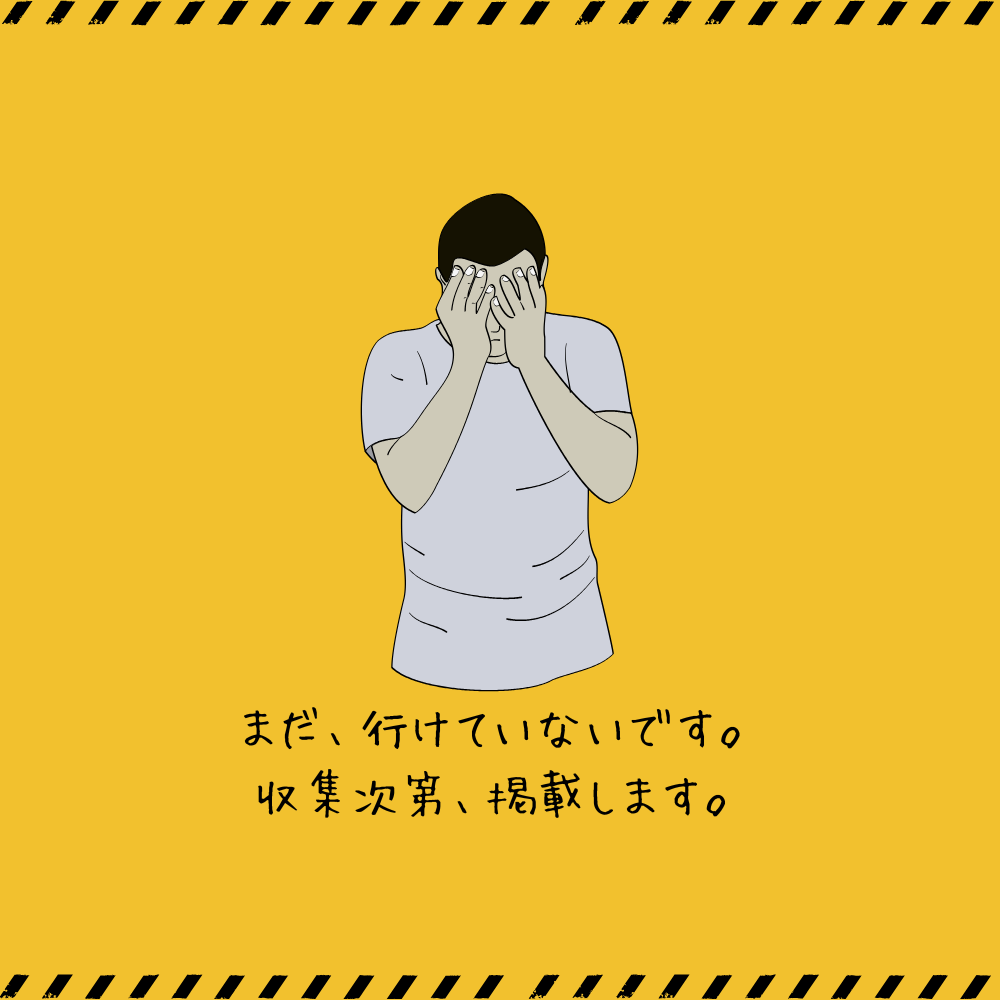91.島原城
日本100名城基本情報
| 住所 | 〒855-0036 長崎県島原市城内1丁目1183-1 |
|---|---|
| 電話 | 0957-62-4766 |
| 築城年 | 1625年(寛永2年) |
営業情報
| 開館時間 | 9:00~17:30(入館は17:00まで) |
|---|---|
| 入場料 | 大人700円、小・中・高校生350円 |
| 休館日 | 無休 |
1. 島原城の歴史と概要
島原城は長崎県島原市城内にあった城で、別名を森岳城、高来城と呼びます。1616年(元和2年)に大和(奈良県)五条から島原に移封した松倉豊後守重政が、1618年(元和4年)から7年余の歳月を費やして築城しました。城は昔「四壁山」「森岳」などと呼ばれた小高い丘を利用して築かれた連郭式平城で、有明海に臨み雲仙岳の麓に位置しています。城郭の形式はほぼ長方形で、高く頑丈な石垣が特徴的な堅固な城でした。
2. 築城の背景と松倉重政
松倉重政は九州の外様大名の牽制とキリシタン対策という大きな任務を与えられて島原に入封しました。4万石の大名としては分不相応とも言える壮大な規模の城を築いたのは、九州の雄藩と有明海で領地を接する島原を幕府が重要視した結果と考えられています。本丸には安土桃山式建築の粋を集めた総塗り込めの五層天守閣をはじめ、3か所に三層櫓がそびえ立つ豪壮堅固な城構えでした。外郭は周囲約4kmの長方形で塀をめぐらし、城門が7か所、平櫓が33か所ありました。
3. 島原の乱と城の歴史的役割
島原城は日本史上最大の一揆である島原の乱(1637年)の舞台となりました。松倉重政とその子勝家による築城のための重税と賦役、キリシタンへの弾圧、過酷な年貢の徴収などが要因となり、農民たちが天草・島原の一揆を起こしました。一揆軍は島原城の大手門などへ攻撃を仕掛けましたが落城させることはできず、城下に火を放ち原城へと向かいました。現在も残る石垣群は、後に原城で幕府軍と互角に戦うことになる一揆軍の猛攻にも耐え、松倉重政の築城技術の高さを物語っています。
4. 歴代城主と幕藩体制
島原の乱の責任を問われて松倉氏は断絶となり、その後は幕府の信頼厚い譜代大名が次々と配置されました。高力忠房、松平忠房、戸田氏、再び松平氏と4氏19代253年間にわたって島原藩政の中心として栄えました。これらの譜代大名の配置は、九州の外様大名監視という島原の地政学的重要性を示しています。各藩主は城の維持管理に努め、特に松平家時代には藩政が安定し、明治維新まで平和な時代が続きました。
5. 明治時代の廃城と民間払い下げ
1873年(明治6年)の「存城廃城令」により、島原城は廃城となり民間に払い下げられました。以来、文字通りの荒城となり、建物は順次解体されて石垣と堀を残すのみとなっていました。明治から昭和初期まで約90年間、天守閣のない城跡だけがその姿をとどめていましたが、この間も地域住民によって史跡としての価値は認識され続けていました。石垣や堀などの基本構造は良好に保存され、後の復元工事の基礎となりました。
6. 戦後復元と観光拠点化
1960年(昭和35年)から段階的な復元事業が開始されました。まず「西の櫓」が復元され、続いて1964年(昭和39年)に「天守閣」、1973年(昭和48年)に「巽の櫓」、1980年(昭和55年)には「丑寅の櫓」などが、矢挟間・鉄砲狭間を備えた長塀とともに復元されました。復元された天守閣は安土桃山様式の壮麗な面影を残し、現在は島原のシンボルとして市民に愛され続けています。これらの建物は資料館として活用され、観光拠点としても重要な役割を担っています。
7. キリシタン史料館と展示内容
復元された天守閣は現在キリシタン史料館として運営され、有名なキリシタン大名有馬晴信(ドン・プロタシオ)時代に盛んであった南蛮貿易時代から、宣教時代・禁教時代・弾圧時代と続く貴重な資料を展示しています。島原の乱関連の史料も豊富に収蔵されており、日本のキリシタン史を学ぶ上で欠かせない施設となっています。5階の展望台からは有明海を望む360度のパノラマが楽しめ、海と山に囲まれた島原の美しい景観を一望できます。
8. 複合文化施設としての機能
島原城内には複数の文化施設が設置されています。北村西望記念館(巽の櫓)では、平和祈念像の制作でも知られる日本彫塑界の巨匠で文化勲章受章者の北村西望氏の代表作約70点を展示しています。民具資料館(丑寅の櫓)では明治・大正・昭和の暮らしが偲ばれる懐かしい民具の数々を展示し、地域の生活文化を伝えています。観光復興記念館では198年ぶりに噴火した雲仙普賢岳の噴火活動の経過を写真、模型、200インチスクリーンで紹介しており、火山学習に最適なスポットとなっています。
9. 日本100名城スタンプと御城印
島原城は2006年に日本城郭協会から日本100名城の91番に認定されており、スタンプは島原城天守閣受付窓口で押すことができます。御城印は松倉家の家紋「九曜紋」のほか、高力家の家紋「四方木瓜」、戸田家の家紋「六つ星」、深溝松平家の家紋「重ね扇」と歴代城主の家紋がデザインされた美しい仕上がりで、価格は300円です。文字は福岡在住の書家・井上龍一郎先生による揮毫で、紙は長崎市の平和公園に手向けられた千羽鶴を使用した再生紙という特別な意味を持っています。
10. アクセスと見学のポイント
島原城へのアクセスは、島原鉄道「島原駅」から徒歩約5分と非常に便利です。車の場合は長崎自動車道諫早ICから約1時間で、有料駐車場が完備されています。見学のポイントは、まず天守閣でキリシタン史料を学び、最上階の展望台で有明海の絶景を堪能すること。2月上旬頃には天守閣をバックに約300本の梅が見頃を迎え、撮影スポットとしても人気です。2024年には築城400年、2025年3月には島原城跡が国の史跡に指定されるなど、歴史的価値がますます注目されている名城です。武将隊による演舞も土日祝日限定で開催されており、戦国時代の雰囲気を体感できます。
アクセスマップ
関連リンク
散歩記録

御城印情報

スタンプ情報