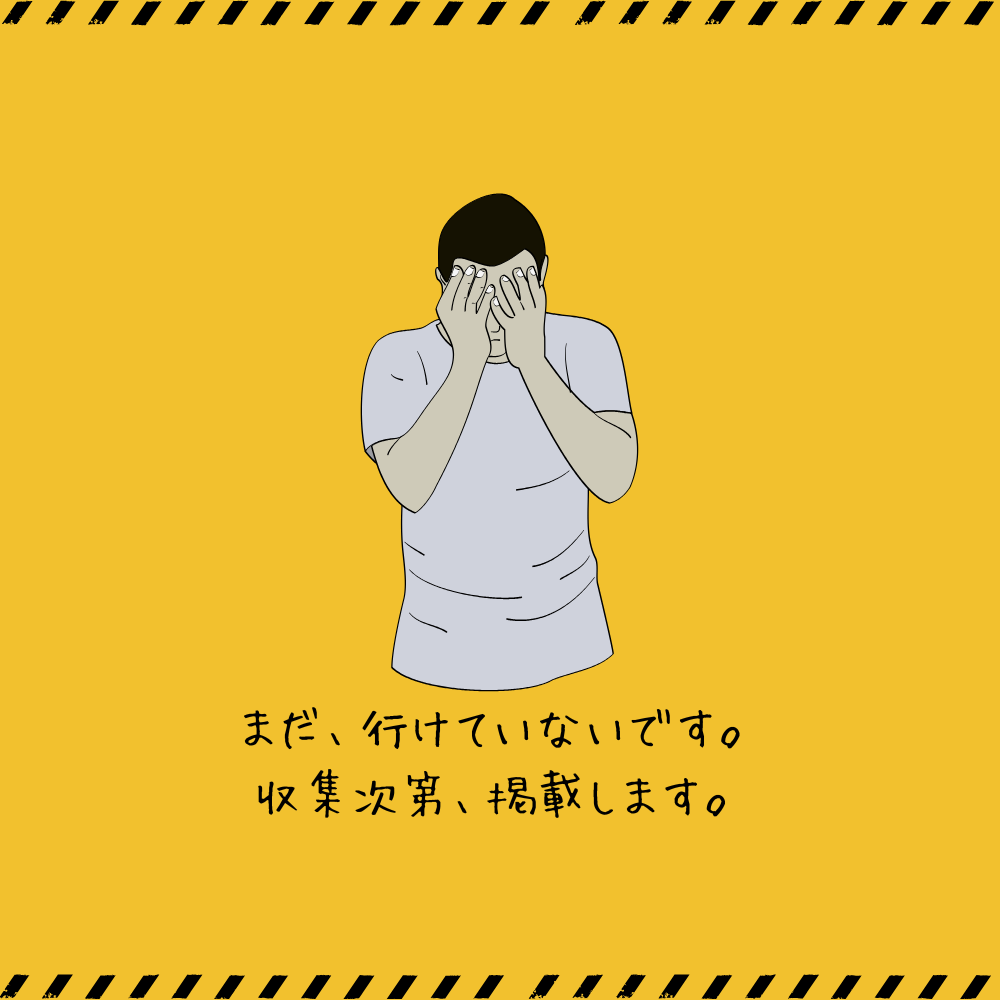197.志布志城
続100名城基本情報
| 住所 | 鹿児島県志布志市志布志町志布志 |
|---|---|
| 電話 | 099-472-1111(志布志市埋蔵文化財センター) |
| 築城年 | 築城年代は不明(南北朝時代に拡充) |
営業情報
| 開館時間 | 志布志市埋蔵文化財センター:9:00-17:00 |
|---|---|
| 休館日 | 月曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始 |
1. 志布志城の築城と初期の歴史
志布志城は築城年代は不明ですが、南北朝時代からこの地が戦乱に巻き込まれたことに伴い次第に拡充されていったと考えられます。建武3年(1336年)には「救仁院志布志城」の肝付氏が重久氏に攻められた記録が残っており、この時期には既に城が存在していました。志布志は万寿3年(1026年)に平季基によって開かれた大荘園島津荘の港として発達し、前川河口部の天然の良港として海上交通の要所でした。中世においては海上交通が発達していたため、この地を支配することは重要な意味がありました。
2. 城主の変遷と政治的位置
志布志城は12世紀から救仁院氏、楡井氏、畠山氏、新納氏、肝付氏と次々と城主が変わり、守護大名・島津氏久が本拠としたこともありました。南北朝時代に志布志城を居城とした島津氏6代当主島津氏久は、この地を重要な拠点として活用しました。戦国時代には新納氏と対立していた豊州家島津氏や肝付氏に城主が代わりましたが、最終的には島津氏が取り戻し、島津方の前線拠点として重要視されました。天正5年(1577年)に志布志は島津氏の直轄地となり、初代の地頭として鎌田政近が任命されました。
3. 城郭構造と築城技術
志布志城は内城・松尾城・高城・新城の4つの中世山城から構成される大規模な城郭で、シラス台地の先端に堀切を設けて各城を構成しています。特に内城だけでも南北約600メートル、東西約300メートルの規模を誇り、深さ17メートルの大空堀(築城時はさらに7メートル深い24メートル)が特徴的です。複雑に入り組んだ空堀群は南九州型城郭の典型的な特徴を示しており、シラス台地の地質を活かした築城技術の優秀な事例として評価されています。内城の矢倉場と呼ばれる曲輪では発掘調査により建物配置が解明されています。
4. 発掘調査と学術的成果
志布志城では過去に内城・松尾城・高城・新城の4つの城で発掘調査が実施され、中世城郭の構造や変遷が明らかになりました。内城の矢倉場と呼ばれる曲輪では発掘調査の成果に基づき柱の位置を再現するなど、学術的根拠に基づいた整備が行われています。出土遺物からは中世後期の陶磁器類や金属製品が発見され、当時の生活様式や交易関係を示す重要な資料となっています。これらの調査成果により、志布志城の歴史的変遷と南九州における中世城郭の特徴が学術的に解明されました。
5. 史跡指定と歴史的評価
志布志城は一国一城令で廃城となりましたが、建物が無くなっただけで石垣などは破壊されませんでした。平成5年(1993年)に内城跡が鹿児島県指定史跡となり、平成17年(2005年)に国の史跡に指定されました。学術的には南九州型城郭を代表する城跡として位置づけられ、シラス台地を活用した独特な築城技術や、海上交通を掌握する戦略的立地、長期間にわたる城主の変遷などが、中世九州の政治史・城郭史研究において重要な事例として評価されています。
アクセスマップ
関連リンク
散歩記録

御城印情報

スタンプ情報