86.大野城
日本100名城基本情報
| 住所 | 福岡県太宰府市太宰府・大野城市乙金・糟屋郡宇美町四王寺 |
|---|---|
| 電話 | 092-558-5000(大野城心のふるさと館) |
| 築城年 | 665年(天智天皇4年) |
営業情報
| 開館時間 | 9:00-19:00(大野城心のふるさと館) |
|---|---|
| 入場料 | 無料 |
| 休館日 | 月曜日・12月28日~1月4日(大野城心のふるさと館) |
1. 日本最古の古代山城
大野城は天智天皇4年(665年)に築かれた日本最古の古代山城で、『日本書紀』に記録される歴史ある城郭です。白村江の戦いで唐・新羅連合軍に大敗した大和朝廷が、日本本土への侵攻に備えて築いた防衛拠点でした。築城技術者は亡命百済人の憶礼福留と四比福夫で、百済の築城技術を用いた朝鮮式山城です。基肄城とともに築かれ、太宰府政庁の北方を守る重要な役割を果たしました。1350年以上の歴史を持つ古代の国防施設として、日本城郭史の出発点となる貴重な遺跡です。
2. 四王寺山の巨大な城郭
大野城は標高410mの四王寺山(大城山)に築かれた日本最大規模の古代山城で、城域は東西約1.5km、南北約3kmに及びます。馬蹄形の尾根に沿って土塁と石塁で囲まれた外周城壁は約6.8km、二重になった部分を含めると総延長8.4kmに達します。太宰府市・大野城市・宇美町の3市町にまたがる広大な城郭で、城内には70棟近くの建物礎石が残されています。9か所の城門が確認され、谷部には石塁で水門が設けられるなど、古代の土木技術の粋を集めた壮大な要塞でした。
3. 百間石垣の圧倒的な存在感
大野城最大の見どころは「百間石垣」で、大野城北側の大きな谷部に築かれた石塁です。水害により流出した部分を含めて長さ約200m、最高部の高さは約6mもある堂々たる石垣で、車道からも見上げることができます。大野城の石塁の中では最も大きく目立つ遺構で、1350年前の石積み技術の高さを物語っています。自然石を巧みに組み合わせた古代の石工技術は現代でも十分に堅固で、当時の百済系技術者の優れた技術力を実感できます。古代山城の代表的な遺構として多くの見学者を圧倒しています。
4. 太宰府口城門と古代の防御システム
太宰府口城門は大野城の9つの城門の中で最も重要な門で、太宰府政庁から大野城への正門でした。発掘調査により2回の建て替えが確認され、門柱の礎石が現存しています。門の西側は石塁で塞がれ、侵入者を限定的にコントロールする巧妙な防御システムが採用されていました。城門周辺には土塁や石塁が複雑に配置され、古代の軍事技術の高さを示しています。現在は礎石と石塁の遺構を見学でき、古代の防御思想を学ぶことができる重要なスポットです。
5. 増長天礎石群と古代建物群
大野城の南端に位置する増長天礎石群は、4棟の建物が整然と並んだ古代の倉庫群です。各建物は約10m×6mの規模で、柱を立てた礎石が良好な状態で残されています。建物群の名称は近くにある増長天像に由来し、武器や食料を保管した軍事倉庫として機能していたと考えられています。周囲には土塁が非常によく残り、古代山城の構造を理解する上で重要な遺構です。礎石の配置から古代建築の技術や規模を具体的に知ることができる貴重な史跡となっています。
6. 聖地四王寺山への変遷
大野城築城から約100年後の774年、城内に四天王寺(四王寺)が建立され、軍事施設から宗教的な聖地へと性格が変化しました。平安時代以降は多くの経塚が造営され、江戸時代の1800年には四王寺三十三体石仏が設置されました。現在の毘沙門堂は四天王寺の法灯を継ぐ寺院で、毎年1月3日の四王寺毘沙門詣りには多くの参拝者が訪れます。古代の軍事施設が中世・近世を通じて信仰の山として愛され続けた歴史は、大野城の重層的な文化価値を物語っています。
7. 日本100名城スタンプと御城印
大野城は日本100名城の第86番に選定され、スタンプは大野城心のふるさと館・大野城市役所・太宰府展示館・宇美町立歴史民俗資料館の4か所に設置されています。2025年3月1日からは宇美町立歴史民俗資料館で御城印の販売が開始予定で、福岡県立宇美商業高校書道部の生徒が揮毫した3種類(白色・若草色・びわ色)が各300円で限定販売されます。古代山城としては珍しい御城印で、大野城の新たな魅力として注目されています。
8. 特別史跡としての価値と保存
大野城跡は1953年に国の特別史跡に指定され、文化財保護法で定められた史跡の最高ランクに位置づけられています。これは国宝と同等の文化的価値を持つことを意味し、日本最古の山城として学術的にも極めて重要です。現在は四王寺県民の森として整備され、遺構の保護と活用が図られています。2003年の集中豪雨による被害を受けて実施された復旧工事では、新たな遺構の発見もあり、継続的な調査研究が進められています。
9. アクセス方法と見学ルート
大野城へのアクセスは、県民の森センター駐車場か太宰府口城門付近の駐車場を利用するのが一般的です。太宰府ICから約20分、西鉄バス「県民の森入口」バス停から徒歩約50分です。見学は車での移動が効率的で、百間石垣など主要な遺構を巡るには半日程度を要します。太宰府市側からは西鉄太宰府駅からタクシーが便利で、多目的広場から徒歩数分で主要遺構にアクセスできます。山頂の毘沙門堂からは福岡平野や博多湾を一望でき、絶景スポットとしても人気です。
10. 見学のポイントと楽しみ方
大野城見学では、まず大野城心のふるさと館で予備知識を得てから現地に向かうのがおすすめです。百間石垣は圧倒的なスケールで必見、太宰府口城門では古代の防御システムを学び、増長天礎石群で古代建物の構造を理解できます。全周約8kmの城壁を完全踏破するには6時間程度かかりますが、主要な見どころだけなら2-3時間で回れます。スマートフォンアプリ「西の都太宰府」を使えば、VRで古代の大宰府の街並みを体験できます。古代史に興味のある方には特におすすめの、日本城郭の原点を体感できる貴重な史跡です。
アクセスマップ
関連リンク
散歩記録

御城印情報

スタンプ情報
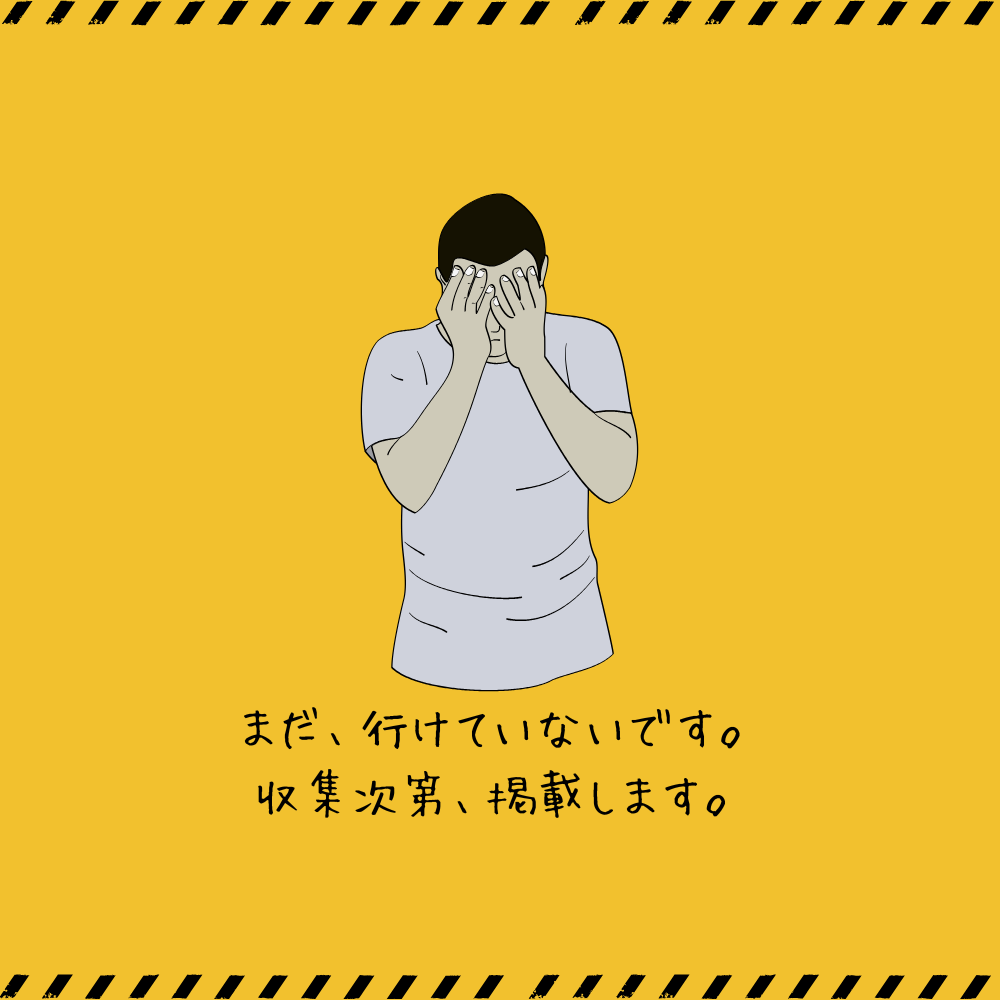
大野城市役所
太宰府展示館
宇美町立歴史民俗資料館

