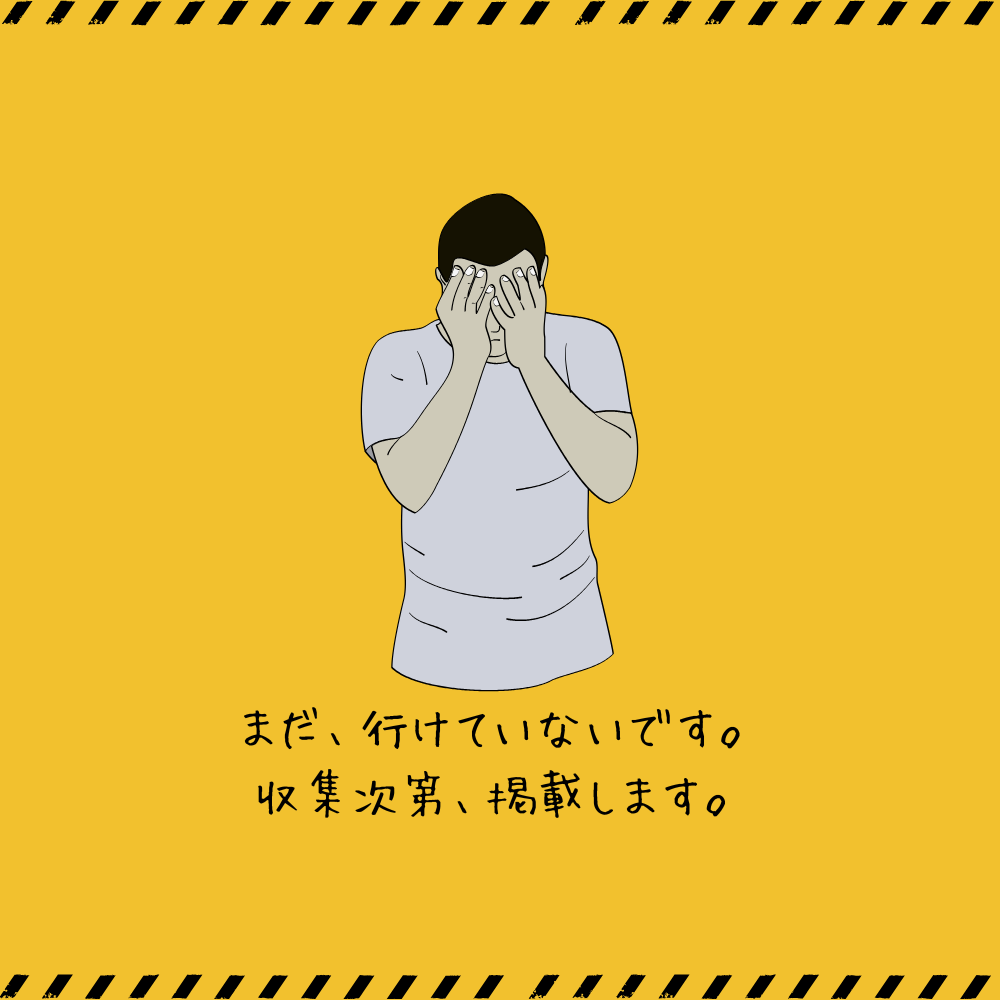191.中津城
続100名城基本情報
| 住所 | 大分県中津市二ノ丁1273 |
|---|---|
| 電話 | 0979-22-3651 |
| 築城年 | 1588年(天正16年) |
営業情報
| 開館時間 | 9:00~17:00 |
|---|---|
| 入場料 | 1,000円(プレオープン料金・ドリンク付) |
| 休館日 | 年中無休 |
1. 中津城の概要と地理的特性
中津城(なかつじょう)または中津川城(なかつがわ(の)じょう)は、大分県中津市二ノ丁(豊前国中津)にあった日本の城です。黒田孝高(如水)が築城し、細川忠興が完成させました。大分県指定史跡で、享保2年(1717年)からは、奥平家が居城としていました。中津城は中津川の河口に位置し、北は周防灘、西は中津川に面し、東は二重、南は三重の堀をつくり、外堀には「おかこい山」と呼ばれる土塁をめぐらせていました。水門から海水が入って堀の水かさは潮の干満で上下する水城で、高松城、今治城とともに日本三大水城の一つに数えられています。また、城郭の形が扇の形をしていたことから、「扇城」とも呼ばれています。地理的に海陸交通の要衝に位置し、水運を活用した戦略的拠点として機能していました。
2. 築城の歴史的背景と政治的意義
天正15年(1587年)、黒田孝高(如水)が、豊臣秀吉より豊前国6郡12万3000石(一説には16万石・その後の検地で18万石となります)を与えられました。当初、馬ヶ岳城に入城しました。天正16年(1588年)、黒田孝高(如水)は、領地の中心である山国川河口に中津城の築城を始めました。同年、熊本の一揆征伐で黒田孝高(如水)が中津城を留守の間に、嫡男の長政は、敵対していた城井鎮房(宇都宮鎮房)を中津城内に引き入れて、惨殺しました。城内には、城井鎮房を祀った城井神社があります。中津城の築城は九州統一を進める豊臣政権の九州支配体制確立の一環として位置づけられ、特に北九州における政治的・軍事的拠点として重要な役割を担いました。黒田如水縄張図には、中津城の本丸、二の丸、三の丸とともに、京町や博多町なども記され、現在の町名はこの時代に由来するものもあります。
3. 城郭構造と築城技術の特徴
中津城に残る黒田孝高(如水)が普請した石垣は、天正16年(1588年)に普請された現存する近世城郭の石垣としては九州最古のものです。本丸上段北面石垣(模擬天守北面下)は、黒田家の石垣に細川家が石垣を継いだ境が見られます。また、本丸南の堀と石垣は、中津市によって修復、復元されています。ここにも黒田・細川時代の石垣改修の跡を見ることができます。黒田家が普請した石垣は、古代山城の唐原山城から持ち出された石が使われているのが特徴です。扇状の縄張りは地形を巧みに利用し、海水を引き込んだ水堀システムは潮汐を利用した防御機能を持つ特異な構造です。江戸時代の絵図には天守は描かれておらず、「中津城下図」には、中津川沿岸の本丸鉄門脇に三重櫓が描かれているのみです。
4. 歴代城主と藩政運営の変遷
寛永9年(1632年)、細川家の熊本藩転封に伴い、小笠原長次が8万石で入封し事実上中津藩が成立しました。以後、中津城は中津藩藩主家の居城となりました。享保2年(1717年)、奥平昌成が10万石で入封し、明治維新まで奥平家の居城となりました。1600年(慶長5年)、黒田氏の代わりに入城した細川忠興は黒田官兵衛が計画した町割りを引き継ぎ、中津城下を整え、ほぼ現在の中津城の形が整いました。1632年(寛永9年)、細川家に代わり、譜代大名の小笠原長次が入封し、城下町の整備を行いました。中津に祇園祭を広めたのも小笠原氏です。第八代将軍徳川吉宗から西国の抑えを期待された譜代大名の奥平昌成が1717年に中津城に入城し、以後1871年(明治4年)の廃城まで、中津藩主の居城として存続しました。各時代を通じて中津城は九州北部の重要な政治的拠点として機能し続けました。
5. 幕末期の変遷と近代への転換
安政3年(1856年)、海防強化のため、海から城への入口に当たる山国川河口(現在は支流の中津川河口)の三百間突堤に砲台を建設しました。文久3年(1863年)、本丸に松の御殿を新築しました。この御殿は小倉県、福岡県、大分県の中津支庁舎として転用されました。1869年(明治2年)、版籍奉還によって府藩県三治制下における中津藩の藩庁が置かれました。1870年(明治3年)、福沢諭吉の進言によって、中津藩士は御殿を残してその他建造物を破却しました。扇状の旧城下町には、今でも築城した黒田官兵衛にちなんだ「姫路町」や「京町」などの町名が残っています。昭和39年(1964年)、本丸上段の北東隅櫓跡(薬研堀端)に観光開発を目的として模擬天守閣が建てられました。中津城は冬至の日には、朝日は宇佐神宮の方角から上り、夕日は英彦山の方角に落ちる場所に築城されています。また、吉富町にある八幡古表神社と薦神社とを結ぶ直線上に位置するなど、築城時の宗教的配慮も確認されます。
アクセスマップ
関連リンク
散歩記録

御城印情報

スタンプ情報