172.三原城
続100名城基本情報
| 住所 | 〒723-0014 広島県三原市城町 |
|---|---|
| 電話 | 0848-64-9234(三原市文化課) |
| 築城年 | 永禄10年(1567) |
営業情報
| 開館時間 | 6:30~22:00(天主台)・見学自由 |
|---|---|
| 入場料 | 無料 |
| 休館日 | 無休 |
1. 歴史と築城の背景
三原城は永禄10年(1567年)頃に、毛利元就の三男・小早川隆景によって三原湾に浮かぶ大島・小島をつないだ埋め立て地に築城が開始された海城です。隆景は天文19年(1550年)に竹原・沼田・両小早川家を掌握し、新高山城を本拠としていましたが、瀬戸内海の水軍拠点として沼田川河口の三原要害を重要視し、拡張・発展させました。当初は水軍の砦として築かれ、これが三原城の原型となりました。
2. 隆景による大規模拡張と海城の完成
天正8年(1580年)から10年にかけて、隆景により大規模な整備が進められ、海城としての偉容を現しました。文禄4年(1595年)に筑前国から三原城に戻り隠居した隆景は、再度三原城の修築に取りかかり、新高山城の石垣を昼夜兼行で運び込むなど、桜山から軍港まで一体化した要塞を完成させました。天主台の「アブリ積み」石垣はこの時期に築かれたもので、満潮時に海に浮かんだように見えることから「浮城」と呼ばれました。
3. 江戸時代の変遷と廃城
慶長2年(1597年)に隆景が病死した後、関ヶ原の戦い後は福島正則が入封し、三原城には養子正之が入りました。元和5年(1619年)には浅野氏が城主となり明治まで続きました。一国一城令でも広島城の支城として残された貴重な存在でした。明治維新により三原城は解体され、明治27年(1894年)に山陽鉄道・三原駅が本丸に跨がる形で開業、後に山陽新幹線の三原駅が設けられ現在に至っています。
4. 続100名城認定と現在の遺構
平成29年(2017年)4月6日に続日本100名城(172番)に選定されました。続日本100名城スタンプは三原観光協会(うきしろロビー観光案内所・JR三原駅構内)と三原市歴史民俗資料館に設置されています。現在は天主台と船入櫓の石垣、本丸中門跡の石垣が残っており、天主台は広島城の天守6基分が入る日本有数の広さを誇ります。本丸跡にJR三原駅があるという全国でも例のない立地となっています。
5. 見どころと御城印
天主台へはJR三原駅1階コンコースから専用通路で6:30~22:00の間アクセス可能で、「アブリ積み」という特殊工法による美しい石垣勾配を間近に見学できます。船入櫓跡の石垣は港町公園として常時見学でき、島の岩礁が基礎部分に見られるのがポイントです。御城印はJR三原駅構内の三原観光協会(うきしろロビー観光案内所)で300円で販売されており、新高山城の御城印も併せて販売されています。
アクセスマップ
関連リンク
散歩記録

御城印情報

スタンプ情報
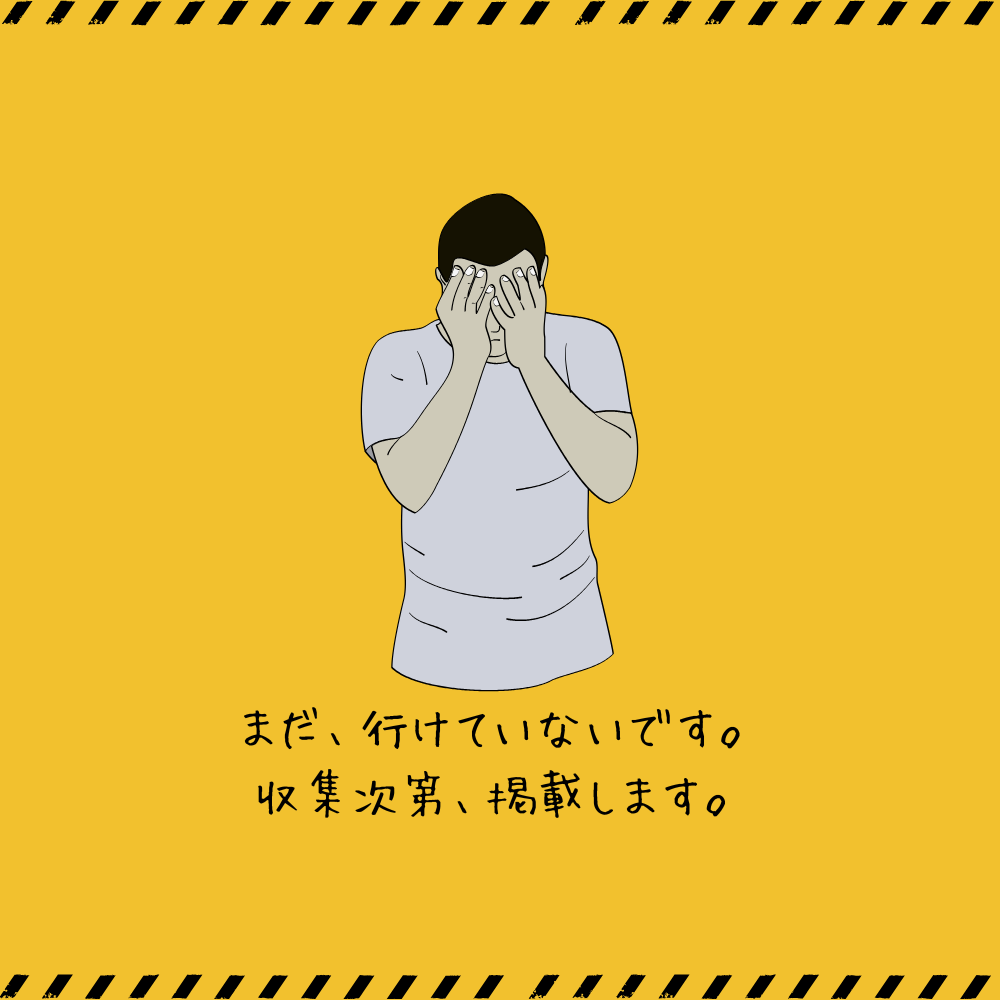
三原市歴史民俗資料館

