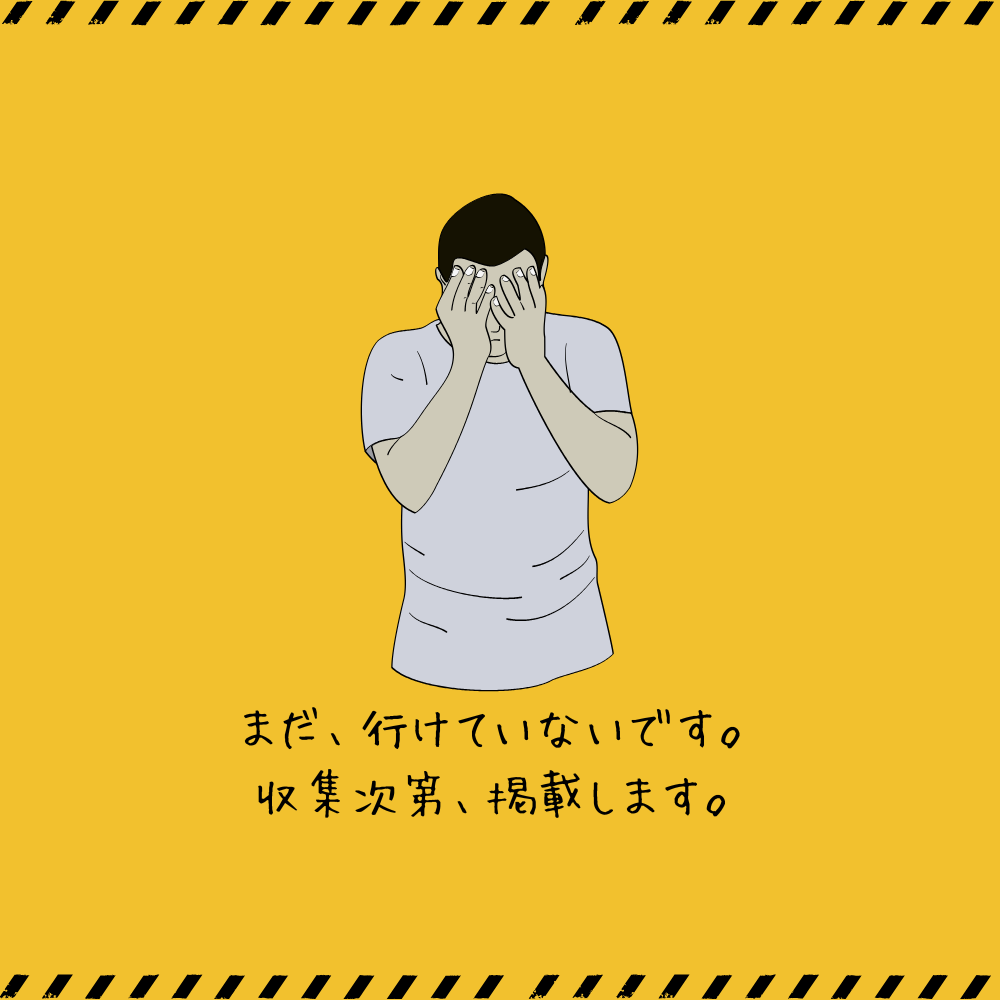181.小倉城
続100名城基本情報
| 住所 | 福岡県北九州市小倉北区城内2-1 |
|---|---|
| 電話 | 093-561-1210 |
| 築城年 | 1602年(慶長7年) |
営業情報
| 開館時間 | 4月〜10月 9:00〜20:00、11月〜3月 9:00〜19:00 |
|---|---|
| 入場料 | 大人350円、中高生200円、小学生100円 |
| 休館日 | なし(年中無休) |
1. 小倉城の歴史と築城の経緯
小倉城の歴史は戦国時代末期の1569年に中国地方の毛利氏が現在の地に城を築いたことから始まりますが、本格的な築城は関ヶ原の戦いで功績を挙げた細川忠興によって1602年(慶長7年)から開始され、約7年の歳月をかけて完成しました。
細川氏が熊本へ転封された後、1632年(寛永9年)には播磨国明石から譜代大名の小笠原忠真が入封し、以後幕末まで小笠原氏の居城となりました。小倉・小笠原藩は将軍徳川家光から九州諸大名の監視という特命を受けており、九州の玄関口として重要な役割を果たしていました。
2. 天守閣の特徴と「唐造り」の構造
小倉城の最大の特徴は、全国でも珍しい「唐造り(からづくり)」または「南蛮造り」と呼ばれる天守閣です。通常の天守閣は上階に行くにつれて部屋が小さくなりますが、唐造りでは4階と5階の間に屋根の庇がなく、5階が4階よりも大きくなっている独特な構造を持ちます。この構造は全国的にも極めて珍しく、小倉城の象徴的な特徴となっています。現在の天守閣は1837年(天保8年)の火災で焼失した後、1959年(昭和34年)に鉄筋コンクリート構造で外観復興されたものです。福岡県内では唯一の天守閣を持つ城であり、その高さは全国第6位、1階の床面積は全国有数の広さを誇ります。天守閣内部は博物館として整備され、2019年にリニューアルされて最新の展示技術を活用した見学が可能です。
3. 城郭の規模と海城としての特徴
小倉城は「日本一の海城」と城郭専門家から称される壮大な規模を誇っていました。かつての城郭は全国で第5位の規模を持ち、西日本では姫路城に次ぐ大きさ、九州では圧倒的な規模で熊本城の約2倍にも及ぶ総構えを持っていました。城下町全体を城郭とする壮大な都市計画のもとで建設され、その規模は「呆れるほどの大きさ」と評されるほどでした。
関門海峡に面した立地を活かした海城として設計され、三方を海に囲まれた地形を巧みに利用していました。現在見ることができるのは、かつての本丸と二の丸の一部にすぎませんが、それでも往時の壮大さを偲ぶことができます。城の石垣は中世に多く用いられた「野面積み」という技法で築かれ、主に当地の足立山系から運び出した自然石を使用しています。
4. 幕末の激動と現代への継承
江戸時代後期、小倉城は激動の舞台となりました。1866年(慶応2年)の第二次長州征討では、小倉藩と長州藩の戦闘が行われ、長州藩の攻勢の前に小倉藩は城に自ら火を放って撤退することを余儀なくされました。明治時代には陸軍の歩兵第12旅団や第12師団の司令部が城内に置かれ、軍都としての性格を持つようになりました。
戦後、市民の熱い要望により1959年に天守閣が再建されました。現在は日本で唯一、一年を通して夜間開城している城として知られ、昼夜を問わず多くの観光客が訪れています。2017年には続日本100名城に選定され、2019年には天守閣内部がリニューアルされ、エンターテイメント性を重視した展示で「日本一おもしろき城」として親しまれています。
5. 見どころと観光情報
小倉城の天守閣は4重5階の構造で、最上階にはキャッスルカフェが設置されており、北九州市の景色を一望しながら休憩することができます。天守閣内には小倉城の歴史や関連する人物の展示があり、最新のXR技術を活用した体験型アトラクションも楽しめます。また、宮本武蔵や佐々木小次郎ゆかりの地としても知られ、巌流島での決闘の物語が展示されています。
城内には八坂神社や小倉城庭園、松本清張記念館などの関連施設もあり、一日を通じて楽しむことができます。春には桜の名所としても知られ、城を囲む満開の桜と天守閣のコントラストが美しい景観を作り出します。全国でも珍しい「お城と鳥居を一緒に撮影できるスポット」としても注目を集めており、フォトスポットとしても人気を博しています。
アクセスマップ
関連リンク
散歩記録

御城印情報

スタンプ情報