189.鞠智城
続100名城基本情報
| 住所 | 熊本県山鹿市菊鹿町米原443-1 |
|---|---|
| 電話 | 0968-48-3178 |
| 築城年 | 7世紀後半 |
営業情報
| 開館時間 | 9:30~17:15(入館は16:45まで) |
|---|---|
| 入場料 | 無料 |
| 休館日 | 月曜日(祝祭日の場合は翌日)、12月25日~1月4日 |
1. 鞠智城の概要と立地的特性
鞠智城(きくちじょう/くくちのき)は、熊本県の山鹿市と菊池市にまたがる台地状の丘陵に築かれた、日本の古代山城。城跡は、2004年(平成16年)2月27日、国指定の史跡「鞠智城跡」に指定されている。鞠智城は標高約90 – 171メートルの米原台地に所在する。城壁の周長は、自然地形の崖を含めて約3.5キロメートル、城の面積は約55ヘクタールである。直線距離で大宰府の南、約62キロメートルに位置し、古代山城では最も南にある城である。有明海に注ぐ菊池川の河口から東北東約30キロメートルの内陸部に位置し、流域には肥沃な平野が広がる地理的要衝に築かれている。
2. 築城の歴史的背景と文献史料
鞠智城は、『続日本紀』に記載された文武天皇2年(698年)の城の修復記事が初見であり、築城年は不明である。しかし、発掘調査では少なくとも7世紀後半 – 10世紀中頃まで約300年、存続したことが判明している。『日本書紀』に記載された白村江の戦いと、防御施設の設置記事は下記の通り。天智天皇2年(663年):白村江の戦いで、倭(日本)百済復興軍は朝鮮半島で唐・新羅連合軍に大敗した。天智天皇3年(664年):対馬島・壱岐島・筑紫国などに防人と烽(とぶひ)を配備し、筑紫国に水城を築く。『続日本紀』に、「大宰府をして大野(おおの)、基肄(きい)、鞠智(くくち)の三城(みつのき)を繕治せしむ」と、記載された城である。白村江の戦いでの敗北を受けた大和朝廷の防衛政策の一環として、水城・大野城・基肄城とほぼ同時期に築かれたと考えられている。
3. 城郭構造と築城技術の特徴
発掘調査では、国内の古代山城で唯一の八角形建物跡2棟(2棟×2時期)・総計72棟の建物跡・3か所の城門跡・土塁・水門・貯水池などの遺構が確認されている。また、貯水池跡では、付札木簡と百済系の銅造菩薩立像が出土している。八角形建物跡や銅造菩薩立像の出土などは、百済からの亡命者が関与したことが窺える。特に八角形建物は国内の古代山城では鞠智城のみで確認される特異な構造で、朝鮮半島の技術的影響を示す重要な考古学的証拠である。城郭全体は自然地形を巧みに利用し、土塁による防御線を築いて約55ヘクタールの広大な城域を形成している。
4. 考古学的調査成果と出土遺物
発掘調査は、1967年(昭和42年)に第1次調査が行われ、2010年(平成22年)までに32次の調査が実施された。調査成果は、 『鞠智城跡 Ⅱー鞠智城跡第8~32次調査報告ー』 熊本県教育委員会 編集/発行 2012年、で報告されている。発掘調査では総計72棟の建物跡が確認され、食糧保管用の米倉や防人の兵舎等、多様な機能を持つ建物群の存在が明らかになった。特に貯水池跡からは墨書された荷札木簡、百済系の銅造菩薩立像、建築用材、土器片などが多数出土し、当時の物資管理体制や宗教的側面を示す貴重な史料が得られている。また軒丸瓦には単弁八葉蓮華文が施されており、朝鮮半島の影響を受けた製作技法が確認されている。
5. 歴史的意義と古代山城史における位置
鞠智城は、7世紀末の律令制の導入時に、役所機能のある肥後北部の拠点に改修されたと考えられている。発掘調査で大宰府と連動した施設の改修と変遷が確認された特異な城跡である。また、他の古代山城は国府の近くに所在するが、鞠智城は城自体が役所機能を有するなど、特殊な古代山城といえる。そして、8世紀後半以降は、倉庫が立ち並ぶ物資貯蔵機能に特化した施設に変化して終焉を迎えたとされている。築城当初は、大宰府と連動した軍事施設で、大野城・基肄城などとともに北部九州の防衛拠点であり、兵站基地や有明海からの侵攻に対する構えなどが考えられている。そして、修復期以降は、軍事施設に加えて、食料の備蓄施設の拠点、南九州支配の拠点などの役割・機能などが考えられている。鞠智城は単なる軍事施設から行政・物資管理拠点へと機能変化を遂げた古代山城として、日本古代史研究における重要な位置を占めている。
アクセスマップ
関連リンク
散歩記録

御城印情報

スタンプ情報
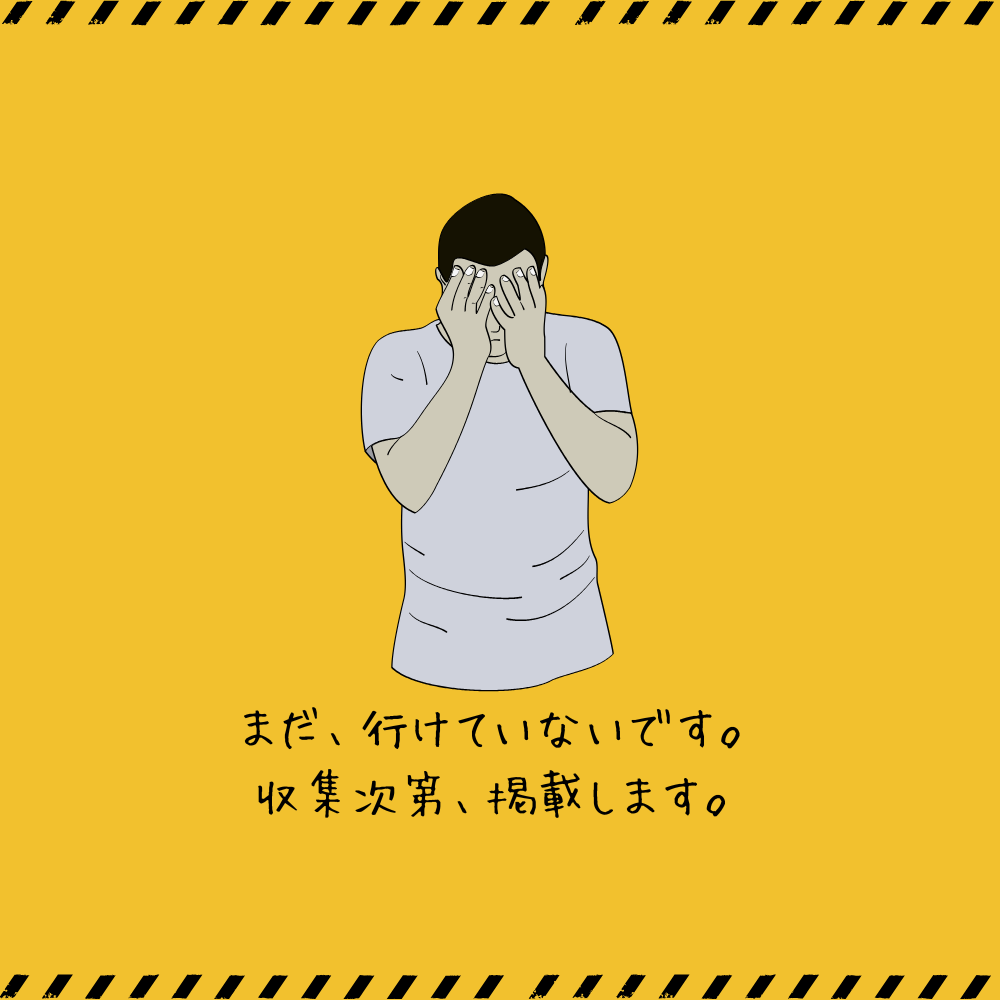
温故創生館

