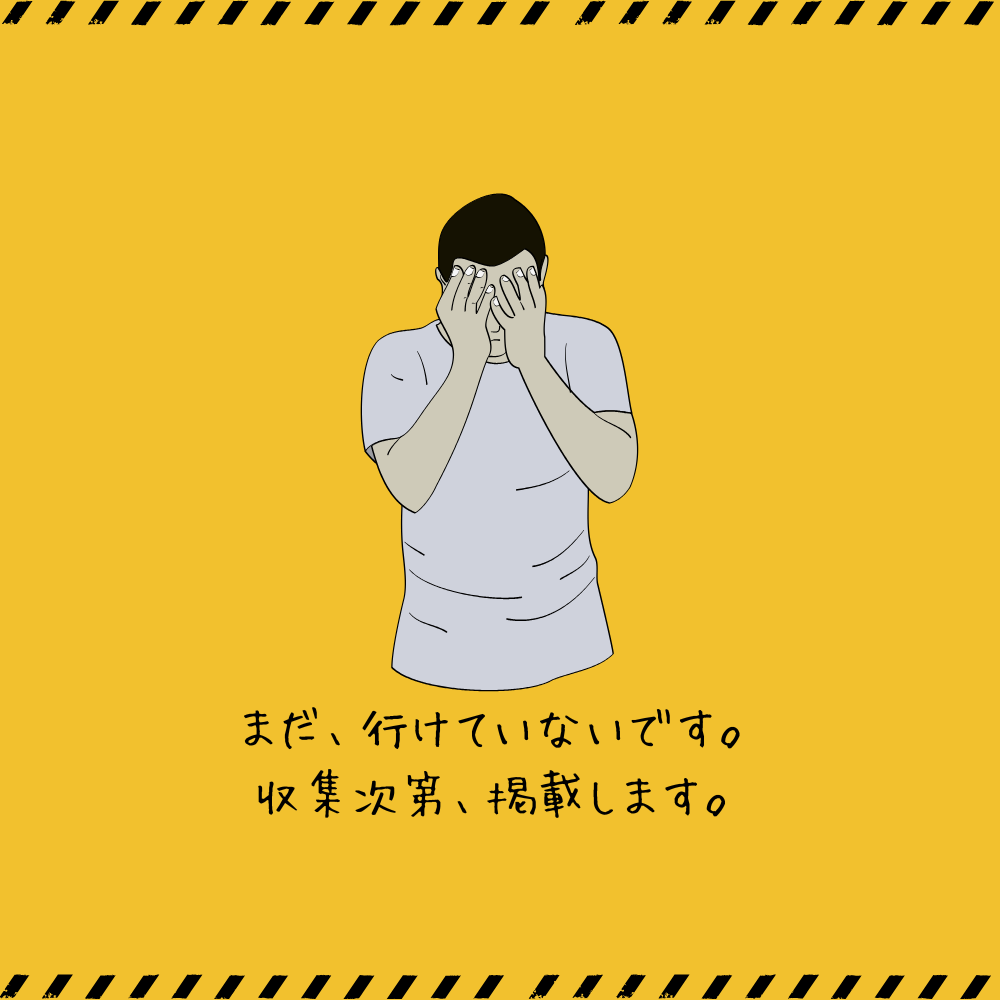184.基肄城
続100名城基本情報
| 住所 | 佐賀県三養基郡基山町大字小倉 |
|---|---|
| 電話 | 0942-92-1211(基山町民会館) |
| 築城年 | 665年(天智天皇4年) |
営業情報
| 開館時間 | 9:00〜21:00(基山町民会館) |
|---|---|
| 入場料 | 無料 |
| 休館日 | 無休(城跡散策は自由) |
1. 基肄城の歴史と築城の背景
基肄城は佐賀県三養基郡基山町と福岡県筑紫野市にまたがる基山に築かれた日本の古代山城です。1954年(昭和29年)3月20日に国の特別史跡「基肄(椽)城跡」に指定されており、日本最古級の山城として重要な歴史的価値を持っています。築城の背景は663年の白村江の戦いでの大敗にあります。唐・新羅連合軍に敗れた大和朝廷は、本土への侵攻の脅威に備えて急速に防衛体制の整備を進めました。天智天皇4年(665年)、大野城とともに築いたことが『日本書紀』に記載されており、城郭の建設を担当したのは「兵法に閑う」と評された亡命百済人の軍事技術専門家、憶礼福留と四比福夫でした。この基肄城は、大宰府を守る南の防御拠点として、主に有明海方面の有事に備えて築かれました。
2. 城郭の構造と築造技術
基肄城は標高404mの基山の3か所の谷を囲み、その東峰(327m)にかけて約3.9kmの城壁を廻らせた包谷式の山城で、城の面積は約60ヘクタールに及びます。城壁の大部分は尾根を廻る土塁ですが、谷部は石塁で塞いでおり、山全体の地形を巧みに利用した防御システムが構築されています。特に注目すべきは水門遺構で、城跡見学の玄関口となる南門と一連の水門石垣には、通水口が国内最大級の規模を持つ水門があります。2015年の水門石垣の保存修理では、新たに三つの通水溝が発見され、同一の石垣面に四つ以上の排水施設を持つ古代山城は、国内においては唯一基肄城のみという貴重な発見となりました。城内には40棟以上もの礎石建物が建てられ、基肄軍団と呼ばれる軍隊が駐屯し、食料や武器の倉庫、住居として機能していました。
3. 古代防衛システムにおける役割
基肄城は単独で存在していたのではなく、古代日本の総合的な防衛システムの重要な一翼を担っていました。大宰府政庁や大野城・阿志岐山城・高良山神籠石など、他の軍事施設と連携を図れる好位置にあり、大宰府都城の外郭防備を固める役割を果たしていました。この防衛体制の原型は、百済泗沘都城にあるとされ、朝鮮半島の高度な軍事技術が導入されていました。
基肄城の東南山麓には「とうれぎ土塁」と「関屋土塁」が確認されており、これらは水城と大野城の関係と同様に、基肄城と対となって最も狭い交通路を塞いだ遮断城として機能していました。古代においては築後国方面と肥後国方面に分岐する要衝にあり、山頂からは北側の博多湾、南側の久留米市や有明海、東側の筑紫野市や朝倉市方面、西側の背振の山並みを一望することができ、情報収集と伝達の拠点としても重要な役割を果たしていました。
4. 古代から中世への変遷
基肄城は古代山城として築かれた後も、時代とともにその役割を変化させながら使用され続けました。『続日本紀』の698年(文武天皇2年)には、大野城・基肄城・鞠智城の三城の修復記事が記載され、『万葉集』にも「記夷城(きいのき)」として記載されています。これらの記録は、基肄城が長期間にわたって維持・使用されていたことを示しています。南北朝時代には、古代の基肄城が改修されて中世の山城「木山城」として再利用されました。山浦地域の武将たちが南朝方として活動し、九州探題一色道猷に対抗する拠点として機能しました。征西将軍懐良親王のもと、菊池武光を中心とした南朝方が基肄城を改修して太宰府の北朝方少弐氏と交戦し、古代の防衛施設が中世においても戦略的価値を持ち続けていたことを物語っています。
5. 現代における保存と活用
現在の基肄城跡は、基山公園として整備され、史跡を巡るハイキングコース(約90分)が設置されており、歴史学習と観光を両立させた活用が図られています。山頂は草スキーのゲレンデとしても利用され、家族でのレジャーにも親しまれています。登山ルート内に礎石群、水門跡、東北門跡、つつみ跡、土塁跡などの遺跡が点在し、登山客からも親しまれています。
アクセスマップ
関連リンク
散歩記録

御城印情報

スタンプ情報