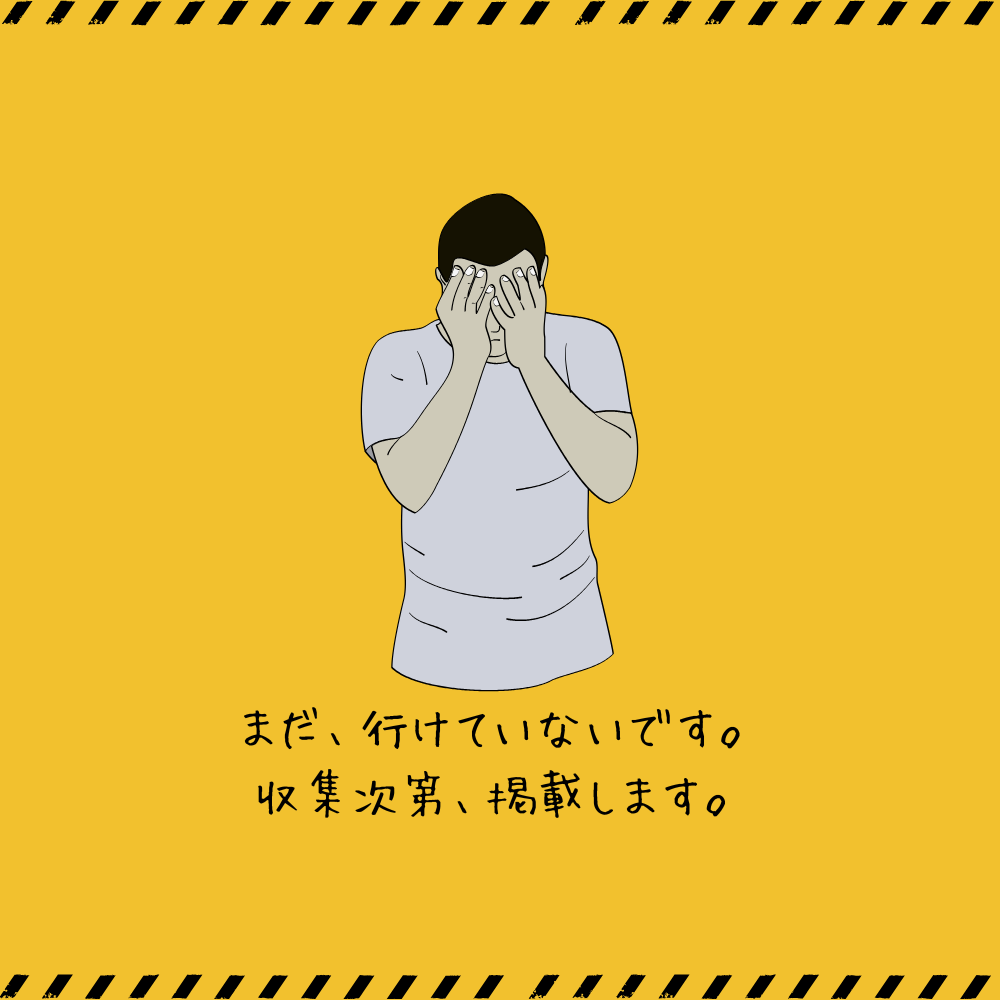185.唐津城
続100名城基本情報
| 住所 | 佐賀県唐津市東城内8-1 |
|---|---|
| 電話 | 0955-72-5697 |
| 築城年 | 1602年(慶長7年) |
営業情報
| 開館時間 | 9:00~17:00(入館は16:40まで) |
|---|---|
| 入場料 | 大人500円、小人250円 |
| 休館日 | 12月29日~12月31日 |
1. 唐津城の概要と地理的特性
唐津城は佐賀県唐津市東城内に位置する近世初期の平山城で、松浦川河口の満島山(海抜46メートル)に築かれています。唐津湾に突き出した満島山上に本丸が配され、その西側に二の丸、三の丸が配された連郭式の城郭構造を持ちます。北面は唐津湾に面するため海城ともいわれ、萩城とともに現在も直接海に聳える石垣が見られる数少ない城郭の一つです。松浦川の右岸には虹の松原が広がり、城から左右に広がる砂浜が鶴が翼を広げたように見えることから舞鶴城の別名を持ち、地形的特徴が城郭の景観美と一体となった稀有な事例となっています。
2. 築城の歴史的背景と名護屋城との関係
唐津城の築城は、関ヶ原の戦い後の政治的変動と密接に関わっています。築城主である寺沢志摩守広高は、慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いで東軍方につき、肥後国天草郡4万石を加増され12万3千石の外様大名となった後、慶長7年(1602年)から本格的な築城を開始しました。築城に際しては、豊臣秀吉の死後廃城となっていた名護屋城の遺材を使用し、九州各地の諸大名の助力を得て築城したとされます。柳川堀、佐賀堀、肥後堀、薩摩堀など、普請に協力した大名の領地名が堀の名に残されており、西国大名による協力体制の実態を示す貴重な史料となっています。
3. 城郭構造と築城技術の特徴
唐津城の築城では大規模な土木工事が実施され、東唐津側と地続きであった満島山を切り離し、松浦川がそこから唐津湾に注ぐよう流路を変更するという画期的な工法が採用されました。2008年から開始された石垣再築整備事業に伴う発掘調査により、天守台南側の地中から天守台の石垣よりも古い時代の旧石垣が発見され、慶長年間前半(1605年頃)の築造と推定されています。さらに旧石垣の裏の盛土からは金箔瓦の一部が出土し、初期段階での建築の格式の高さを物語っています。これらの調査成果により、従来の名護屋城遺材転用説に加えて、より複雑な築城過程の存在が示唆されています。
4. 藩政における政治的機能と変遷
唐津城は江戸時代を通じて唐津藩の藩庁として機能し、寺沢氏、大久保氏、松平氏、土井氏、水野氏、小笠原氏の各大名が城主を務めました。特に水野忠邦は唐津藩主として文化8年から14年まで藩政改革を行い、後に浜松藩主を経て幕閣入りし天保改革を推進したことで知られます。小笠原長行は唐津城本丸で生まれ、幕末期に老中として生麦事件や長州征伐の処理に追われるなど、唐津藩主出身の政治家として重要な役割を果たしました。城は単なる軍事施設ではなく、西国統治の拠点として、また幕政を担う人材を輩出する政治的基盤として機能していました。
5. 近代以降の変遷と文化財的価値
明治4年(1871年)の廃藩置県により廃城となった唐津城は、本丸跡が舞鶴公園として整備され、昭和41年(1966年)に文化観光施設として模擬天守が建設されました。現在の天守は寺沢時代の天守台跡に築かれていますが、当時の天守の存在を示す資料は確認されていません。2008年から継続されている石垣修復事業では、地盤の軟弱性が確認され基礎地盤の改良が必要となるなど、近世城郭の保存における技術的課題も明らかになっています。唐津城は近世初期の築城技術と政治史研究において重要な史料価値を持つとともに、地域の文化的シンボルとして現代に受け継がれている貴重な文化遺産です。
アクセスマップ
関連リンク
散歩記録

御城印情報

スタンプ情報