186.金田城
続100名城基本情報
| 住所 | 長崎県対馬市美津島町黒瀬 |
|---|---|
| 電話 | 0920-52-1566(観光情報館ふれあい処つしま) |
| 築城年 | 667年(天智天皇6年) |
営業情報
| 開館時間 | 見学自由(屋外史跡のため) |
|---|---|
| 入場料 | 無料 |
| 休館日 | なし(屋外史跡のため) |
1. 金田城の概要と立地
金田城は長崎県対馬市美津島町黒瀬に位置する古代山城で、対馬中央部の浅茅湾に突き出した半島状の城山(標高276メートル)に築かれています。7世紀に築城された朝鮮式山城で、西日本各地に築城された一連の古代山城のうち朝鮮半島への最前線に位置し、城山の三方は海に囲まれ、陸続きの南西側も急峻な地形をなす天然の要害となっています。白嶽から北へ延びる白岳石英片岩の岩脈から形成された地質的特徴を持ち、山上から北西方向には朝鮮半島が眺望可能であるため、守りやすく見張りにも適した戦略的立地を示しています。
2. 築城の歴史的背景と日本書紀の記述
金田城の築城は、天智天皇6年(667年)の日本書紀の記述に基づき、白村江の戦い(663年)での倭軍敗北を受けた国防政策の一環として行われました。日本書紀には「天智天皇6年11月、倭国高安城、讃岐国山田郡屋嶋城、對馬国金田城を築く」と明記されており、これは倭・百済連合軍が唐・新羅連合軍に大敗した後の防衛態勢整備の一環でした。天智天皇3年(664年)に大宰府の防備を固めるために対馬島・壱岐島・筑紫国等に防人・烽が設置され、筑紫に水城が築造された後の最終段階として、対朝鮮半島防衛の最前線に金田城が築城されました。
3. 城郭構造と築城技術
金田城は城山の急峻な自然地形を利用して築かれた包谷式山城で、城域面積は約22ヘクタールを測ります。城の最大の特徴は、城山で産出する石英斑岩を用いて積まれた石塁で、総延長約2.2キロメートルに及び、見学できる古代山城のなかでもトップクラスの石塁が保存されています。城戸は全部で三箇所設けられ、一ノ城戸には水圧による崩落を防ぐ水門が設置され、二ノ城戸は階段式の石敷床面を持ち、三ノ城戸では最も高い約7メートルの石塁を見ることができます。これらの遺構は古代の高度な築城技術と工学的知識を示す貴重な証拠となっています。
4. 考古学的調査成果と防人の実態
1985年度以降に実施された発掘調査により、金田城の歴史的変遷と防人の生活実態が明らかになっています。ビングシと呼ばれる城内最大の平坦地では土塁と門礎石が発見され、旧土塁と新土塁の二重構造になっていることが判明し、城の修築過程を物語っています。土塁付近の掘立柱建物跡からは炉の跡も発見され、防人の居住施設の存在が確認されました。出土品としては須恵器・土師器・鍛冶関連遺物・温石等があり、須恵器の編年研究により7世紀中頃に築城され、7世紀末頃に修築、8世紀初頭以後には廃城化したという城の盛衰過程が解明されています。
5. 歴史的意義と文化財的価値
金田城は1982年に国の特別史跡に指定され、史跡の最高ランクである特別史跡としては長崎県第一号の指定を受けています。これは文化財保護法で定められた史跡の国宝級の評価であり、7世紀の古代山城の遺構が良好に保存されていることが高く評価されたものです。また、江戸時代後期には対馬藩による修築が行われ、明治時代には対馬要塞の一部として城山砲台が設置されるなど、古代から近代まで一貫して国防の要衝として機能し続けた歴史的重層性も重要な価値となっています。金田城は古代日本の対外防衛政策と築城技術を研究する上で不可欠な史跡として、学術的にも極めて高い価値を有しています。
アクセスマップ
関連リンク
散歩記録

御城印情報

スタンプ情報
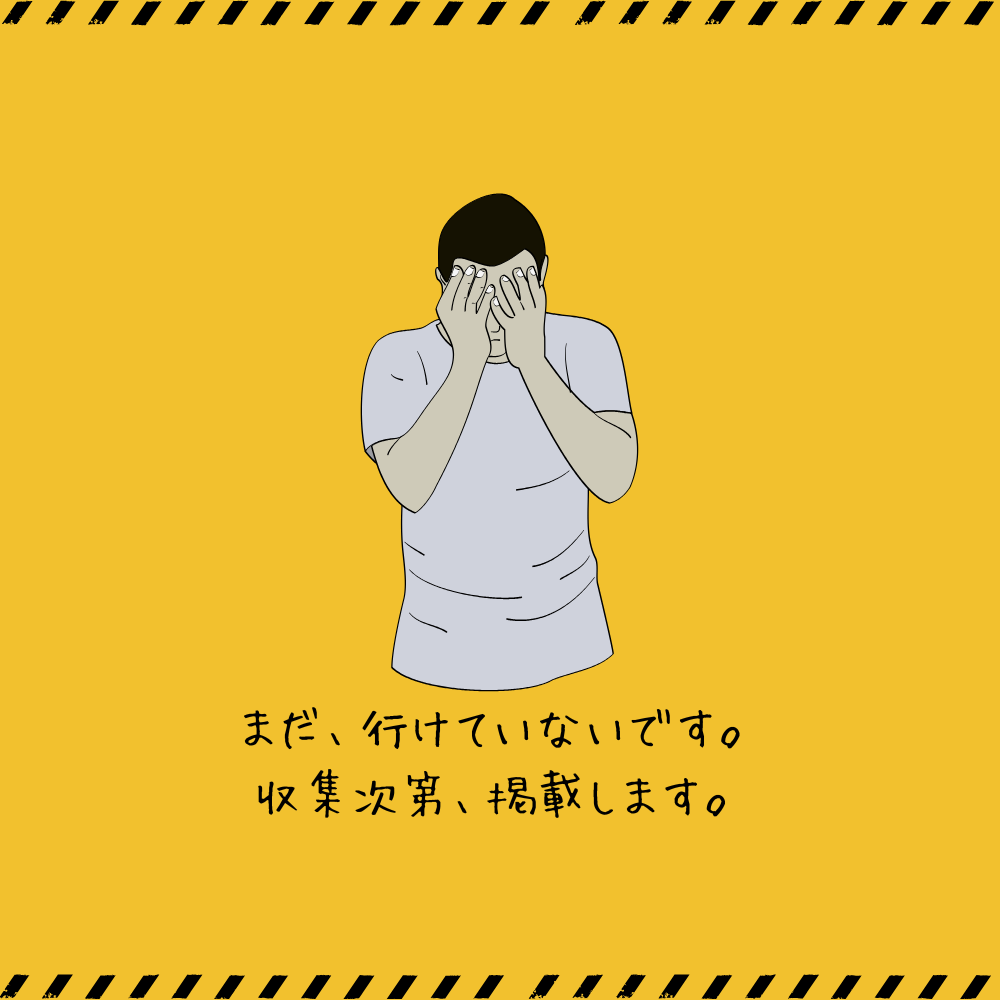
美津島地区公民館

