97.鹿児島城
日本100名城基本情報
| 住所 | 鹿児島県鹿児島市城山町7-2 |
|---|---|
| 電話 | 099-286-2534 |
| 築城年 | 1601年(慶長6年) |
営業情報
| 開館時間 | 9:00~18:00(黎明館) |
|---|---|
| 入場料 | 一般400円、高・大学生250円、小・中学生150円(黎明館) |
| 休館日 | 月曜(祝日の時は翌日)、毎月25日、年末年始 |
1. 築城の歴史と城主について
鹿児島城は、慶長6年(1601年)頃に島津家第18代当主で初代薩摩藩主となる島津家久(忠恒)によって築城が開始された平城です。関ヶ原の戦いで西軍側に属して敗北した島津氏が、徳川家康の薩摩征伐に備えて築いた城でもあります。朝鮮出兵や関ヶ原の影響で財政が苦しかった島津氏は、石高77万石の薩摩藩の城としては質素な造りを選択せざるを得ませんでした。約10年の歳月をかけて完成した城は、以後廃藩置県まで270年間にわたって島津氏の居城として利用されました。島津氏は薩摩、大隅、日向の三国を支配する大大名として君臨し、幕末期には明治維新の立役者を多数輩出しました。
2. 城の構造と特徴
鹿児島城は、標高107mの中世上山城跡である城山の東麓に築かれた平城で、背後の山城と麓の居館から構成される平山城的性格も持っています。中世以来の館造りを踏襲し、華麗な御殿建築が建つ本丸と二の丸の二つの曲輪から構成され、御楼門以外に天守も櫓もないシンプルな構造が特徴です。本丸には政庁と藩主の居館、表書院が置かれ、二の丸には世継ぎや側室などの居館と庭園が設けられていました。城全面の東側には一族や重臣の屋敷地と役所群が広がり、実用性を重視した造りとなっていました。別名「鶴丸城」と呼ばれるのは、屋形の形状が鶴が羽を広げたような形であったことに由来します。
3. 火災と再建の歴史
鹿児島城は度重なる火災に見舞われた悲運の城でもあります。元禄9年(1696年)に最初の大火災で焼失し、宝永4年(1707年)に再建されました。しかし明治6年(1873年)の火災によって本丸が再び焼失し、このとき威風堂々たる御楼門も失われました。さらに明治10年(1877年)の西南戦争では二の丸も炎上し、建物はほぼすべて焼失してしまいました。西南戦争は薩摩の英雄である西郷隆盛が政府軍と戦った最後の内戦で、鹿児島城周辺も激戦地となりました。現在城跡に残るのは本丸と二の丸周囲の石垣と水堀のみで、往時の壮麗な建物群を偲ぶことはできませんが、2020年に御楼門が日本最大の城門として復元されました。
4. 薩摩藩の政治と文化
鹿児島城を拠点とした薩摩藩は、独特の政治制度と文化を発達させました。城下町は町人地である上町・下町・西田町と武家地である上方限・下方限の5つのエリアに分かれ、「町方三分・武家七分」と呼ばれるように幕末時点で居住人口の9割が武士階級でした。薩摩藩は外城制という独自の地方支配制度を採用し、領内各地に外城(とじょう)と呼ばれる地方拠点を設置して支配を行いました。また、奄美群島での黒糖専売や琉球貿易により莫大な財政収入を得て、表高77万石に対して実質100万石を超える実力を持っていたとされています。藩校造士館では優秀な人材を育成し、幕末期には西郷隆盛、大久保利通らの維新の志士を輩出しました。
5. 現在の城跡と復元御楼門
現在の鹿児島城跡には、本丸跡に鹿児島県歴史資料センター黎明館、二の丸跡には鹿児島県立図書館、鹿児島市立美術館、鹿児島県立博物館などの文化施設が建てられています。2020年3月31日には、総工費10億9000万円をかけて御楼門が復元されました。この御楼門は日本最大の城門として復元され、現在は鹿児島のシンボルとして多くの観光客を迎えています。復元された御楼門は夜間にライトアップされ、石垣とともに幻想的な姿を見せています。黎明館には鹿児島城の詳細なジオラマが展示されており、往時の城の全貌を知ることができます。
6. 日本100名城としての価値
鹿児島城は平成18年(2006年)4月6日に日本100名城の97番に選定され、その歴史的価値が認められました。100名城スタンプは鹿児島県歴史・美術センター黎明館と鹿児島まち歩き観光ステーションの2か所に設置されています。城址碑と石垣がデザインされたスタンプは、鹿児島城の特徴をよく表現しています。黎明館では島津家に関する貴重な資料や薩摩の歴史を学ぶことができ、城跡見学と合わせて薩摩藩の歴史と文化を深く理解することができます。77万石の大藩でありながら質素な造りの城という特異な存在として、日本の城郭史において重要な位置を占めています。
7. 御城印と城跡グッズ
鹿児島城では複数種類の御城印が販売されており、基本版は300円で黎明館などで購入できます。御城印には島津家の家紋である「島津十字」(丸に十の字)がデザインされ、薩摩藩の歴史と威厳を表現しています。限定版や特別デザインの御城印も発行されており、コレクターに人気があります。黎明館のミュージアムショップでは、鹿児島城や島津家に関する書籍、絵葉書、記念品なども販売されており、登城の記念品として多くの観光客に愛用されています。また、復元された御楼門をモチーフにした新しいグッズも登場しています。
8. 西郷隆盛と城山
鹿児島城と密接に関連するのが、薩摩の英雄西郷隆盛の物語です。西南戦争で政府軍と戦った西郷隆盛は、最期に鹿児島城の背後にある城山で自刃しました。現在城山には西郷隆盛終焉の地の碑が建てられ、麓には西郷隆盛像があります。西郷隆盛像は鹿児島のシンボルの一つとなっており、多くの観光客が訪れています。また、城山からは鹿児島市街地と桜島を一望することができ、薩摩の雄大な自然と歴史を同時に感じることができる絶好の展望スポットとなっています。西郷軍の洞窟跡なども残されており、激動の幕末・明治維新期の歴史を肌で感じることができます。
9. アクセスと周辺観光
鹿児島城跡へのアクセスは、九州自動車道鹿児島ICから約15分、鹿児島中央駅からは市電「市役所前」下車徒歩5分、またはカゴシマシティビュー「薩摩義士碑前」下車すぐと非常に便利です。黎明館には無料駐車場も完備されています。周辺には照國神社(島津斉彬を祭神とする神社)、薩摩義士碑、西郷隆盛像、城山展望台などの史跡・観光スポットが徒歩圏内に点在しており、半日から一日かけて薩摩の歴史を巡ることができます。また、桜島フェリー乗り場や天文館繁華街も近く、鹿児島観光の起点として最適な立地にあります。
10. 保存活動と今後の展望
鹿児島城跡は国の史跡に指定され、石垣や堀などの遺構の保存活動が継続的に行われています。2020年の御楼門復元は大きな話題となり、鹿児島の新たな観光シンボルとして注目を集めています。今後も石垣の修復や遺構の発掘調査が計画されており、さらなる城跡整備が期待されています。黎明館をはじめとする文化施設では、薩摩の歴史と文化の発信拠点として、展示内容の充実や教育プログラムの開発が進められています。また、日本遺産「薩摩の武士が生きた町」の構成文化財としても位置づけられ、地域全体での歴史文化の保存と活用が推進されています。明治維新150周年以降も、薩摩藩の歴史的意義を国内外に発信し続ける重要な拠点としての役割を果たしています。
アクセスマップ
関連リンク
散歩記録

御城印情報

スタンプ情報
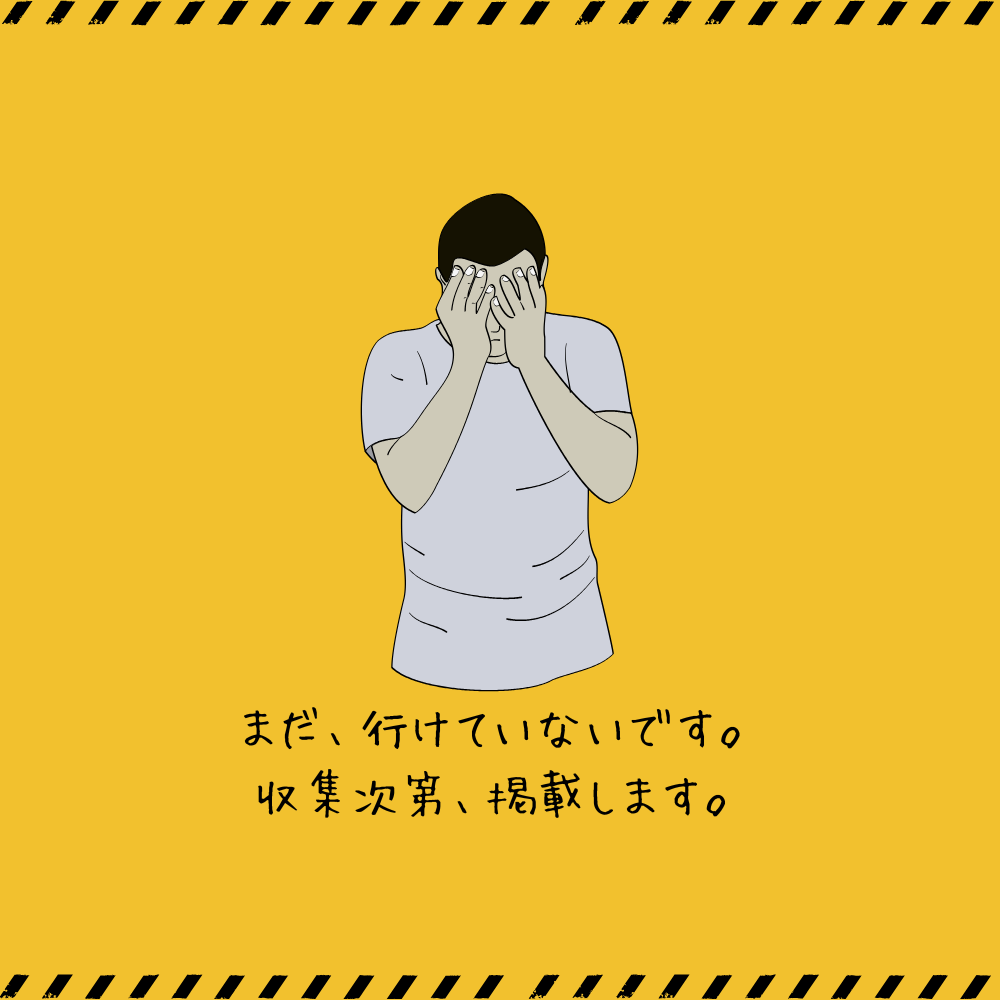
鹿児島まち歩き観光ステーション

