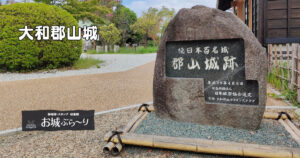160.飯盛城
続100名城基本情報
| 住所 | 大阪府大東市・四條畷市(飯盛山) |
|---|---|
| 電話 | 072-876-7011(大東市歴史民俗資料館 |
| 築城年 | 室町時代中期 |
営業情報
| 開館時間 | 9:30~19:30(大東市歴史民俗資料館) |
|---|---|
| 入場料 | 無料(城跡) 無料(大東市歴史民俗資料館) |
| 休館日 | 第1・第3火曜日・12月29日~1月3日 |
1. 飯盛城の歴史と立地
飯盛城は大阪府大東市と四條畷市にまたがる標高315.9mの飯盛山に築かれた中世の山城で、河内と大和の国境となる生駒山脈の北西支脈に位置し、室町時代中期に河内守護代の木沢長政により築城されたとされます。永禄3年(1560年)11月に三好長慶が芥川山城から拠点を移して以降、長慶が永禄7年(1564年)に42歳で没するまでの約4年間、この城は政権が所在する「首都」的な役割を担い、五畿内と四国一帯を統治する天下人の居城として機能しました。
2. 三好長慶の天下統一拠点
三好長慶は飯盛城を拠点に室町幕府の政治を動かし、織田信長に先駆ける戦国時代最初の天下人として評価される人物で、城には松永久秀をはじめとする重臣や奉行人らが常住し、天下の政治が行われました。長慶の死後、その遺体は御体塚郭に仮埋葬されたといわれ、3年間にわたってその死は秘匿されましたが、やがて織田信長の畿内進出により三好氏の勢力は衰退し、天正3年(1575年)に信長が河内を平定した際、飯盛城も廃城となりました。
3. 城郭構造と築城技術
飯盛城は中世の山城としてはかなり大きな部類に属し、全盛期には南北に1200m、東西に500mに達し、70以上の曲輪が確認される強固な要塞でした。特筆すべきは石垣を多用した構造で、織田信長の安土城に先駆ける貴重なもので、花崗岩の自然石をほぼ垂直に積み上げた野面積みの技術が使われ、数段にわたって築かれた石垣も確認されています。これらの石垣は建物の基礎というより土の押さえや城の威容を示すためのものと考えられ、後の時代の城郭建築に大きな影響を与えました。
4. 発掘調査と学術価値
平成28年(2016年)から3年かけて実施された大東市と四條畷市による共同調査により、城全体に石垣が造られていたことが明らかになり、織田信長の安土城以前の「石垣の城」として重要な発見がなされました。城内には多くの曲輪や堀切、土橋といった遺構が良好な状態で残り、大小114の曲輪が作られた城の広さは戦国時代の山城としては西日本有数の規模を誇り、日本の中世史・中世城郭史を研究する上で極めて重要な位置を占めています。
5. 現在の保存状況と文化財価値
現在の飯盛城跡は飯盛山ハイキングコースとして整備され、2021年10月11日に国史跡に指定されて文化財としての価値が公式に認められました。アクセスはJR学研都市線の四條畷駅や野崎駅から徒歩約1時間で、大東市立野外活動センターから山頂までは約20分の登山となり、続日本100名城スタンプは大東市歴史民俗資料館、四條畷市立歴史民俗資料館、大東市立野外活動センターの3ヶ所に設置されています。また大東市・四條畷市共同で制作された御城印は2枚並べると飯盛城跡縄張図が完成するデザインとなっており、両市の連携による城跡活用の先進事例として注目されています。
アクセスマップ
関連リンク
散歩記録

御城印情報

スタンプ情報

四條畷市立歴史民俗資料館
大東市立野外活動センター