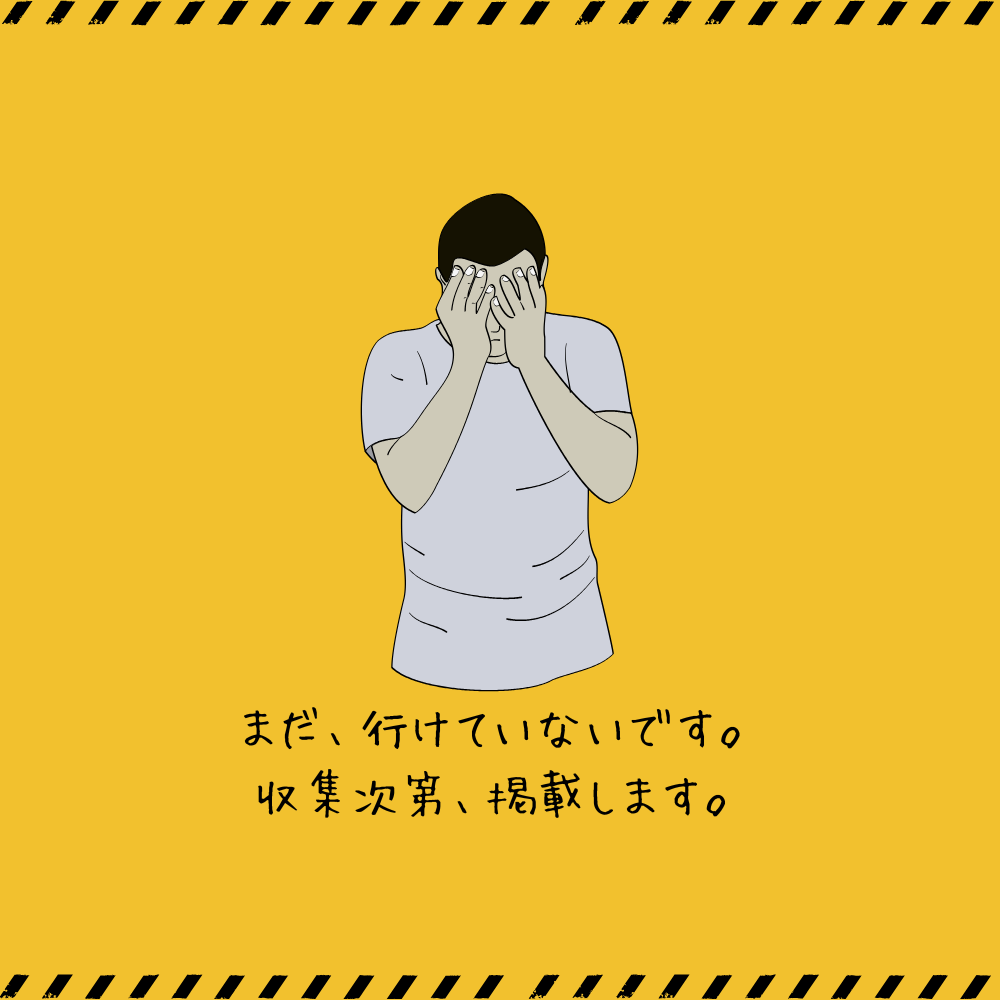93.人吉城
日本100名城基本情報
| 住所 | 〒868-0051 熊本県人吉市麓町18番地4 |
|---|---|
| 電話 | 0966-22-2324(人吉城歴史館) |
| 築城年 | 1448年(文安5年) |
営業情報
| 開館時間 | 9:00~17:00(入館は16:30まで) |
|---|---|
| 入場料 | 個人330円、団体(20人以上)220円、高校生以下無料 |
| 休館日 | 毎週火曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始(12月29日~1月3日) |
1. 人吉城の歴史と概要
人吉城は熊本県人吉市麓町にあった梯郭式平山城で、別名を繊月城、三日月城と呼びます。1198年(建久9年)に相良長頼が地頭として人吉荘に赴任して以来、明治まで相良氏35代670年間という日本史上最長の在城記録を持ちます。これほど長期間にわたって居城を変えなかった大名領主は、全国で相良氏のみという極めて稀有な存在です。人吉城は市内中央部を流れる球磨川の南側に位置し、球磨川とその支流胸川の合流点の山に築かれており、自然の地形を巧みに活用した堅固な城でした。
2. 相良氏の入部と築城の経緯
鎌倉時代初期の1198年(建久9年)、源頼朝の命により相良長頼がこの地に下向し、それ以前にこの地を所領していた平頼盛の代官、矢瀬主馬助を滅ぼして人吉城に入城しました。城の改修に取りかかる際、三日月模様を持つ石「繊月石」が見つかり、これに倣い繊月城が異名となりました。城として本格的に整備されたのは11代相良長続の時代1448年(文安5年)とされ、その後18代頼房から20代長毎にかけて石垣普請を含めた大改修が行われ、本丸・二の丸・堀・矢倉門が完成しました。
3. 球磨川を活用した水城の特徴
人吉城の最大の特徴は、日本三大急流の一つといわれる球磨川とその支流胸川を天然の堀として活用したことです。北側と西側を球磨川と胸川で囲み、東側と南側は山の斜面と崖を天然の城壁として、巧みに自然を利用した縄張りになっています。球磨川沿いに三の丸を配し、その南に二の丸、さらに丘陵上に本丸が配された構造で、多くの船着き場を設けて水運を活用し、物資の運搬や交通の要所として機能していました。本丸には天守は築かれず護摩堂があったとされています。
4. 幕末の大火と西洋式石垣の導入
1862年(文久2年)、城下の鉄砲鍛冶恒松寅助宅から出火した火事は大火となり、人吉城と城下の大半が焼失しました(寅助火事)。この火災を契機として、人吉城では武者返しをつけた西洋式石垣を導入し、外塀も土塀に変更されました。この石垣はヨーロッパの築城技術である槹出工法(はねだしこうほう)を応用したもので、日本では品川台場で初めて導入され、他に函館の五稜郭と龍岡城にしかない大変珍しいもので、規模は人吉城のものが最も大きいとされています。
5. 明治維新と廃城後の変遷
1871年(明治4年)の廃藩置県により人吉城は廃城となりましたが、その後1877年(明治10年)の西南戦争では西郷軍の拠点となり、官軍の攻撃で多くの建物が焼失しました。1872年(明治5年)からの払い下げにより城は石垣を残すのみとなっていました。長らく荒廃していた城跡でしたが、1961年(昭和36年)に国指定史跡となり、それ以前から「人吉城公園」として整備が進められていました。現在も清流と石垣、復元された櫓や長塀の景観が美しい調和を見せています。
6. 平成期の復元事業と整備
1989年(平成元年)には隅櫓が復元され、1993年(平成5年)には大手門脇多門櫓などが木造で復元されました。これらの復元により、往時の城の威容が蘇り、人吉城公園として市民や観光客に親しまれる史跡となりました。復元された多門櫓内部では、人吉城の絵図や発掘された出土品などが展示され、土・日曜日、祝日には無料で見学することができます。城跡の整備により、石垣の美しさや縄張りの巧妙さを間近で観察できる貴重な史跡として評価が高まりました。
7. 人吉城歴史館と地下室遺構
2005年(平成17年)に開館した人吉城歴史館は、旧相良清兵衛屋敷内に建設された施設で、全国的に例のない井戸を備えた石造り地下室の遺構がそのまま保存・展示されています。この地下室遺構は発掘調査で発見されたもので、3Dモデルも作成され一般に公開されています。歴史館では人吉城の構造や相良氏670年の歴史に関する資料が展示され、城のジオラマ模型、別称の由来となった「繊月石」なども見ることができ、人吉城と相良氏の理解を深める重要な施設となっています。
8. 令和2年7月豪雨と復旧への歩み
2020年(令和2年)7月3日からの大雨(令和2年7月豪雨)により、人吉城址も甚大な被害を受け、人吉城歴史館は施設設備復旧のため休館を余儀なくされました。しかし、2025年7月にリニューアルオープンを果たし、地域復興のシンボルとしての役割を再び担うことになりました。災害からの復旧過程では、地下室遺構の保護や石垣の安全確認など、文化財保護の観点からも重要な取り組みが行われ、地域住民と行政が一体となって史跡の保存と活用に努めました。
9. 日本100名城スタンプと御城印
人吉城は2006年4月6日に日本100名城の93番に選定されました。スタンプは人吉城歴史館東側駐車場に設置された倉庫内に置かれ、24時間いつでも押印が可能となっています。これは豪雨災害の影響で歴史館が休館していた期間中も観光客への配慮として設置されたもので、現在も継続されています。御城印は人吉城歴史館や人吉城多門櫓(土日祝日のみ)で300円で販売されており、相良氏の家紋や繊月城の文字が美しくデザインされています。4種類の御城印が販売されており、コレクション性も高く人気を集めています。
10. アクセスと見学のポイント
人吉城へのアクセスは、JR九州肥薩線人吉駅から徒歩約25分、または九州産交バス「五日町」下車徒歩9分です。車の場合は九州自動車道人吉ICから約10分で、無料駐車場(乗用車50台)が完備されています。見学のポイントは、武者返しの石垣や胸川際からの美しい景観、復元された多門櫓、そして人吉城歴史館の地下室遺構です。城跡からは人吉盆地や球磨川の流れを一望でき、自然と歴史が調和した美しい風景を楽しめます。また、隣接する青井阿蘇神社(国宝)や相良護国神社なども合わせて見学することで、相良氏670年の歴史をより深く理解することができます。春には桜の名所としても知られ、四季を通じて美しい景観を楽しめる史跡です。
アクセスマップ
関連リンク
散歩記録

御城印情報

人吉城多門櫓(土日祝日のみ)
スタンプ情報