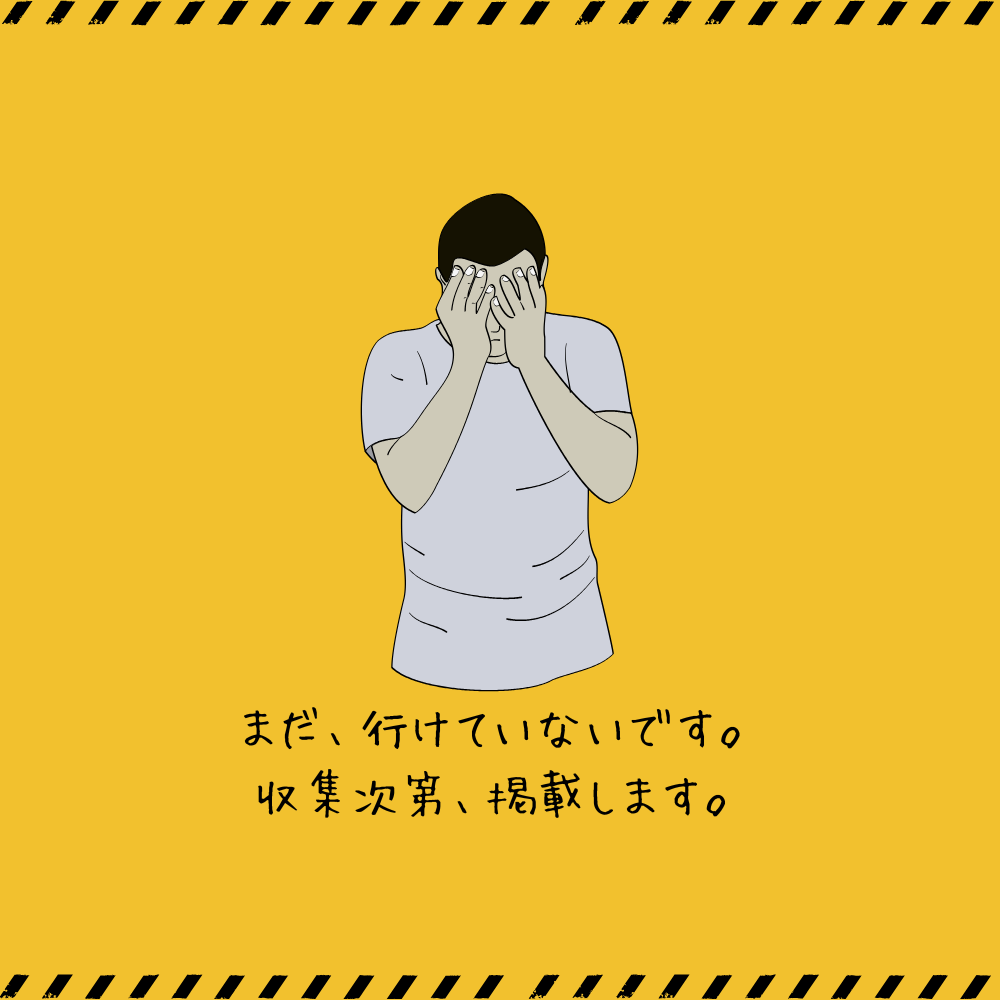73.広島城
日本100名城基本情報
| 住所 | 〒730-0011 広島県広島市中区基町21-1 |
|---|---|
| 電話 | 082-221-7512 |
| 築城年 | 1589年(天正17年) |
営業情報
| 開館時間 | 3月〜11月:9:00〜18:00(入館は17:30まで) 12月〜2月:9:00〜17:00(入館は16:30まで) ※5月〜8月・3月の土日祝、5/1-2、8/12-15:9:00〜19:00 |
|---|---|
| 入場料 | 大人(18歳以上65歳未満):370円 大人(65歳以上):180円 高校生及び18歳未満:180円 小・中学生・乳幼児:無料 |
| 休館日 | 12月29日〜12月31日、臨時休館あり |
1. 広島城の概要と歴史的意義
広島城は、中国地方一帯を領有した戦国大名・毛利輝元が天正17年(1589年)に築城を開始した平城です。太田川河口の三角州という水陸交通の要衝に位置し、「鯉城(りじょう)」の愛称で親しまれています。関ヶ原の戦い後は福島正則、その後は浅野氏12代の居城となり、明治維新まで続きました。昭和20年(1945年)の原爆投下により全ての建物が倒壊しましたが、昭和33年(1958年)に天守閣が再建され、広島復興のシンボルとして現在に至ります。日本100名城の一つに選定され、日本三大平城の一つにも数えられる名城です。
2. 毛利輝元による築城と「島普請」
毛利輝元は郡山城から本拠を移すため、太田川河口の三角州に新たな城を築くことを決断しました。この築城は「島普請」と呼ばれるほどの大規模な土地造成を伴い、城の完成には約10年を要しました。築城にあたっては豊臣秀吉の大阪城や聚楽第の影響を受けたとされ、五重五階の大天守に三重三階の小天守を配し、渡り廊下でつなぐ連結式天守を採用しました。本丸を囲む内堀に面して23基の櫓が配置され、当時としては最新の築城技術が用いられました。天正19年(1591年)に輝元が入城し、新たな毛利氏の本拠地として機能しました。
3. 福島正則による城郭の拡張整備
関ヶ原の戦い後、毛利輝元に代わって福島正則が広島城に入封し、城郭の大幅な拡張整備を行いました。福島氏は内堀・中堀・外堀の三重の堀を完成させ、88基の櫓と10基の門を配置して防備を大幅に強化しました。城域は東西南北約1キロメートル、面積約90万平方メートルの全国最大級の規模となり、現在のマツダスタジアム約25個分の広さを誇りました。城内には本丸御殿や城主一族の屋敷、役所や蔵、大身の侍の屋敷が立ち並び、城下町の整備も同時に進められました。しかし元和5年(1619年)、台風被害の修築を幕府に無断で行ったため武家諸法度違反で改易となりました。
4. 浅野氏12代の治世と城下町の発展
福島正則の改易後、浅野長晟(ながあきら)が広島城に入封し、以後明治維新まで浅野氏12代約250年間の居城となりました。浅野氏時代には大規模な城普請は行われませんでしたが、干拓事業が継続的に実施され、城下町は当初の5〜6倍の規模にまで拡大しました。浅野氏は文治政治を重視し、学問や文化の振興に努めました。城内には藩校や文庫が設置され、多くの学者や文人が育成されました。また、洪水や地震などの自然災害にたびたび見舞われ、その都度復旧工事が行われました。特に寛永元年(1624年)の地震では石垣や櫓、塀などが大きな被害を受けました。
5. 天守閣の建築様式と特徴
広島城大天守は望楼型天守の代表例で、入母屋造の大きな屋根を持つ基部の上に望楼(物見)を配した構造になっています。二層までが基部、三層より上が望楼部分で、この様式は関ヶ原の戦い以前の古い形式です。外壁は白漆喰の壁の一部を黒い板で覆う「下見板張」と呼ばれる仕上げが施されており、これは豊臣秀吉の大阪城をモデルにしたとされています。風雨にさらされる部分を下見板で保護する実用的な工夫で、大天守のみならず城内の各種櫓にも採用され、広島城の特色の一つとなっていました。内部は五重五階の構造で、各階には城主の居住空間や政務室、武具庫などが配置されていました。
6. 原爆による被災と戦後復興
昭和20年(1945年)8月6日、アメリカ軍による原子爆弾投下により、広島城の全ての建物が倒壊しました。明治時代以降も残されていた大天守や渡櫓、表御門などの貴重な文化財も一瞬にして失われました。戦後、昭和28年(1953年)に城跡が国の史跡に指定されると天守再建の機運が高まり、昭和32年(1957年)の広島復興大博覧会に合わせて天守閣の再建が決定されました。昭和33年(1958年)3月に竣工し、同年6月1日に広島城郷土館(現在の博物館)として開館しました。鉄筋コンクリート造による外観復元でしたが、広島市民にとって復興のシンボルとして大きな意味を持ちました。
7. 現在の天守閣と博物館展示
現在の広島城天守閣は、昭和33年(1958年)に再建された鉄筋コンクリート造の建物で、内部は広島の歴史を紹介する博物館となっています。一層では広島城の構造や毛利輝元による築城、広島藩の政治史などを実物資料や模型で展示し、二層では広島城下絵屏風(複製)をはじめとする城下町の様子を紹介しています。三層では広島ゆかりの刀剣や甲冑、浅野家の馬印などの武具を展示し、四層では企画展示室として様々なテーマ展を開催しています。五層は展望室となっており、広島市内を一望でき、天気の良い日には宮島まで望むことができます。年間6本程度の企画展も開催されています。
8. 二の丸の復元と馬出の機能
平成6年(1994年)には二の丸の復元整備が完了し、平櫓、多聞櫓、太鼓櫓、表御門、御門橋が木造で復元されました。広島城二の丸は「馬出(うまだし)」としての性格を持つ特徴的な構造で、本丸の虎口である中御門を守る重要な防御施設でした。二の丸は本丸とは土橋で、東側の三の丸とは御門橋で繋がり、各々とは独立した形で存在しています。敵が本丸に攻め込む際は、御門橋を渡って表御門を突破し、二の丸を通過してさらに土橋を渡る必要があり、二の丸の防衛上の重要性が理解できます。復元された櫓群は内部も見学可能で、当時の武士の生活や城の防御システムを学ぶことができます。
9. 城址公園としての現在と周辺環境
現在の広島城跡は広島市中央公園内に位置し、内堀を含む本丸跡と二の丸跡の範囲約12万平方メートルが国の史跡として保護されています。公園内にはソメイヨシノを中心に約350本の桜が植えられており、春には多くの花見客で賑わいます。また、同じ敷地内には広島護国神社が鎮座し、多くの参拝者が訪れています。城の周辺は広島市の中心部として発展し、かつての三の丸跡には広島県庁や広島市民病院、基町高等学校などが建設されています。原爆ドームや平和記念公園へも徒歩圏内で、広島観光の重要な拠点となっています。交通アクセスも良好で、路面電車「紙屋町東」から徒歩約15分の立地です。
10. 日本100名城スタンプと見学のポイント
広島城は日本100名城の73番に選定されており、スタンプは天守閣入口前通路に設置されています。年末(12月29日〜31日)以外はいつでも押印可能です。見学のポイントとしては、まず二の丸の復元建物群で戦国時代の城郭建築を体感し、続いて天守閣で広島の通史を学ぶコースがおすすめです。天守閣からの眺望は必見で、広島市内の街並みと瀬戸内海の島々を一望できます。御城印は天守閣1階のミュージアムショップで300円で販売されており、毛利家・福島家・浅野家の家紋をモチーフにした朱印が押されています。見学所要時間は1〜2時間程度で、周辺の縮景園や原爆ドームと合わせた観光コースも人気です。
アクセスマップ
関連リンク
散歩記録

御城印情報

スタンプ情報