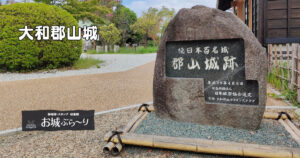157.八幡山城
続100名城基本情報
| 住所 | 滋賀県近江八幡市宮内町 |
|---|---|
| 電話 | 0748-32-0303 |
| 築城年 | 天正13年(1585年) |
営業情報
| 開館時間 | 9:00~17:00(八幡山ロープウェー) |
|---|---|
| 入場料 | 大人:片道500円、往復880円/小人:片道250円、往復440円 |
| 休館日 | 無休 |
1. 八幡山城の歴史と立地
八幡山城は天正13年(1585年)に豊臣秀吉の甥である羽柴秀次が築いた山城で、近江八幡市街地のすぐ北側にある標高283mの八幡山に位置し、安土城落城の3年後に織豊政権の近江支配の新たな拠点として建設された重要な城郭です。秀次は後に関白となった人物であり、この城は豊臣政権における近江統治の中枢として機能しました。
2. 城郭構造と築城技術
八幡山城は最頂部の本丸を中心に、南東に二の丸、西に西の丸、北に北の丸、南西の尾根上に出丸を配置する構造を持ち、山頂から八の字形に広がる尾根上の小曲輪と、尾根に挟まれた南斜面中腹に秀次館跡と家臣団館跡群を階段状に配した立体的な縄張りが特徴です。特に秀次居館跡では巨大な内枡形の食い違い虎口や算木積みの高石垣、鏡石積みによる権威の象徴的石垣など、高度な築城技術が確認されています。
3. 城下町と商業政策
八幡山城の城下町は安土城の城下町の町民を移住させて形成され、横筋4通り、縦筋12通りを中心とした碁盤目状の整然とした町並みが築かれ、他の城下町が防備重視でジグザグの町筋を採用するのに対し、商業振興第一主義に切り替えた平和的政策が特徴的でした。東から二筋を大工町、鍛冶屋町、畳屋町、鉄砲町などの職人居住区とし、三筋目から西を仲屋町筋、為心町筋、魚屋町筋、新町筋、小幡町などの商人街として計画的に配置し、これが後の近江商人発祥の礎となりました。
4. 発掘調査と貴重な発見
平成の発掘調査により秀次居館跡では書院造の御殿があったと推定される大型礎石建物跡と金箔瓦が多数出土し、特に秀次の馬印である沢瀉紋の飾り瓦など貴重な遺物が確認され、また安土城の2倍に達する約270mの大手道や東西300m×南北100m余りの巨大な平坦地など、権力者の居館としての規模の大きさが明らかになっています。これらの発見により八幡山城の歴史的価値と築城技術の先進性が学術的に実証されました。
5. 現在の保存状況と観光価値
現在の八幡山城跡には石垣を残すのみですが、本丸跡には秀次菩提寺の村雲御所瑞龍寺が京都から移築され、八幡山ロープウェーにより山頂へのアクセスが容易になり、北の丸跡や西の丸跡からは琵琶湖や比良山系を一望できる絶景スポットとして多くの観光客が訪れています。また八幡堀とともに重要伝統的建造物群保存地区に指定された城下町の街並みも含めて、戦国時代から近世初期の歴史文化を体感できる貴重な史跡として保存整備されています。
アクセスマップ
関連リンク
散歩記録

御城印情報

スタンプ情報