196.佐土原城
続100名城基本情報
| 住所 | 宮崎県宮崎市佐土原町上田島8202-1 |
|---|---|
| 電話 | 0985-74-1518(宮崎市佐土原歴史資料館) |
| 築城年 | 建武年間(1334-1338年) |
営業情報
| 開館時間 | 鶴松館:土日祝日9:00-16:30(入館16:00まで) |
|---|---|
| 入場料 | 入館無料 |
| 休館日 | 平日(鶴松館) |
1. 佐土原城の歴史
佐土原城は建武年間(1334年から1338年)に田島氏一族の田島休助により築かれました。応永34年(1427年)頃に伊東祐賀が入城し佐土原氏を名乗り、後に伊東四十八城の一つとなりました。天文5年(1536年)に焼失しましたが、天文11年(1542年)から天文12年(1543年)にかけて新たに鶴松城として再建されました。その後島津氏によって伊東氏が豊後国に追いやられると、島津家久が入城し、天正15年(1587年)に家久が急死すると息子の豊久が城主となりました。
2. 佐土原城の特徴
佐土原城は山城と麓の館がセットになった構造で、本丸、南ノ城、松尾丸の3つの大きな曲輪を中心に小規模な曲輪や空堀で構成されています。平成9年(1997年)の発掘調査で天守台跡と金箔鯱瓦が発見され、日本最南端の天守の存在が確実となりました。本丸の北側には櫓台(天守台)があり、一部の曲輪には織豊城郭の影響を受けた桝形虎口の跡が残っています。現在は二の丸御殿の一部が復元され(鶴松館)、佐土原城跡歴史資料館として公開されています。
3. 島津氏の居城として
慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いで豊久が討死にしたため佐土原は徳川氏の預かるところとなりましたが、慶長8年(1603年)に垂水島津氏の以久が3万石で佐土原藩主となり明治まで続きました。2代藩主忠興は幕府の許可を得て山上にあった政庁を現在の鶴松館がある二の丸に移し、佐土原藩の藩庁として使用されました。最後の藩主忠寛は版籍奉還後に政庁を佐土原から広瀬に移すことを決め、明治3年(1870年)に広瀬城の築城を始めたため佐土原城は破却されました。
4. 現在の佐土原城
佐土原城跡は平成16年(2004年)に国指定史跡となり、平成5年(1993年)に発掘調査を基にした二の丸御殿(復興)が鶴松館として造られました。山城部分は2018年の台風24号による被害を受けましたが2021年に再開放されました。鶴松館では佐土原島津家に伝わる屏風や鎧兜などが展示され、土日祝日のみ開館しています。城の駅佐土原いろは館では観光案内や地域の物産販売を行っています。
5. 訪問情報
佐土原城跡へはJR日豊本線佐土原駅からバス「西都行き」で東春田下車徒歩8分でアクセスできます。続100名城スタンプは土日祝日は鶴松館、平日は城の駅佐土原いろは館に設置されています。御城印は城の駅佐土原いろは館で300円で販売されており、通常版をはじめ複数のデザインが用意されています。本丸跡までの登城路は整備されており所要時間は約20分で、堀切や虎口、本丸跡の天守台などを見ることができます。山城部分の見学の際は動きやすい服装と履き物がおすすめです。
アクセスマップ
関連リンク
散歩記録

御城印情報

スタンプ情報
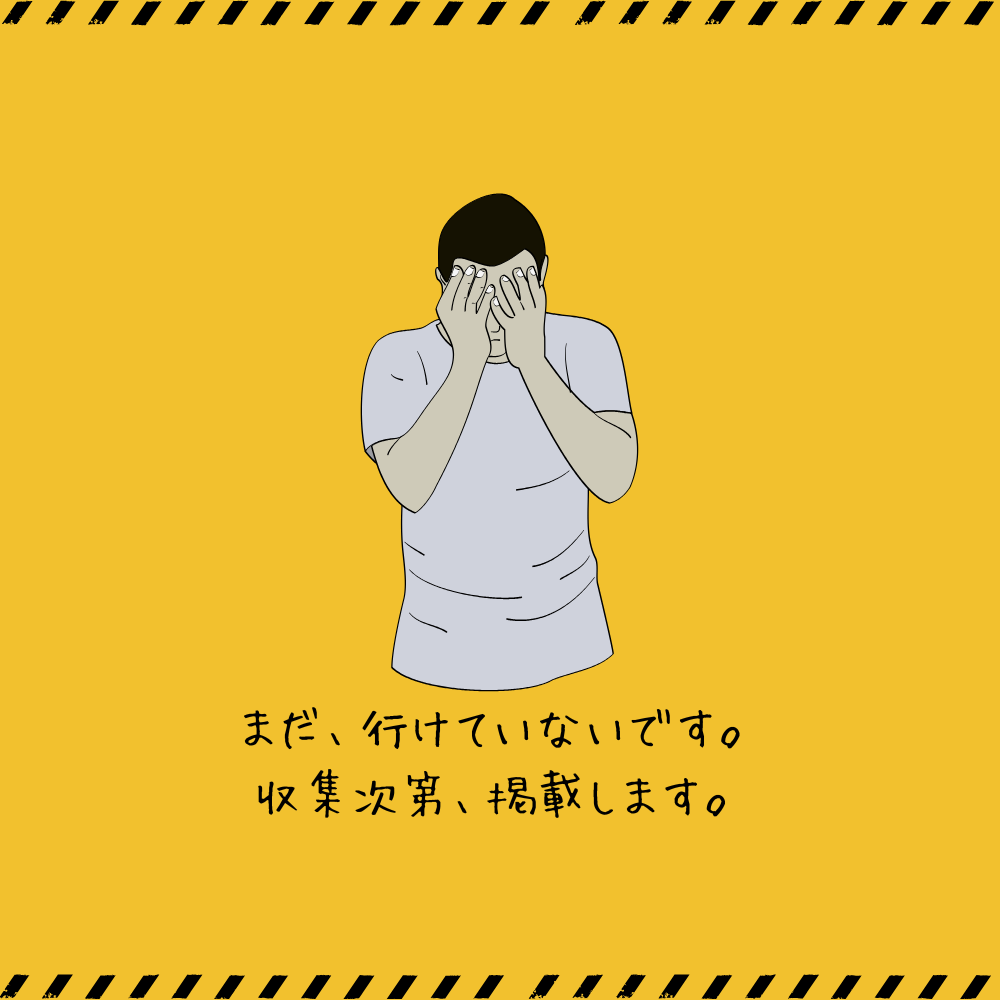
■平日:城の駅佐土原いろは館(年中無休、1月1-3日休)

