187.福江城
続100名城基本情報
| 住所 | 長崎県五島市池田町1-1 |
|---|---|
| 電話 | 0959-74-5400(五島観光歴史資料館) |
| 築城年 | 1863年(文久3年) |
営業情報
| 開館時間 | 9:00~17:00(五島観光歴史資料館) |
|---|---|
| 入場料 | 300円(五島観光歴史資料館) |
| 休館日 | 月曜日(祝日の場合は翌日)・12月29日~1月3日 |
1. 福江城の概要と地理的特性
福江城は長崎県五島市池田町に位置する近世末期の海城で、五島列島の福江島に築かれた日本最後の城として知られています。別名石田城とも呼ばれ、築城当時は日本で唯一三方を海で囲まれた海城という特異な立地条件を持っていました。現在は周囲の埋め立てにより内陸の城となっていますが、城郭の東西160間(約291メートル)、周囲1235間(約2246メートル)の規模を持ち、幕末期の海上防衛施設としての特徴を色濃く残しています。石垣や石橋、現存する蹴出門などの遺構が往時の姿を偲ばせています。
2. 築城の歴史的背景と幕末情勢
福江城の築城は、嘉永2年(1849年)から文久3年(1863年)にかけて行われ、五島藩第30代藩主五島盛成によって開始され、その子盛徳の代に完成しました。築城の背景には、ペリー来航以降の幕末情勢の変化があり、黒船をはじめとする異国船の来航に備えるため、江戸幕府から特別に築城許可を得て建設されました。15年の歳月と延べ5万人の人夫、2万両という巨額の工費を投じて完成した城は、開国による海防強化という時代の要請を体現した軍事施設でした。しかし完成からわずか9年後の明治4年(1871年)に廃城となり、明治政府によって解体されました。
3. 城郭構造と軍事的特徴
福江城は幕末期の海上防衛という特殊な目的に対応した城郭構造を持ち、城内には台場(砲台)が設けられるなど、従来の城郭にはない軍事的特徴を備えていました。本丸、二の丸、三の丸からなる連郭式の縄張りで、本丸には藩主居住施設、二の丸には政庁機能が配置されていました。石垣は切込接の精巧な技法で築かれ、枡形虎口や食い違いなどの防御施設も設けられています。特に現存する蹴出門は城の裏門として機能し、緊急時の脱出路としての役割も担っていたと考えられます。
4. 五島氏の統治と文化的遺産
五島氏は平安時代から続く名族で、戦国時代を経て江戸時代には外様大名として五島列島を統治しました。福江城の築城主である五島盛成は、藩政改革や産業振興に努めるとともに、文化的な基盤整備も行いました。二の丸跡に現存する五島氏庭園は、盛成の隠居所として造営された池泉回遊式庭園で、心字池を中心とした美しい景観が国の名勝に指定されています。庭園内の建築物や石組み、植栽は江戸時代末期の大名庭園の特徴を良好に保存し、五島氏の文化的素養と美意識を現代に伝える貴重な文化遺産となっています。
5. 近代化への対応と文化財的価値
明治維新後の福江城は、本丸跡に長崎県立五島高等学校が建設され、教育施設として新たな役割を担うようになりました。城跡は長崎県指定史跡として保護され、五島氏庭園は国指定名勝として文化財的価値が認められています。現在は北の丸跡に五島観光歴史資料館や五島市立図書館、文化会館が建設され、地域の文化拠点として機能しています。福江城は日本最後の城という歴史的意義に加え、幕末期の海防思想と築城技術、大名文化の総合的な研究資料として重要な価値を持ち、近世城郭史の最終段階を示す貴重な史跡として評価されています。
アクセスマップ
関連リンク
散歩記録

御城印情報

スタンプ情報
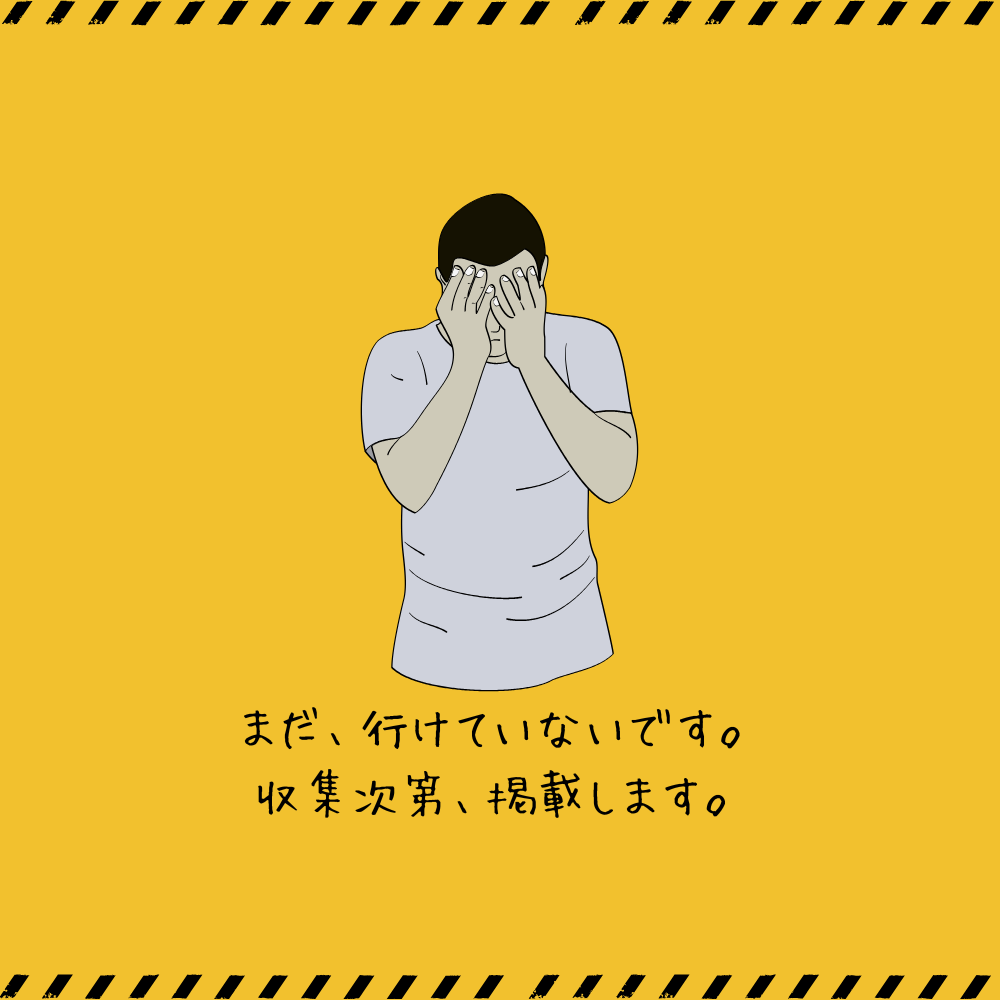
五島観光歴史資料館

