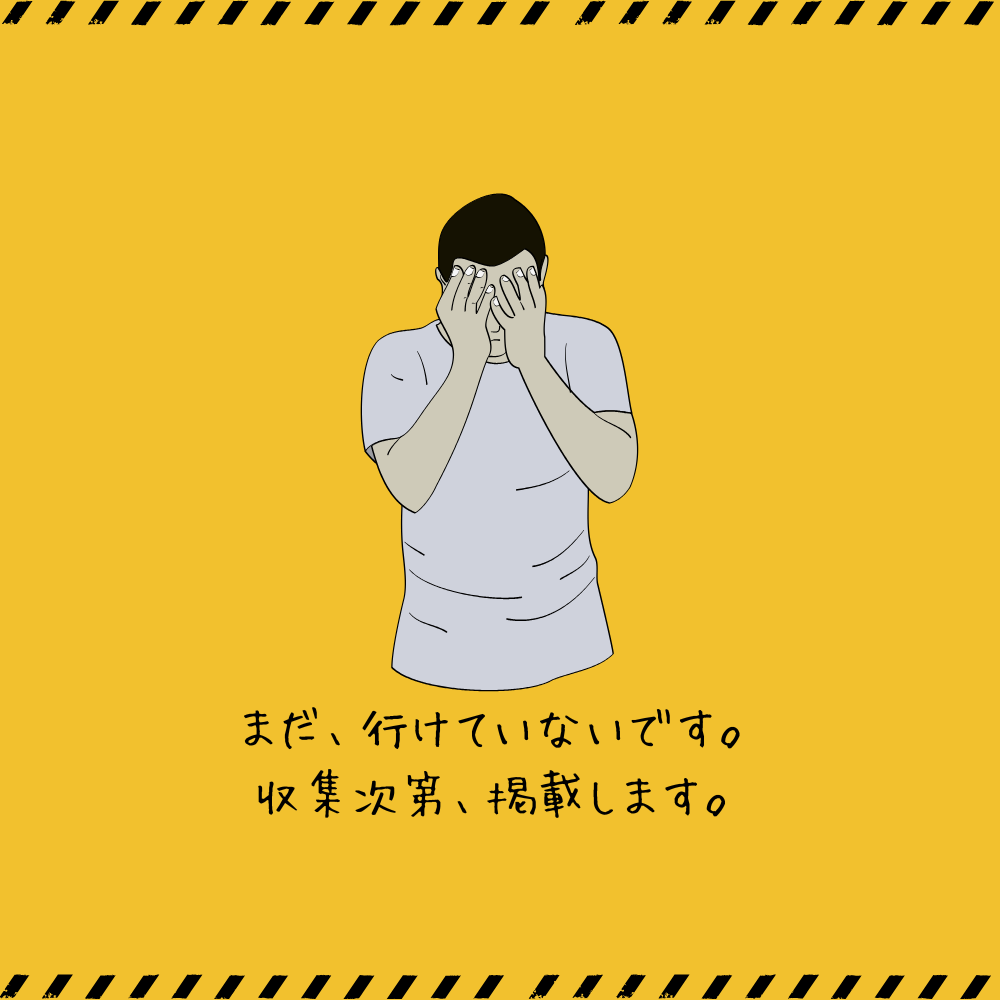182.水城
続100名城基本情報
| 住所 | 福岡県太宰府市国分2-17-10(水城館) |
|---|---|
| 電話 | 092-555-8455(水城館) |
| 築城年 | 664年(天智天皇3年) |
営業情報
| 開館時間 | 9:00〜16:30(水城館) |
|---|---|
| 入場料 | 無料 |
| 休館日 | 月曜日(祝日の場合はその翌日)、12月28日〜1月4日 |
1. 水城の歴史と築城の背景
水城は福岡県太宰府市・大野城市・春日市にまたがって築かれた日本の古代の城です。城跡は1953年(昭和28年)に国の特別史跡「水城跡」に指定されており、日本最古級の防衛施設として重要な歴史的価値を持っています。
築城の背景は663年の白村江の戦いでの大敗にあります。唐・新羅連合軍に敗れた大和朝廷は、本土への侵攻を恐れて急速に防衛体制の整備を進めました。天智天皇3年(664年)、筑紫国に大堤を築いて水を貯えさせ、これを「水城」と名付けたと『日本書紀』に記録されています。この水城は、朝鮮半島の百済国の都・扶余の東羅城と同じ高度な土木技術を駆使して建設され、当時の国際情勢の緊迫を物語る重要な遺跡となっています。
2. 水城の構造と築造技術
水城は博多湾側の福岡平野から筑紫(太宰府)に通じる平野を閉塞する「遮断城」として機能していました。全長約1.2km、高さ約9m、基底部の幅約80m、上部の幅約25mという巨大な二段構造の土塁で構成され、東西の端部には東門と西門が設けられていました。土塁の博多側には幅60m、深さ4mほどの外濠が存在し、「水城」の名前の由来となっています。
築造技術も非常に高度で、軟弱地盤を強化するために土塁の最下層部に多量の枝葉を敷き詰める「敷粗朶(しきそだ)工法」が用いられています。また、土塁の上層部は土質の異なる積土を10cm程度の単位で硬く締め固めて積み上げる「版築(はんちく)工法」により構築されており、これらは当時の朝鮮半島の最先端土木技術でした。土塁には長さ79.5m、内法幅1.2m、高さ0.8mの木製導水管「木樋(もくひ)」が埋設され、外濠への給水システムが整備されていました。
3. 古代防衛システムの中核拠点
水城は単独で存在していたのではなく、古代日本の総合的な防衛システムの中核を担っていました。背後には大野城や基肄城といった古代山城が配置され、九州北部の防衛ラインを形成していました。また、水城の西方には複数の小規模な土塁遺構があり、これらは「小水城」と総称されて水城と連携した防衛網を構築していました。
この防衛システムは、対馬島・壱岐島に配備された防人(さきもり)や烽(のろし)による情報伝達システムと連動しており、7世紀後半の日本が取り組んだ一大国家事業でした。九州だけでなく瀬戸内海沿岸にも同様の城郭が配置され、一体的・計画的に築かれた古代日本の国防戦略の壮大さを物語っています。
4. 大宰府政庁との関係と発展
水城は軍事的防衛施設として出発しましたが、やがて大宰府政庁の発展とともにその性格も変化していきました。東門と西門は大宰府への主要な出入口となり、特に西門は大宰府と筑紫館(後の鴻臚館)を結ぶ儀礼的な外交の主要道として8世紀後半まで重要な役割を果たしました。
外国使節や都からの官人らを迎える場所として機能し、大宰府を訪れる人々との出会いと別れの舞台ともなりました。土塁の修理や門の建て替えを経ながら大宰府を守護し続けましたが、平安時代の終わりごろにはその役割を終えていったと考えられています。この長期間にわたる使用は、水城の重要性と古代日本における大宰府の政治的地位を示すものです。
5. 現代における保存と活用
現在の水城跡は国の特別史跡として厳重に保護されており、1350年を経た現在でもその壮大な土塁の姿を目にすることができます。1970年から本格的な発掘調査が開始され、福岡県教育委員会・九州歴史資料館・太宰府市・大野城市が継続的に調査を行っています。2013年から2014年にかけては、100年ぶりの土塁断面再調査が実施され、新たな知見が得られました。
2017年には水城東門跡に水城館が開館し、水城の歴史や構造について多言語での解説展示が行われています。館内には展望台も設けられ、水城跡を一望できるほか、無料の休憩スペースも提供されています。春には菜の花、秋にはコスモスが濠跡一面に咲き誇り、多くの観光客が訪れる景勝地としても親しまれており、古代の防衛遺跡としての学術的価値と現代の観光資源としての魅力を両立させています。
アクセスマップ
関連リンク
散歩記録

御城印情報

スタンプ情報