177.引田城
続100名城基本情報
| 住所 | 香川県東かがわ市引田 |
|---|---|
| 電話 | 0879-33-2533(引田公民館) |
| 築城年 | 天正15年(1587年) |
営業情報
| 開館時間 | なし(屋外) |
|---|---|
| 入場料 | 無料 |
| 休館日 | なし |
1. 引田城の歴史的背景と築城経緯
引田城は播磨灘を望む標高82mの城山に築かれた平山城で、三方を海に囲まれた天然の要害を利用した海城としても機能していました。城の歴史は古く、天智天皇6年(667年)に屋嶋城築城の際、安倍比羅夫率いる引田氏によって狼煙台として造られたのが始まりとされています。永正年間(1504~1521年)頃には昼寝城主寒川元政の家臣四宮右近が城主となり、元亀3年(1572年)には三好長治の侵攻により矢野駿河守が城主となりました。
2. 仙石秀久の入城と戦略的価値
天正10年(1582年)の中富川合戦後、豊臣秀吉は長宗我部氏への対策として仙石権兵衛秀久を引田城に派遣し、四国征伐の拠点として活用しました。四国征伐後、仙石秀久は讃岐国を領有し引田城主となりましたが、九州征伐での戸次川合戦の失態により改易となりました。この間、引田城は阿波との国境守備の重要拠点として機能し、瀬戸内海の制海権確保において戦略的価値を発揮していました。
3. 生駒親正による城郭整備と石垣技術
天正15年(1587年)、播磨国赤穂から移封された生駒親正が讃岐国17万6千石を得て入城し、引田城を本格的な近世城郭として整備しました。生駒氏は高松城を本城とし、西に丸亀城、東に引田城を配置する三城体制を構築しました。引田城では讃岐国で初めて総石垣による築城が行われ、現在も残る野面積みの石垣は算木積み部の隅間に間詰め石を使用した古い積み方で、引田城で初めて築かれた石垣と考えられています。建物の礎石や多くの瓦も発見されており、織田信長の安土城から始まった織豊系城郭の特徴を示しています。
4. 城郭構造と防御機能
引田城は化粧池のある谷を囲むようにU字型に展開する尾根上に築かれ、本丸を南側に配置し、北二の丸と南二の丸の間に大手門を設けた巧妙な縄張りとなっています。東側に延びる尾根には東の丸が築かれ、北の離れた場所には出丸のような北曲輪が配置されました。化粧池は城内の女性たちが化粧に使用したとされる一方、岩山特有の水不足を解決するための人工貯水池としても機能していました。北二の丸には御殿があったとされ、発掘調査により建物の礎石と瓦が多数発見されています。
5. 一国一城令による廃城と史跡指定
慶長20年(1615年)の一国一城令により引田城は廃城となりましたが、その後いつ取り壊されたかは不明で、長らく忘れられた存在でした。しかし、近年の文化財保護意識の高まりにより調査・保存の機運が高まり、平成12年(2000年)12月20日に「城山国有林(引田城址)」として市指定史跡に指定されました。その後、令和2年(2020年)3月10日に東かがわ市内初の国史跡に指定され、平成29年(2017年)には公益財団法人日本城郭協会により続日本100名城に選定されました。現在も生駒氏時代の石垣遺構が良好に保存され、高松城・丸亀城では失われた生駒時代の貴重な石垣技術を今に伝えています。
アクセスマップ
関連リンク
散歩記録

御城印情報

スタンプ情報
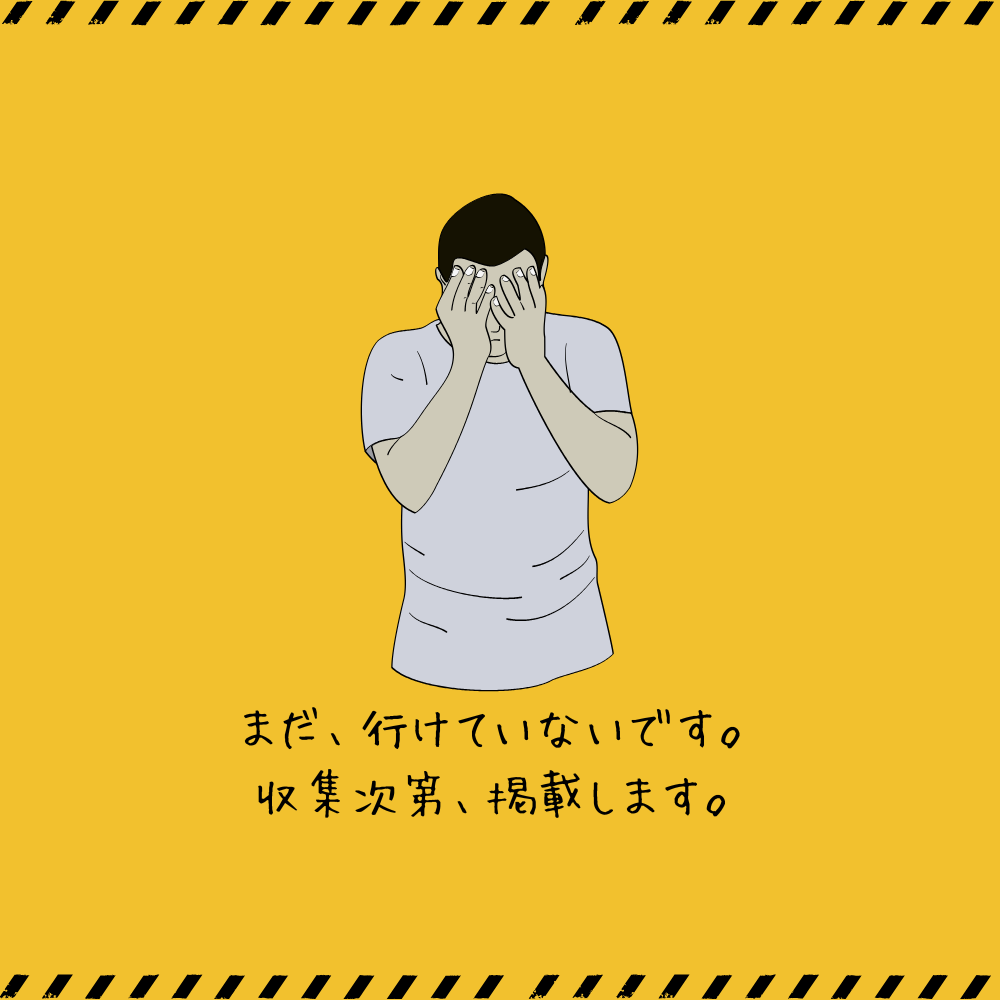
引田公民館

