174.大内氏館・高嶺城
続100名城基本情報
| 住所 | 山口県山口市大殿大路(大内氏館) 山口県山口市上宇野令(高嶺城) |
|---|---|
| 電話 | 083-920-4111(山口市教育委員会文化財保護課) |
| 築城年 | 大内氏館:1360年頃(山口古図)/1400年代半ば(発掘調査) 高嶺城:弘治2年(1556年) |
営業情報
| 開館時間 | 常時開放(史跡) |
|---|---|
| 入場料 | 無料 |
| 休館日 | なし |
1. 大内氏館・高嶺城の概要と歴史的背景
大内氏館・高嶺城は、山口県山口市に位置する大内氏の城館群で、続日本100名城の174番に選定されています。大内氏館は大内氏24代当主の大内弘世が山口を本拠と定めた際に築かれた居館で、江戸時代の「山口古図」では14世紀半ばの1360年頃の築城とされていますが、発掘調査では1400年代半ば第13代大内教弘の建築である可能性が高いとされています。
高嶺城は大内氏最後の当主である大内義長が、弘治2年(1556年)に毛利元就の脅威に備えて築城した山城です。標高338mの鴻ノ峰頂上に築かれ、大内氏館の詰の城として機能する予定でしたが、未完成のまま毛利軍の侵攻を受けることとなりました。弘治3年(1557年)、義長は高嶺城から脱出して長門国へ逃亡し、大寧寺で自害して大内氏は滅亡しました。
2. 大内氏館の構造と築城技術
大内氏館は京都を模した山口の街に相応しく「城」ではなく「館」として建てられた方形の居館で、最盛期には堀を含めて東西160m・南北170m以上の規模を誇りました。京都の将軍邸を模しているとも言われ、初期は溝と塀で囲まれていましたが、15世紀中頃には空堀と土塁による防御力を備えた城館に発展しました。
大内氏の領土拡大に伴い、館は最低5回の増築が繰り返されたことが発掘調査により確認されています。館のすぐ北側には別邸として築山館(築山御殿)が築かれ、大内氏館は住居として、築山館は迎賓館的な役割を担っていました。この複合的な館構造は、大内氏の権力の拡大と文化的洗練度の向上を物語っています。
3. 大内文化の象徴としての庭園と出土遺物
大内氏館の最も特徴的な要素は、その庭園群です。館の南東部には大きな池を持った庭園があり、北西部には枯山水の庭園が配置されていました。発掘調査では南北約40m・東西約20mの池泉庭園をはじめ4つの庭園跡が検出され、現在は最大規模の池泉庭園が水を張った姿で復元整備されています。
井戸跡からは金箔を貼った土師器の皿や中国産の壺なども多数出土しており、これらの遺物は大内氏が京都や海外の洗練された文化を積極的に取り入れていたことを示しています。特に金箔の土師器は一度使用すると廃棄される使い捨ての食器で、当時の大内氏の経済力と文化的贅沢さを物語る貴重な資料となっています。
4. 高嶺城の軍事技術と毛利氏による完成
高嶺城は山口城下の西方に位置する鴻ノ峰頂上に築かれた典型的な山城で、頂上部の主郭を中心に四方に延びる尾根へ郭を配しています。主郭周辺には石垣が使用され、礎石や瓦等も出土しており、戦国期の山城技術を示す貴重な遺構となっています。大内氏滅亡後、高嶺城の築城は毛利氏によって再開され完成を見ました。
城代として吉川氏の一門である市川経好が入り、毛利氏による山口支配の拠点として機能しました。永禄12年(1569年)の大内輝弘の乱では、市川経好の妻(市川局)が指揮を執って城を守り抜いたという記録が残っており、高嶺城の堅固さを物語っています。元和一国一城令により寛永15年(1638年)に廃城となるまで、高嶺城は中国地方における重要な軍事拠点として機能し続けました。
5. 国史跡としての価値と現代における意義
大内氏館・高嶺城は昭和34年(1959年)に「大内氏遺跡 附凌雲寺跡」として国の史跡に指定され、継続的な発掘調査と復元整備が進められています。館の西門は木造で復元され、石組みの排水溝跡とともに見学可能となっており、土塁や空堀の一部も形状が確認でき、往時の館の広さを実感できます。
高嶺城跡では主郭周辺の石垣、巨大な二重堀切とそれに付随する畝状竪堀群、虎口空間の石垣などが良好に保存されており、戦国期の山城技術を学ぶ上で貴重な教材となっています。両史跡は中世から戦国期における居館と山城の複合的な城館システムを示す全国的にも稀少な事例として、城郭史研究において極めて重要な位置を占めています。
アクセスマップ
関連リンク
散歩記録

御城印情報

大路ロビー
スタンプ情報
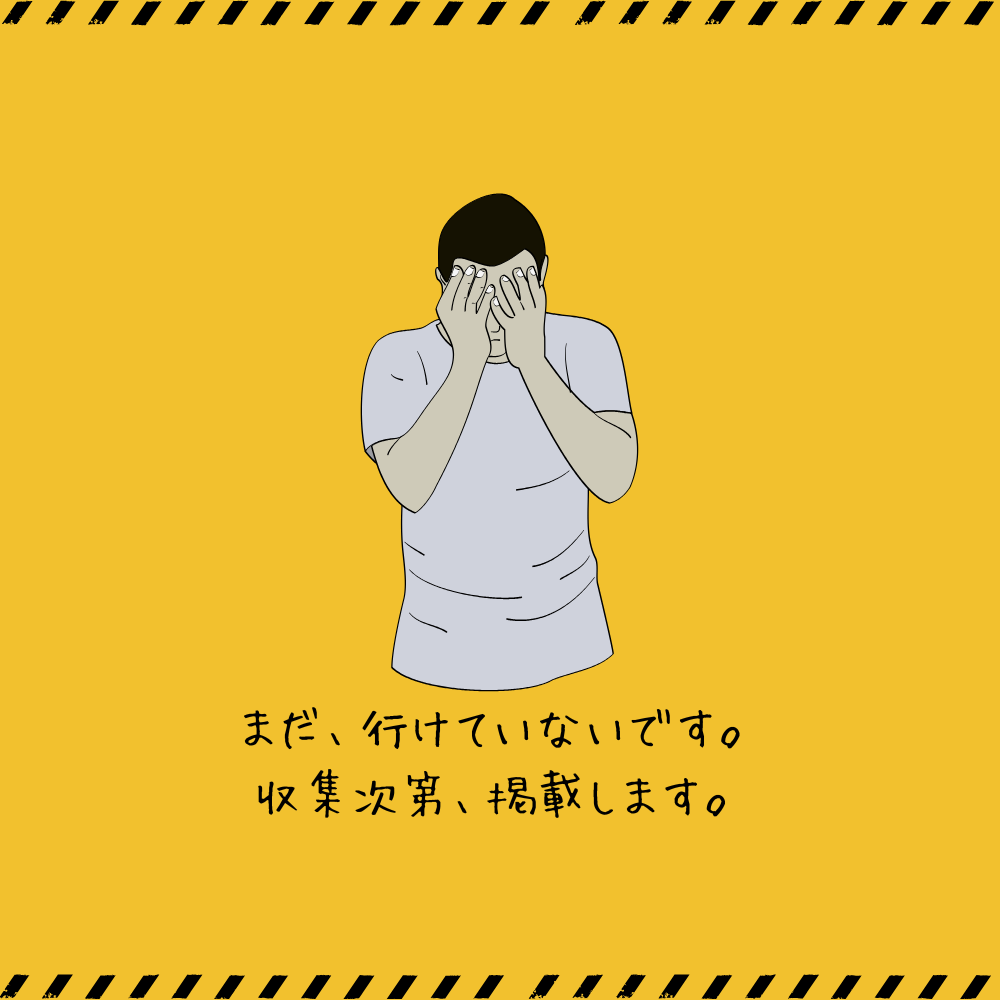
大路ロビー

