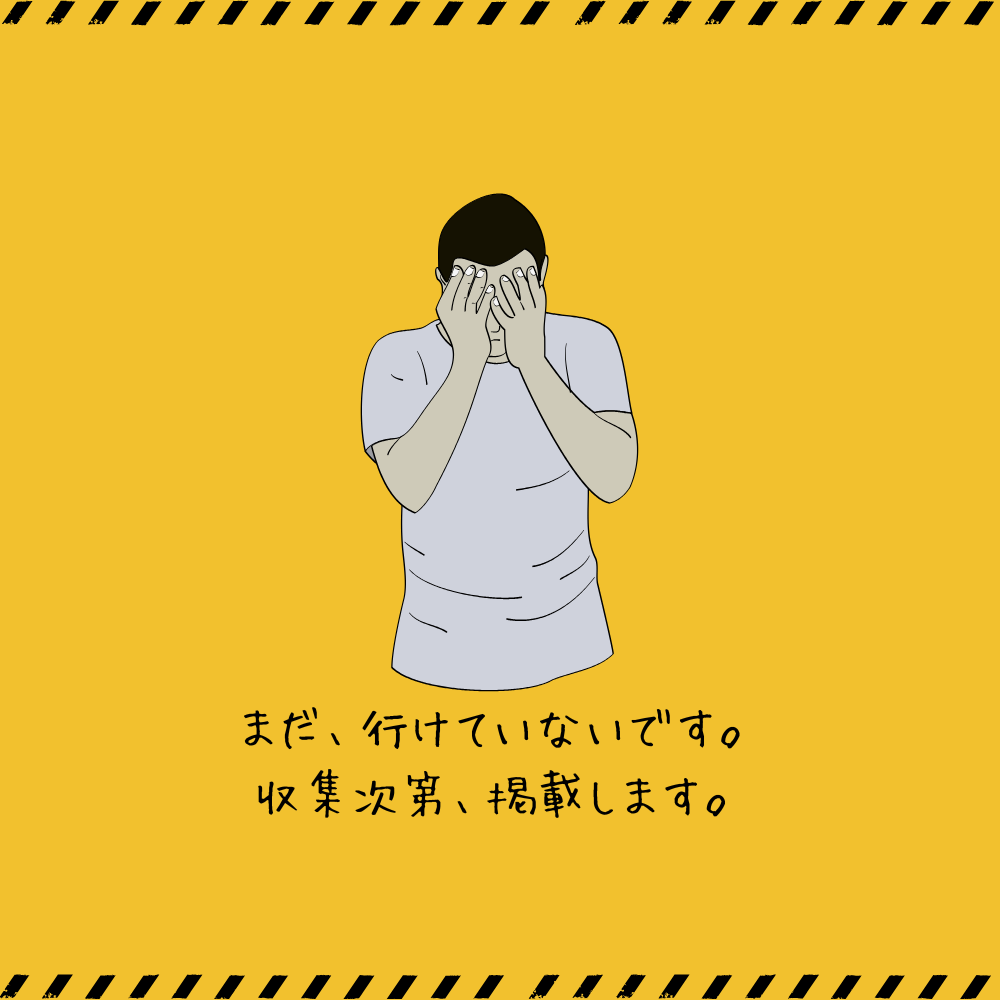75.萩城
日本100名城基本情報
| 住所 | 〒758-0057 山口県萩市堀内1-1 |
|---|---|
| 電話 | 0838-25-1826(萩城跡指月公園料金所) |
| 築城年 | 1604年(慶長9年) |
営業情報
| 開館時間 | 8:00〜18:30(4月〜10月) 8:30〜16:30(11月〜2月) 8:30〜18:00(3月) |
|---|---|
| 入場料 | 8:00〜18:30(4月〜10月) 8:30〜16:30(11月〜2月) 8:30〜18:00(3月) |
| 休館日 | 年中無休 |
1. 萩城の概要と歴史的意義
萩城は、関ヶ原の戦いで西軍の総大将となり敗北した毛利輝元が、慶長9年(1604年)に日本海に面した指月山麓に築城した平山城です。「指月城」とも呼ばれ、120万石から36万9千石に大幅減封された毛利氏の新たな居城として機能しました。山麓の平城部分(本丸・二の丸・三の丸)と指月山山頂の山城部分(詰の丸)を組み合わせた特殊な構造で、戦時と平時の両方に対応した実戦的な縄張りとなっています。明治7年(1874年)に廃城令により建物は解体されましたが、石垣や堀などの遺構は良好に保存されており、現在は指月公園として整備されています。2015年には世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産に登録され、日本100名城の75番にも選定されています。
2. 毛利輝元による築城と立地選択
毛利輝元は、関ヶ原の戦い後の減封により、本拠地を安芸国広島城から長門国萩に移すことを余儀なくされました。萩の地は日本海に突出した三角州で、三方を海に囲まれた天然の要害でした。輝元は指月山という標高143メートルの独立丘陵を利用し、山麓に政庁機能を持つ平城を、山頂に戦時の最後の砦となる山城を配置する二重構造の城郭を計画しました。この立地選択は、海からの攻撃を想定した防御と、毛利氏の威信を示す象徴的な意味を併せ持っていました。築城には指月山に連なる干潟を埋め立てる大規模な土木工事が必要で、慶長9年(1604年)に着手し、慶長13年(1608年)に完成しました。輝元は本丸御殿がまだ完成していない段階で入城し、新領国の統治にあたりました。
3. 五重五階天守の建築技術と特徴
萩城の天守は五重五階の複合式望楼型で、高さ約21メートルの堂々たる姿でした。天守台の高さは約11メートルで、三角州の軟弱地盤に対応するため、底面を広げて荷重を分散させる特殊な構造となっていました。外壁は白漆喰総塗籠で、窓には銅板を貼った突き上げ戸を採用し、防火対策が施されていました。特徴的なのは一階部分が天守台から半間ほど張り出した張出構造で、この部分の床下は石落としとして利用されました。また、天守の北側には付櫓が接続された複合式の縄張りで、付櫓内部には中二階があり、天守への動線も工夫されていました。明和5年(1768年)の修理では赤瓦に葺き替えられ、より優美な姿となりましたが、明治7年(1874年)に解体されました。建築技術的には当時最先端の工法が用いられ、左右対称の設計で構造的な強度も確保されていました。
4. 本丸・二の丸・三の丸の機能分化
萩城の山麓部分は本丸、二の丸、三の丸に明確に区分され、それぞれ異なる機能を持っていました。本丸には天守と本丸御殿が配置され、藩主の居住空間と政務空間が集約されていました。本丸御殿は書院造の豪華な建物で、大広間、黒書院、白書院などがあり、重要な政治的決定がここで行われました。二の丸には重臣の詰所や役所機能が配置され、藩政の実務が執り行われました。三の丸は家老クラスの重臣屋敷が立ち並ぶエリアで、現在でも旧厚狭毛利家萩屋敷長屋(重要文化財)が現存しています。各曲輪は石垣と堀で明確に区画され、特に内堀は幅約20メートルの立派なもので、現在も当時の姿をよく残しています。城内には23基の櫓と10基の門があり、厳重な警備体制が敷かれていました。
5. 指月山詰の丸と山城機能
萩城最大の特徴は、指月山山頂に築かれた詰の丸(山城部分)です。標高143メートルの山頂一帯に曲輪群が配置され、有事の際の最終防衛拠点として機能しました。山城部分には主郭、二の丸、三の丸などの曲輪が階段状に配置され、各曲輪は石垣で囲まれていました。山頂の主郭には平時でも番兵が常駐し、狼煙台としての機能も果たしていました。山城への登山道は厳重に管理され、途中には番所が設けられていました。この山城部分は中世的な山城の構造を色濃く残しており、近世城郭でありながら実戦的な性格を強く持っていたことを示しています。現在でも登山が可能で、山頂からは萩市街地と日本海を一望することができ、当時の見張り機能を実感することができます。指月山の森林は城内林として保護され続け、現在は国の天然記念物に指定される貴重な照葉樹林となっています。
6. 萩城下町の形成と都市計画
萩城の築城と同時に、城下町の整備も本格的に行われました。毛利輝元は城を中心とした都市計画を策定し、武家屋敷、町人町、寺院群を系統的に配置しました。城の東側には上級武家屋敷が建ち並ぶ堀内地区が、南側には中下級武家屋敷のある平安古地区が形成されました。町人町は萩城の外側に配置され、商業や手工業の中心地として発展しました。特筆すべきは道路計画で、意図的に鍵の手に折れ曲がった道路(鍵曲)を多用し、敵の侵入を阻む工夫が施されました。また、外堀の外側には寺院群を配置し、有事の際の防衛拠点としても機能するよう計画されました。この萩城下町は「江戸時代の地図がそのまま使える唯一の城下町」と称されるほど良好に保存されており、現在も当時の町割りをそのまま残す貴重な歴史的景観となっています。
7. 幕末における政治的役割と山口移鎮
江戸時代後期、萩城は長州藩の政治的中心地として重要な役割を果たしました。特に幕末の動乱期には、13代藩主毛利敬親のもとで尊王攘夷運動の拠点となりました。吉田松陰が主宰した松下村塾は萩城下にあり、高杉晋作、久坂玄瑞、木戸孝允(桂小五郎)、伊藤博文など、後の明治維新の立役者たちを輩出しました。しかし文久3年(1863年)、毛利敬親は幕府に無断で藩庁を山口に移転させました(山口移鎮)。これは京都に近い山口の方が政治的に有利と判断したためで、萩城は藩庁としての機能を失い、番兵が置かれるのみとなりました。この山口移鎮により萩城の政治的役割は終わりましたが、長州藩の精神的中心地としての地位は維持され続けました。慶応元年(1865年)には高杉晋作らが萩城を包囲する事件も起きましたが、実際の戦闘には至りませんでした。
8. 明治維新後の変遷と廃城
明治維新後、版籍奉還により萩城は明治政府の管理下に置かれました。明治4年(1871年)の廃藩置県により長州藩は消滅し、萩城は名実ともにその役割を終えました。明治6年(1873年)の廃城令により、萩城は解体対象となりました。明治7年(1874年)、天守をはじめとする建物はすべて解体され、石垣や堀の一部のみが残されました。城跡には明治23年(1890年)、歴代藩主を祀る志都岐山神社が創建され、総面積約20万平方メートルの境内が指月公園として整備されました。大正時代から昭和初期にかけて、城跡の史跡としての価値が認識され始め、昭和26年(1951年)に国の史跡に指定されました。戦後は観光地としての整備が進み、現在に至っています。近年では平成8年(1996年)から史跡萩城跡外堀保存整備事業が実施され、北の総門の復元や堀・石垣の整備が行われました。
9. 現在の指月公園と観光地化
現在の萩城跡は指月公園として整備され、萩市を代表する観光スポットとなっています。園内には天守台、梨羽家茶室、万歳橋、東園などの旧跡が点在し、当時の城郭構造をよく示しています。特に花江茶亭は、13代藩主毛利敬親が安政年間に藩主別邸・花江御殿に増築した茶室で、明治22年に園内に移築されたものです。春には約600本のソメイヨシノが咲き誇り、桜の名所として多くの観光客を迎えています。園内には山口県天然記念物に指定されたミドリヨシノという珍しい桜もあり、日本では萩でしか見ることができません。夜間は天守跡の石垣などがライトアップされ、水面に映る幻想的な姿を楽しむことができます。また、世界遺産構成資産としての価値も高く評価されており、国内外から多くの見学者が訪れています。
10. 日本100名城スタンプと見学のポイント
萩城は日本100名城の75番に選定されており、スタンプは萩城跡指月公園本丸入口料金所に設置されています。スタンプのデザインには内堀と天守台が描かれており、萩城の特徴的な石垣を表現しています。御城印は料金所で500円で販売されており、記念品として人気があります。見学のポイントとしては、まず本丸跡で天守台の石垣を観察し、築城技術の高さを実感することがおすすめです。内堀沿いを歩けば、当時の城郭規模の大きさを体感できます。時間に余裕があれば指月山の詰の丸まで登山し、山城部分の遺構も見学すると、萩城の全体像を理解できます。所要時間は平城部分のみなら1時間程度、山城まで含めると2〜3時間が目安です。萩城下町、松下村塾、萩博物館などと合わせて巡ることで、幕末維新の歴史をより深く理解することができます。桜の季節(3月下旬〜4月上旬)には特に美しい景観を楽しむことができ、夜間ライトアップも実施されています。
アクセスマップ
関連リンク
散歩記録

御城印情報

スタンプ情報