74.岩国城
日本100名城基本情報
| 住所 | 〒741-0081 山口県岩国市横山3 |
|---|---|
| 電話 | 0827-41-1477(岩国城ロープウェー) |
| 築城年 | 1608年(慶長13年) |
営業情報
| 開館時間 | 9:00〜16:45(入館は16:30まで) |
|---|---|
| 入場料 | 大人:270円 小学生:120円 ※ロープウェー別途:大人往復560円、小人往復260円 ※セット券(錦帯橋・ロープウェー・岩国城)割引あり |
| 休館日 | ロープウェー点検日、水曜(祝祭日の場合は翌日) |
1. 岩国城の概要と歴史的意義
岩国城は、関ヶ原の戦い後に岩国領主となった吉川広家によって慶長13年(1608年)に築城された山城です。錦川を天然の外堀とし、標高約200メートルの城山(横山)山頂に位置する堅固な要塞でした。三層四階の桃山風南蛮造りという独特の天守を持ち、当時としては珍しく山上に空堀を設けた城郭でもありました。しかし築城完了からわずか7年後の元和元年(1615年)、徳川幕府の一国一城令により天守などの主要建造物が破却され、短命に終わった悲劇の城として知られています。現在の天守は昭和37年(1962年)に外観復元されたもので、錦帯橋とともに岩国観光のシンボルとして親しまれています。日本100名城の74番に選定されています。
2. 吉川広家による築城と戦略的立地
吉川広家は毛利元就の三男である吉川元春の三男で、関ヶ原の戦いでは毛利氏の西軍参加を阻止し、東軍に内通したことで戦後も領地を安堵されました。岩国の地は水陸交通の要衝であり、瀬戸内海に注ぐ錦川が天然の防御線となる理想的な立地でした。広家は横山の山頂に戦時の城(要害)を、山麓には平時の居館(御土居)を配置する輪郭式の縄張りを採用しました。本丸には四重六階の天守を中心に、北ノ丸、二ノ丸、水の手などの曲輪を配置し、石垣は古式穴太積みで築かれました。城下と城を隔てる錦川には後に錦帯橋が架けられ、特徴的な景観を作り出しています。この立地選択は軍事的な防御と政治的な象徴性を兼ね備えた、広家の深謀遠慮を表しています。
3. 桃山風南蛮造りの天守建築
岩国城天守の最大の特徴は「桃山風南蛮造り」という独特の建築様式でした。この南蛮造り(唐造り)とは、最上階をその下階より大きく造り、その間の屋根を省略した構造のことで、三層目が二階建て(三階・四階)になり、四階が三階より外にはみ出している形状でした。この構造は主に最上階で使用されることが多いですが、岩国城では中層階で採用された珍しい例でした。同様の構造を持つ城には小倉城や高松城などがありますが、山城での採用は非常に稀でした。外観は白漆喰の壁に黒瓦という美しい姿で、安土桃山時代の華麗な建築文化を体現していました。内部は四重六階で構成され、各階には武具庫や見張り台、城主の居住空間などが配置されていました。
4. 一国一城令による破却と廃城
元和元年(1615年)、徳川幕府が発布した一国一城令により、岩国城は破却の運命を辿りました。厳密には周防国には岩国城のみが存在していたため破却の必要はありませんでしたが、毛利氏が幕府への遠慮から先走って自主的に破却してしまったとされています。天守をはじめとする主要建造物は取り壊され、石垣も破却が命じられましたが、天守台の下部約1/4が地中に埋まって残存しました。この天守台は平成7年(1995年)の発掘調査により古式穴太積み石垣として復元されています。破却後は山麓の居館(御土居)が陣屋として機能し、吉川氏は岩国領(事実上の岩国藩)の藩主として明治維新まで続きました。短期間で廃城となったため、戦火を免れた石垣や曲輪の遺構が比較的良好な状態で保存されています。
5. 昭和の天守復元と観光化
戦後の観光振興の一環として、昭和30年代に岩国城天守の復元計画が立案されました。昭和37年(1962年)、市民の熱意と募金活動により外観復元天守が完成しました。復元にあたっては、錦帯橋からの景観を重視し、旧天守台から約50メートル南東に位置をずらして建設されました。これにより錦帯橋方面からの眺望が格段に向上し、観光地としての魅力が高まりました。天守は鉄筋コンクリート造で建設され、内部は博物館として整備されました。1階から3階には岩国の歴史資料、武具甲冑、刀剣類が展示され、最上階は展望台として利用されています。同時期に岩国城ロープウェーも開設され、山麓から山頂までのアクセスが大幅に改善されました。現在も岩国観光の中核施設として多くの観光客を迎えています。
6. 錦帯橋との一体的景観
岩国城は日本三名橋の一つである錦帯橋と一体となった美しい景観を形成しています。錦帯橋は延宝元年(1673年)、第3代岩国領主吉川広嘉によって架けられた全長約193メートルの木造5連アーチ橋で、釘を一本も使わない伝統技法で建造されています。橋から仰ぎ見る岩国城の姿は絵画的な美しさを誇り、逆に城からの眺望でも錦帯橋の優美な曲線美を堪能できます。春には橋の両岸に桜が咲き誇り、秋には紅葉が彩りを添え、四季を通じて素晴らしい景観を提供しています。夜間には錦帯橋と岩国城の両方がライトアップされ、幻想的な夜景を演出します。この橋と城が織りなす風景は、日本の城郭と土木技術の粋を集めた文化的景観として高く評価されており、多くの写真愛好家や観光客を魅了し続けています。
7. 現在の天守内展示と見学内容
現在の岩国城天守内は4階建ての博物館として運営されており、岩国の歴史と文化を紹介する貴重な資料が展示されています。1階では岩国城の築城から破却までの歴史を模型や資料で解説し、錦帯橋の精密模型も展示されています。2階では吉川氏の歴史と岩国藩政について詳しく紹介し、武具甲冑類も豊富に展示されています。3階は企画展示室として活用され、季節ごとにテーマを変えた特別展が開催されています。最上階の4階は展望室となっており、360度のパノラマビューを楽しむことができます。展望室からは錦帯橋、吉香公園、岩国市街地、錦川、遠くは瀬戸内海の島々、宮島、岩国錦帯橋空港まで一望でき、晴天時には四国の山々も望むことができます。各階には音声ガイドも設置されており、詳しい解説を聞きながら見学することが可能です。
8. 山城遺構と発掘調査成果
岩国城跡には破却を免れた貴重な山城遺構が数多く残存しています。北ノ丸では石垣下に犬走りがあり、石垣を間近で観察できるルートが整備されています。水の手曲輪では内枡形の虎口跡が良好な状態で保存されており、一部に石階段も残されています。これらの遺構は未整備エリアに多く、山城らしい荒々しさと高低差を感じることができます。平成7年(1995年)の発掘調査では、破却された天守台の基礎部分が発見され、古式穴太積みの石垣として復元展示されています。この調査により、実際の天守台は現在の復元天守より約50メートル北西に位置していたことが判明しました。復元天守1階では発掘調査で明らかになった縄張図が展示されており、往時の城郭構造を詳しく知ることができます。また、石切場跡も発見されており、築城時の石材調達の様子も解明されています。
9. アクセスと周辺観光施設
岩国城へのアクセスは、JR岩国駅または山陽新幹線新岩国駅からバスで錦帯橋まで向かい、そこから岩国城ロープウェーを利用するのが一般的です。ロープウェーは山麓駅から山頂駅まで約3分で結び、定員25名のゴンドラ内では音声ガイドで岩国の歴史を紹介しています。山頂駅から天守まては徒歩約5分です。車利用の場合は山陽自動車道岩国ICから約10分で、錦帯橋周辺に複数の駐車場が整備されています。周辺には吉香公園、岩国美術館、吉川史料館、岩国徴古館などの文化施設が点在し、香川家長屋門や目加田家住宅などの武家屋敷建築も見学できます。紅葉谷公園は秋の紅葉が特に美しく、季節ごとに異なる表情を楽しむことができます。錦帯橋・ロープウェー・岩国城のセット券も販売されており、効率的な観光が可能です。
10. 日本100名城スタンプと御城印情報
岩国城は日本100名城の74番に選定されており、スタンプは天守1階受付と岩国城ロープウェー山麓駅受付の2箇所に設置されています。天守の休館日(ロープウェー点検日など)には山麓駅でスタンプを押印することができます。御城印は岩国城受付で販売されており、基本版350円のほか、季節限定版(夏バージョン6月〜8月)500円、特別版1,000円など複数のバージョンが用意されています。また、日本100名城の城カードも350円で販売されています。見学のポイントとしては、まず錦帯橋を渡って吉香公園を散策し、ロープウェーで山頂へ向かうコースがおすすめです。天守からの眺望を楽しんだ後は、北ノ丸や水の手曲輪などの山城遺構も見学し、石切場跡まで足を延ばすとより深く岩国城を理解できます。所要時間は錦帯橋と合わせて2〜3時間程度で、春の桜、秋の紅葉の季節は特に美しい景観を楽しむことができます。
アクセスマップ
関連リンク
散歩記録

御城印情報

スタンプ情報
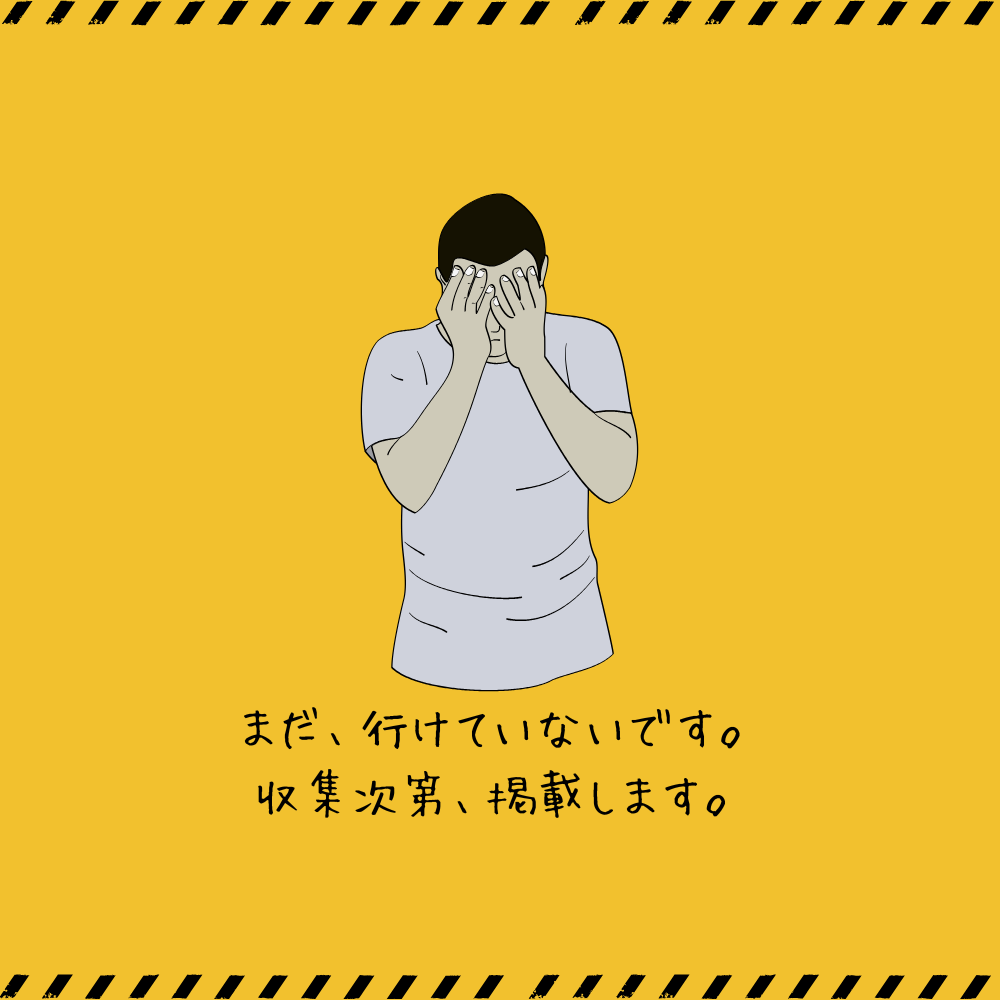
②岩国城ロープウェー山麓駅受付(休館日)

