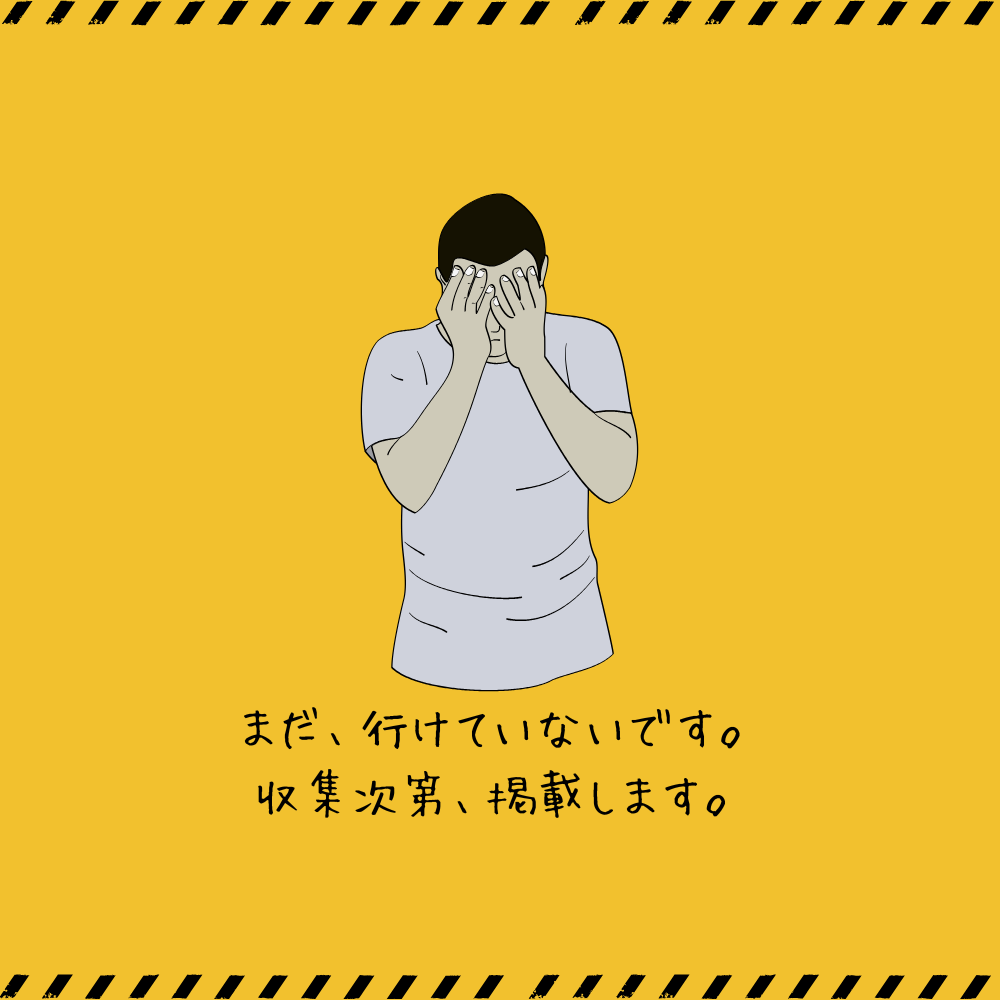109.米沢城
続100名城基本情報
| 住所 | 〒992-0052 山形県米沢市丸の内1丁目4-13 |
|---|---|
| 電話 | 0238-21-6226(米沢観光コンベンション協会) |
| 築城年 | 1238年(暦仁元年) |
営業情報
| 開館時間 | ー |
|---|---|
| 入場料 | ー |
| 休館日 | ー |
1. 米沢城の概要
米沢城が最初に築かれたのは、鎌倉時代中期の暦仁元年(1238年)と伝えられる。鎌倉幕府の重臣・大江広元の次男・長井時広が出羽国置賜郡長井郷の地頭として赴任した際に築城されたと推定されているが、これを実証する史料や遺構は確認されていない。時広は赴任地の地名から長井姓を名乗った。以後、長井氏の支配が150年近く続いた。
2. 城の特徴と構造
米沢城は平城で、本丸・二の丸・三の丸からなる輪郭式縄張りの城である。石垣は少なく、土塁を多用し、全体的に質素な城となった。これは、米沢城が敵に侵入されたり落城した経験がないことや、120万石時代の家臣をほとんど削減しなかったため、財政が逼迫していたという説もあるが、上杉景勝が会津で建設を目指していた神指城も米沢城と同様の縄張で、土塁を多用した造りである。これは春日山城の麓にあった関東管領邸である御館にも共通した特徴であり、上杉氏の本拠地としての伝統的な城館建築の造りである。
3. 歴史的意義
戦国時代後期には伊達氏の本拠地が置かれ、伊達政宗の出生した城でもある。1598年(慶長3年)に五大老・上杉景勝が120万石で入封した際は直江兼続が城主を務めたこともある。その後は「関ケ原の戦い」後に石高を減じられながらも江戸時代を通じて上杉氏の居城として利用され、江戸時代屈指の名君として知られる上杉鷹山などが藩主となっている。
4. 現在の状況
現在、本丸跡は上杉神社の境内となっている。上杉鷹山を祀る松岬神社も隣接している。暦仁元年(1238)長井時広の築城と伝えられる、米沢城(松岬城あるいは舞鶴城とも称された。)の城跡で、現在は本丸と二の丸の一部が公園となり、濠内には上杉神社や稽照殿(宝物殿)、上杉謙信像、上杉鷹山像などがある。明治6年、城が取り壊され、明治7年、公園として市民に開放された。四周を濠に囲まれ、200本の桜に包まれた桜の名所ともなっている。
5. 文化的価値
上杉景勝の時代には御三階櫓が北東隅と北西隅に二基存在したが、そのうち丑寅三重櫓を天守の代用とした。1673年(延宝元年)に御三階櫓は上杉綱憲により修理再築されたが、明治に入って取り壊された。2001年に開館した米沢市上杉博物館には上杉氏関連の資料が展示されている。国宝の上杉家文書や上杉洛中洛外図屏風(原本)も上杉博物館で展示されている。
アクセスマップ
関連リンク
散歩記録

御城印情報

スタンプ情報