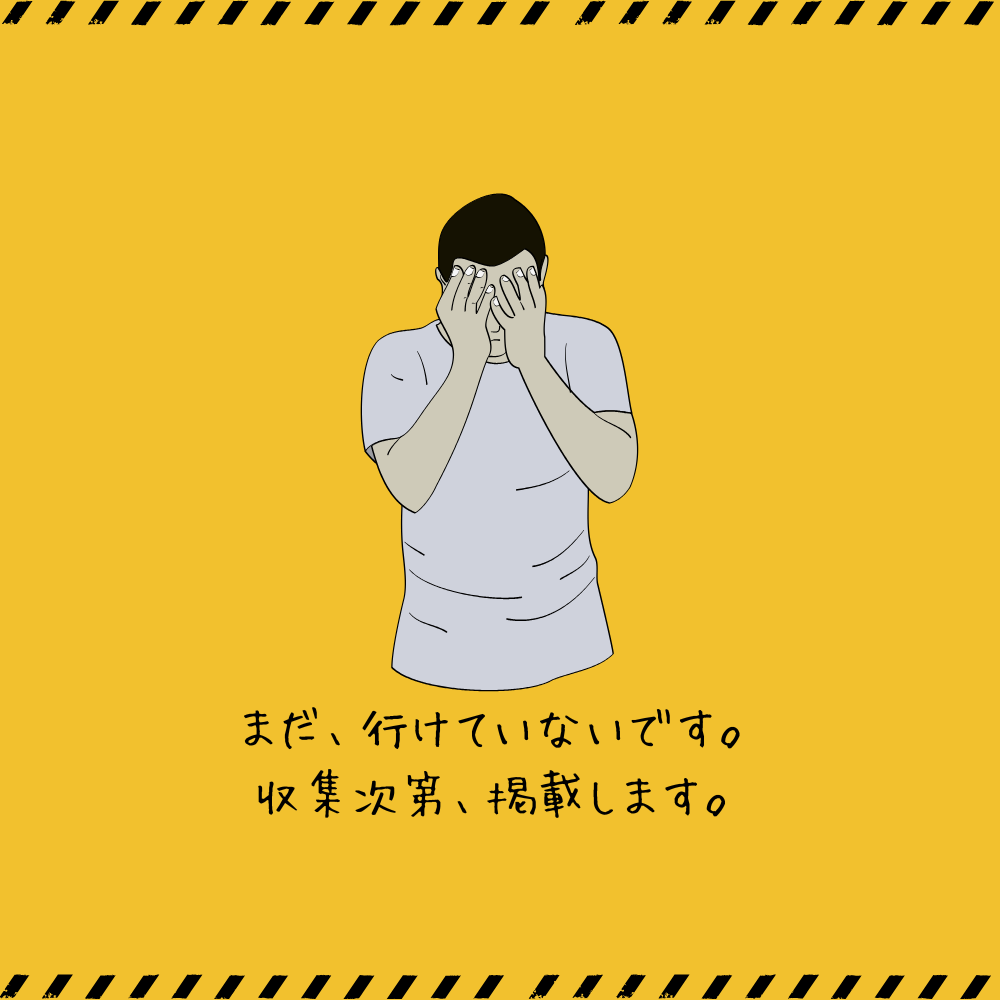108.鶴ケ岡城
続100名城基本情報
| 住所 | 〒997-0035 山形県鶴岡市馬場町4-1 |
|---|---|
| 電話 | 0235-22-8100(荘内神社) |
| 築城年 | 鎌倉時代初期 |
営業情報
| 開館時間 | ー |
|---|---|
| 入場料 | ー |
| 休館日 | ー |
1. 鶴ヶ岡城の概要
鶴ヶ岡城は、室町時代初期、武藤長盛による築城が始まりといわれており、古くは大宝寺城と呼ばれた。1601年には、山形の最上氏による庄内支配の拠点となり、その2年後に鶴ヶ岡城に改称された。最上氏改易後の1622年、信州松代より酒井忠勝が入部して以降、藩主酒井氏は、1871年の廃藩置県まで12代・約250年に亘ってこの地を治めるとともに、その治世の間、鶴ヶ岡城が酒井氏の居城となった。
2. 城の特徴と構造
鶴ヶ岡城は、本丸を中心に同心円状に二の丸と三の丸が取り囲み、各々に土塁と堀を巡らした輪郭式平城である。他の東北地方の城と同様に土塁を多用し、石垣は主要な部分にしか用いられていなかった。また、天守は構えられなかったが、本丸東北隅に2層2階の隅櫓と二の丸南西隅にも2層2階の隅櫓が建てられていた。
3. 歴史的意義
戦国時代、庄内地方は上杉氏と最上氏によって争われ、豊臣政権下で上杉景勝の領地となった。1600年関ヶ原の戦いで上杉景勝は西軍に付いたため会津120万石から米沢30万石に減封され、庄内地方は山形城を本拠地としていた最上義光の領地となった。最上義光は隠居の城として大宝寺城を修復して鶴ヶ岡城と改称した。その後「最上騒動」により改易となったため、譜代大名の酒井忠勝が出羽庄内藩の初代藩主として入り、幕末まで酒井氏が城主をつとめた。
4. 現在の状況
現在、本丸・二の丸跡周辺は鶴岡公園となっており、桜の名所として日本さくら名所100選に選ばれている。鶴岡公園は730本の桜が植えられている。また、三の丸跡に残る酒井家御用屋敷跡庭園は酒井氏庭園として1976年に国の名勝に指定されたほか、公園の南東に残る藩校「致道館」は東北地方に唯一現存する藩校として国の史跡に指定されている。
5. 文化的価値
この酒井氏は、あの徳川四天王の酒井忠次を祖とする。庄内藩の藩校だった致道館が現存していることから、致道博物館では「大名酒井家の名宝 国宝展示」が開催され、数々の貴重な国宝、重要文化財を見ることができるなど、文化的価値の高い史跡である。
アクセスマップ
関連リンク
散歩記録

御城印情報

スタンプ情報