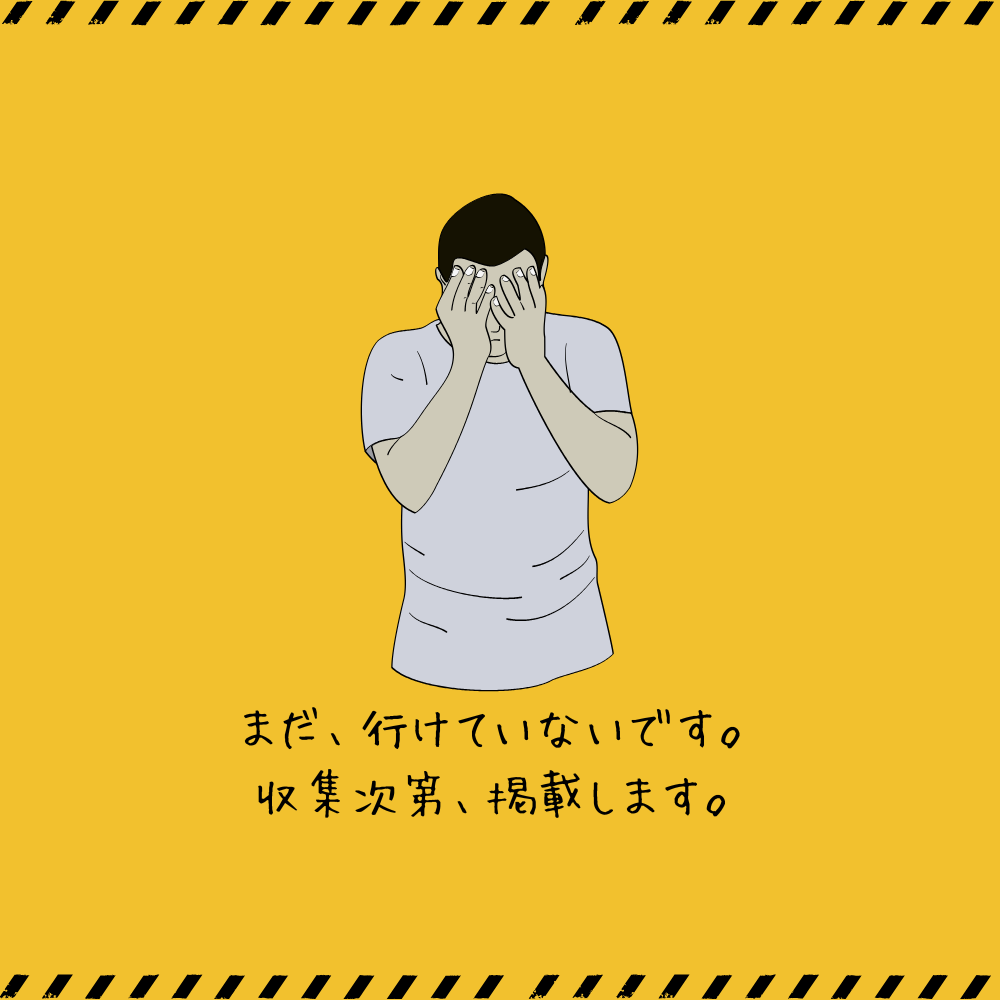113.土浦城
続100名城基本情報
| 住所 | 茨城県土浦市中央1-13 |
|---|---|
| 電話 | 029-824-2928 |
| 築城年 | 室町時代後期(永享年間1429-1441年) |
営業情報
| 開館時間 | 9:00~16:30 |
|---|---|
| 入場料 | 200円(東櫓) |
| 休館日 | 月曜日・祝日の翌日(翌日が土日の場合は開館)・年末年始(12月28日~1月4日) |
1. 土浦城の歴史
室町時代の永享年間(1429年から1441年)に常陸守護であった八田知家の後裔で豪族の小田氏に属する若泉(今泉)三郎が築城したのが始まりとされる。江戸時代、貞享2年(1684)に大改修され、現在の縄張りが完成しました。関東に入った徳川家康は、土浦を次男で結城氏に養子入りした結城秀康に与え、土浦城を領内の支城とする。その後藤井松平家、西尾家、朽木家と城主が代わり、寛文9年(1669年)に土屋数直が入封した。土屋政直が再び6万5千石で入封した。その後、3度の加増を受けて9万5千石となり、常陸国では水戸藩に次いで大きな領地を支配し、以後土屋家が11代(約200年間)にわたって世襲して明治維新に至った。
2. 土浦城の構造と特徴
平城で、本丸・二の丸・三の丸からなる輪郭式縄張りの城である。何重にもめぐらされた水掘の中心に位置する本丸は、水に浮かぶ亀の姿に例えられ、このことから亀城の別名で親しまれている。天守は作られなかった。太鼓櫓門が現存し、東西二か所の櫓が復元されている。本丸に現存する櫓門としては、関東地方で唯一現存するもので、明暦2年(1656年)に改築されたものである。
3. 現在の土浦城
現在は亀城公園として整備され、本丸と二の丸の一部が保存されている。東櫓は、江戸時代初期に西尾氏が城主だったときに建てられたと伝えられています。明治時代の火災で焼失しましたが、平成10年(1998)に復元されました。西櫓も昭和24年(1949年)のキティ台風で倒壊したが、平成3年(1991年)に復元された。東櫓は土浦市立博物館の付属展示館として活用され、土浦城のスタンプは、土浦城東櫓(亀城公園内)に設置しています。
4. 土浦城の文化的意義
土浦城は江戸時代を通じて一貫して土屋氏の居城として機能し、近世城郭の典型的な構造を保持してきた。特に現存する櫓門は関東地方における数少ない江戸時代建築の遺構として貴重である。また、天守を持たない平城としての特徴や、水堀を多用した防御システムは、関東平野における城郭建築の一典型を示している。
5. 土浦城の見どころ
土浦城では現存する櫓門と復元された東西櫓、そして往時の水堀の一部を見ることができる。特に櫓門は1656年に朽木氏が城主の時に改築された記録が残っており、土浦城に残る江戸時代の建築物として価値が高い。土浦市立博物館では土浦城の復元模型や関連資料を展示しており、城の全体像を理解することができる。
アクセスマップ
関連リンク
散歩記録

御城印情報

スタンプ情報