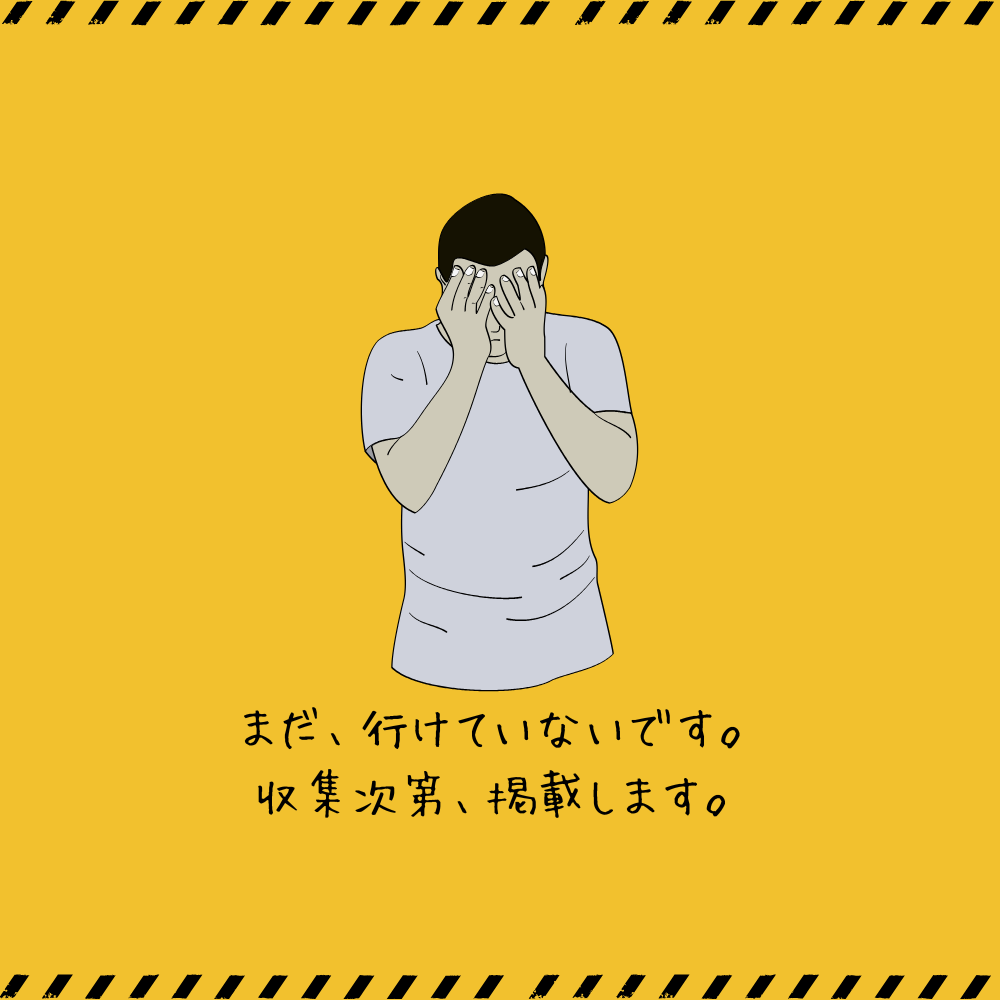120.菅谷館
続100名城基本情報
| 住所 | 埼玉県比企郡嵐山町大字菅谷757 |
|---|---|
| 電話 | 0493-62-5896(埼玉県立嵐山史跡の博物館) |
| 築城年 | 鎌倉時代初期(12世紀末頃) |
営業情報
| 開館時間 | 9:00~16:30(館跡は随時見学可能) |
|---|---|
| 入場料 | 館跡無料・博物館100円 |
| 休館日 | 月曜日(祝日の場合は翌日)・年末年始 |
1. 菅谷館の歴史と畠山重忠
菅谷館は埼玉県比企郡嵐山町にある中世の館跡で、鎌倉幕府の有力御家人として知られる畠山重忠の居館跡と伝えられています。重忠は源平の戦いや奥州合戦で功績を残し「鎌倉武士の鑑」と讃えられた人物で、元久2年(1205年)に北条義時による謀略により二俣川で討ち取られました。『吾妻鏡』文治3年(1187年)の記録に「武蔵国菅谷館」として登場し、重忠が身の潔白を訴えるため引きこもった場所として記されています。
2. 戦国時代の城郭整備
畠山重忠の死後、菅谷館は長く詳細不明でしたが、15世紀後半の戦国時代になって山内上杉氏により城郭として再整備されました。長享2年(1488年)に菅谷原で山内上杉家と扇谷上杉家が激戦を繰り広げた須賀谷原合戦の前後に、太田資康が河越城への押さえとして菅谷の旧城を再興したとされています。その後は天文15年(1546年)の河越夜戦以降に進出した後北条氏によって戦国末期まで使用されました。
3. 城郭構造と防御システム
現在見られる菅谷館跡は戦国時代に整備された城郭遺構で、本郭・二の郭・三の郭を中心とした構造となっています。本郭は最も防御力が高く、二の郭と比べて高い土塁が築かれており、虎口には出枡形土塁が設けられ横矢掛かりの構造となっています。搦手門跡は喰い違い虎口となっており、空堀と二重土塁の遺構が良好に残されています。三の郭は武士や騎馬の集合地として利用されていたと考えられています。
4. 史跡指定と文化財価値
菅谷館跡は昭和48年(1973年)に国の史跡に指定され、平成20年(2008年)には松山城跡、杉山城跡、小倉城跡とともに「比企城館跡群」として一括指定されました。鎌倉時代における菅谷館の中心部分と考えられる本郭部分は中世館跡の遺構例として稀少な遺跡であり、土塁と空堀が良好に保存されています。平成29年(2017年)には続日本100名城(120番)に選定され、埼玉県内では5城目の認定となりました。
5. 見学と博物館施設
菅谷館跡は年中随時見学可能で、東武東上線武蔵嵐山駅から徒歩約15分でアクセスできます。三の郭跡には埼玉県立嵐山史跡の博物館が設けられており、埼玉県の中世史について学習できます。続日本100名城のスタンプは博物館の展示室受付前に設置されており、観覧料を支払わなくても押印可能です。館跡内には畠山重忠公像が建立されており、竹筋コンクリート製の珍しい構造となっています。
アクセスマップ
関連リンク
散歩記録

御城印情報

スタンプ情報