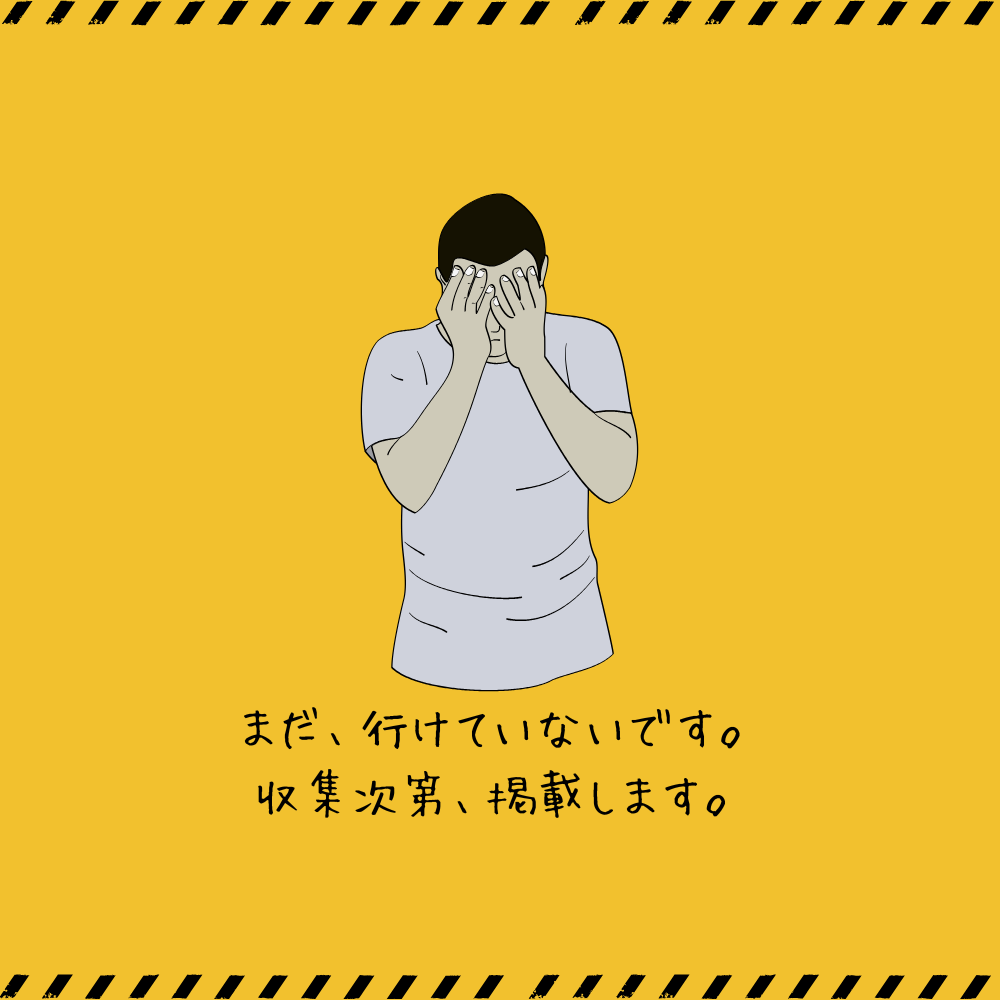8.仙台城
日本100名城基本情報
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区天守台青葉城址 |
|---|---|
| 電話 | 022-214-8544(仙台市教育局文化財課) |
| 築城年 | 1601年 |
営業情報
| 開館時間 | 常時開放(城跡) |
|---|---|
| 入場料 | 無料(城跡) |
| 休館日 | なし(城跡) |
歴史と概要
慶長5年(1601年)に初代仙台藩主・伊達政宗によって青葉山に築城された仙台城は、雅称を「青葉城」、別名を「五城楼」とも呼ばれます。廃藩置県・廃城令までの約270年間、伊達氏代々の居城として機能し、仙台藩62万石の政庁でした。二代藩主伊達忠宗の代に完成した仙台城は約2万坪の規模を誇り、大藩にふさわしい大規模な城郭でした。
築城の背景
関ヶ原の戦いの後、伊達政宗は徳川家康の許しを得て千代に居城を移すことを決定しました。1600年(慶長5年)12月、政宗は青葉山に登って縄張りを開始し、地名を仙台と改めました。仙台が選ばれた理由は、陸路では東海道の延長上にある「海道」と東山道に由来する「山道」が合流し、水路では名取川・広瀬川を経由して太平洋に通じる交通の要所であったことが挙げられます。
城郭の構造と特徴
標高約130mの青葉山に築かれた仙台城は、東と南を断崖が固める天然の要害を活用した平山城です。政宗が築いた当初は本丸と西の丸からなる山城で、天守台は設けられたものの天守は建設されませんでした。これは徳川家康の警戒を避けるための配慮とされています。後に二代忠宗の代には山麓に二の丸、三の丸(東の丸)が造営され、平山城としての体裁が整いました。
現存する遺構と復元建築
現在残る主要な遺構は石垣で、特に本丸北壁の石垣は壮観です。建築物は戦災で失われましたが、1967年(昭和42年)に民間の寄付により脇櫓(隅櫓)が復元されました。本丸跡には1964年に設置された伊達政宗公騎馬像が立ち、仙台市のシンボルとなっています。青葉城資料展示館では、CGによる城郭復元映像を見ることができます。
江戸時代から明治維新まで
江戸時代を通じて仙台城は火災や地震により何度か被害を受けましたが、その都度修復されました。戊辰戦争では奥羽越列藩同盟の盟主となりましたが、仙台が戦場となることはなく、創建以来一度も攻撃を受けることなく明治維新を迎えました。しかし明治以降は陸軍用地となり、多くの建築物が解体されました。
現代の整備と活用
平成15年(2003年)に国史跡に指定され、城跡一帯は青葉山公園として整備されています。伊達政宗騎馬像と本丸北壁石垣は日没から午後11時まで通年でライトアップされ、100万都市仙台の夜景スポットとしても人気です。土井晩翠銅像前では「荒城の月」の自動演奏が9時から18時まで30分ごとに流れ、文学的な趣も添えています。
震災復興と課題
2011年の東日本大震災や2021年・2022年の福島県沖地震により石垣の一部が崩落しましたが、現在復旧工事が進められています。仙台市では政宗公没後400年にあたる2036年に向けて大手門の復元を計画しており、往時の姿を取り戻す取り組みが続けられています。
アクセス・見学情報
仙台駅西口バスプール16番乗り場から観光シティループバス「るーぷる仙台」で約20分、「仙台城跡」下車。地下鉄東西線「国際センター駅」から徒歩15分。有料駐車場あり(夜間18時~翌8時は無料開放)。日本100名城スタンプは仙台城見聞館(9時~17時、年中無休)で押印可能です。
アクセスマップ
関連リンク
散歩記録

御城印情報

スタンプ情報