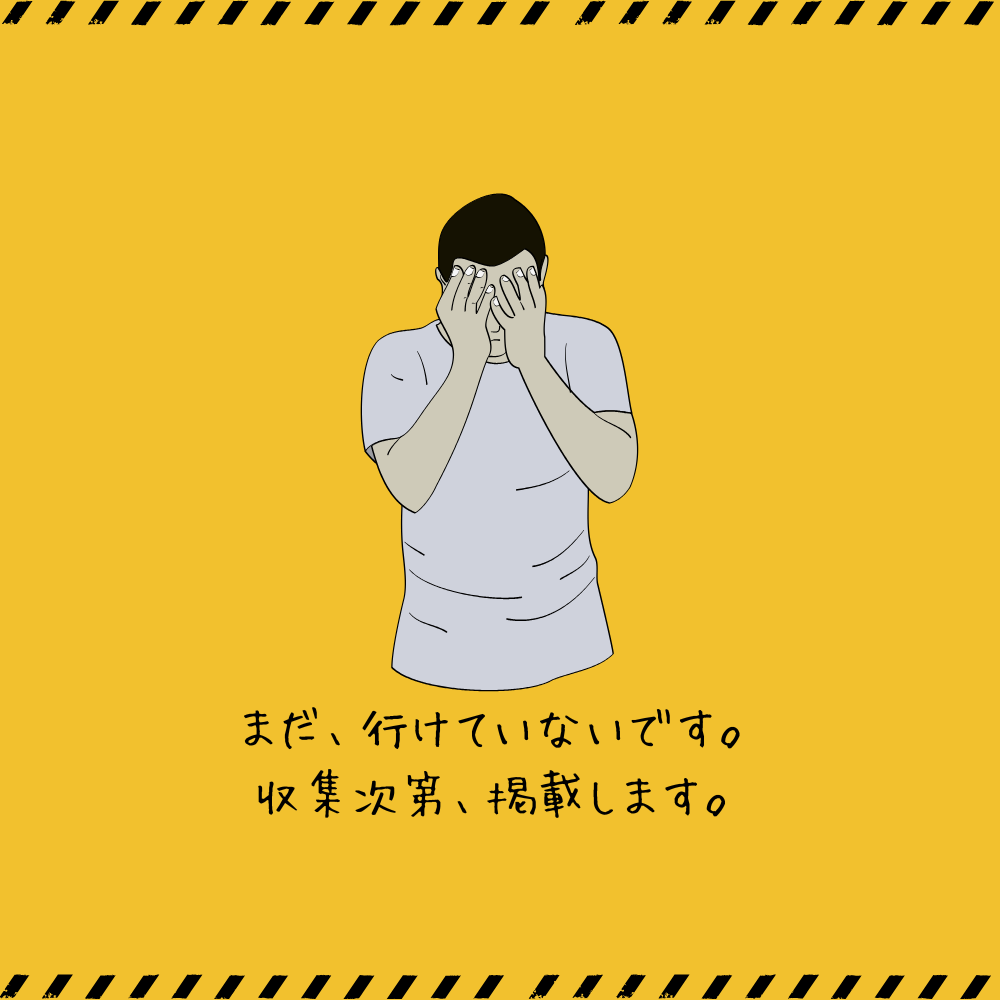118.忍城
続100名城基本情報
| 住所 | 埼玉県行田市本丸17-23 |
|---|---|
| 電話 | 048-554-5911(行田市郷土博物館) |
| 築城年 | 文明年間(1469年~1486年) |
営業情報
| 開館時間 | 9:00~16:30(博物館:16:00までに入館) |
|---|---|
| 入場料 | 200円(高校生以上)、100円(小・中学生) |
| 休館日 | 月曜日・祝日の翌日・第4金曜日・年末年始 |
1. 忍城の歴史
忍城は室町時代中期の文明年間(1469年~1486年)に、この地を統一した成田氏によって築城されたと伝えられている。関東七名城の一つとされ、初代城主の成田顕泰以降、天正18年(1590年)までの約100年間、成田氏四代にわたる居城であった。1590年(天正18年)、豊臣秀吉の関東平定の際、城主・成田氏長は小田原城にて籠城し、叔父・成田泰季を城代として約500人の侍や足軽のほか、雑兵、農民、町人など3,000人が忍城に立てこもった(忍城の戦い)。石田三成による総延長28kmにおよぶ石田堤を建設した水攻めにも関わらず忍城は落城せず、結局は小田原城が先に落城したことによる開城となった。
2. 忍城の構造と特徴
北を利根川、南を荒川に挟まれた扇状地に点在する広大な沼地と自然堤防を生かした構造となっている。湿地帯を利用した平城で、元々沼地だったところに島が点在する地形だったが、沼を埋め立てず、独立した島を曲輪として、橋を渡す形で城を築いた。当初は櫓を立てずに本丸は空き地とし、二の丸に屋敷を作ってそこを住まいとしていた。そのため、攻めにくく守りやすい城であったとされる。この地形的特徴から、数度の城攻めを受けても、一度も落城しなかった要害堅固な城として知られ、豊臣方の水攻めに耐え抜いた逸話から浮き城または亀城と称された。
3. 現在の忍城
現在、城跡には行田市郷土博物館が建てられており、御三階櫓が外観復興されている。1988年(昭和63年)2月17日に本丸跡に行田市郷土博物館が開館し、御三階櫓は博物館の一部として「忍城鳥瞰図」や文献などを元に、鉄筋コンクリート構造によって外観復興されている。ただし位置や規模は史実とは異なり、内部は展望室や行田の歴史を写真や資料で紹介する展示室として利用されている。また、周囲には土塁の一部が残存している。外堀跡を整備した「水城公園」があり、桜の名所としても知られている。
4. 忍城の文化的意義
江戸時代に入ると忍藩の藩庁となり、徳川氏の譜代大名や親藩の居城となった。「知恵伊豆」の異名で知られる松平信綱や老中・阿部忠秋が城主を務め、忍城は武蔵河越や下総佐倉と並ぶ「老中の城」として幕府を支える重要拠点と位置づけられた。城下町は中山道の裏街道宿場町としての機能や、付近を流れる利根川の水運を利用した物流路としての機能を兼ね備えて繁栄し、江戸時代後期からは足袋の産地として名をはせるようになった。近代には年間約8,500万足、全国シェアの約8割を占める足袋の生産地となり、「和装文化の足元を支え続ける足袋蔵のまち行田」として日本遺産に認定されている。
5. 忍城の見どころ
石田堤とは、石田三成が忍城を水攻めするために築いた堤(堤防)で、総延長28kmの一部が現存している。三成は本陣を忍城を一望する丸墓山古墳(埼玉古墳群)に置き、近くを流れる利根川を利用した水攻めを行った。現在も石田堤史跡公園を中心に北端から南端まで500m以上も残っており見ごたえがある。毎年11月の第二日曜日に「行田商工祭・忍城時代祭り」が行われ、武者行列や火縄銃演武などが行われる。また、行田ゼリーフライや行田フライなどのB級グルメでも有名で、小説・映画『のぼうの城』の舞台としても知られている。
アクセスマップ
関連リンク
散歩記録

御城印情報

スタンプ情報