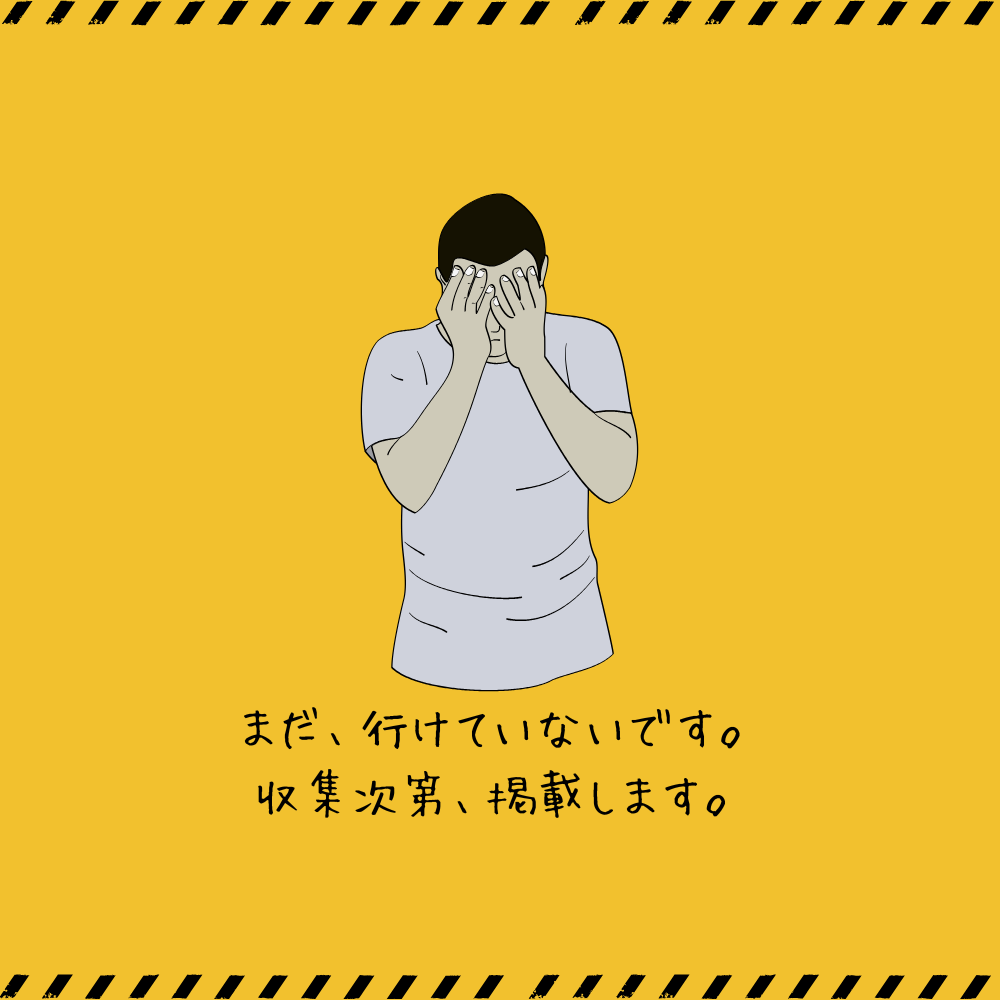11.二本松城
日本100名城基本情報
| 住所 | 福島県二本松市郭内 |
|---|---|
| 電話 | 0243-55-5095(二本松市産業部観光課) |
| 築城年 | 1414年 |
営業情報
| 開館時間 | 常時開放(城跡) |
|---|---|
| 入場料 | 無料(城跡) |
| 休館日 | なし(城跡) |
歴史と概要
応永21年(1414年)に畠山満泰が塩沢の田地ケ岡より白旗ケ峯に居を移し、二本松城と号したのが始まりです。城は二本松市街地の北に位置し、麓の居館と標高345mの「白旗が峰」に築かれた城郭からなる梯郭式の平山城で、別名「霞ヶ城」「白旗城」とも呼ばれます。霞ヶ城の名は、春に公園全体を覆う桜が霞に包まれたような景色になることに由来しています。
築城の背景と変遷
畠山氏が約170年間居城としましたが、天正14年(1586年)に伊達政宗が攻め落とし、片倉景綱、次に伊達成実を城代としました。豊臣秀吉の奥州仕置後は蒲生氏郷、上杉景勝の支城となり、寛永20年(1643年)に丹羽光重が入城してから明治維新まで二本松藩主丹羽氏の居城となりました。光重は城内の石垣修築を行うとともに城下町を整備し、三重の天守閣を築きました。
現存する遺構と復元建築
現在残る主要な遺構は石垣で、特に本丸直下の大石垣(野面積み)は高さ13m、幅15~21mの規模を誇ります。昭和57年(1982年)に箕輪門とともに二階櫓、多門櫓が再建され、平成5年から7年にかけて本丸の修復工事により本丸石垣や天守台が整備されました。箕輪門は丹羽光重により最初に建造された櫓門で、領内の箕輪村から調達したカシの巨木を使用したためこの名が付けられました。
石垣の技術と特徴
二本松城の石垣は時代により異なる積み方が見られます。安土城の石垣を積んだ穴太衆と呼ばれる優れた石工集団により築かれた石垣があり、大手門跡では亀甲積み崩しの技法による石垣の一部が現存しています。本丸石垣は打込接布積み崩し、大石垣は野面積み布積み崩しの技法で築かれており、それぞれ異なる時代の石積み技術を見ることができます。
戊辰戦争と二本松少年隊
幕末の戊辰戦争では二本松藩は奥羽越列藩同盟に参加し、新政府軍と戦いました。この時、12歳から17歳の少年たちで編成された「二本松少年隊」が故郷を守るために出陣し、若い命を散らしました。箕輪門前には彫刻家・橋本堅太郎氏による「二本松少年隊群像」が平成8年(1996年)に建立され、その勇気と志を後世に伝えています。
現代の整備と活用
現在は「霞ヶ城公園」として整備され、平成19年(2007年)に国史跡に指定されました。日本さくら名所100選にも選定され、春には約2,500本の桜が咲き誇ります。秋には全国的に有名な「二本松の菊人形」が開催され、多くの観光客が訪れます。令和4年(2022年)には「にほんまつ城報館」が開館し、二本松城の歴史や発掘品を展示する拠点となっています。
城郭の構造と防御
城域は東に口を開けた馬の蹄のような形をしており、東側の開口部に水堀と門を築いて守りを固めています。地形的な弱点となる西側の搦手には大隣寺と龍泉寺を配置して防御力を補完しました。本丸、二の丸、三の丸の曲輪構成で、総面積は約18万平方メートルに及びます。
文化的価値と教訓
二本松城には7代藩主・丹羽高寛が設置した「戒石銘」があり、藩士の心得を刻んだ石碑として現在も残されています。また、洗心亭などの茶室跡も確認されており、武家文化だけでなく茶の湯文化も育まれていたことがわかります。城跡は中世の遺構と近世の城郭が残る特色ある史跡として、歴史的価値の高い文化遺産です。
アクセス・見学情報
JR東北本線二本松駅から徒歩約20分、車で約5分。東北自動車道二本松ICから約5分。駐車場は大型2台、普通車40台収容可能。日本100名城スタンプは「にほんまつ城報館」(9:00~17:00、月曜休館)またはJR二本松駅構内観光案内所で押印できます。御城印は2種類あり、箕輪門と丹羽氏の家紋「直違紋」をデザインしたものが各300円で販売されています。
アクセスマップ
関連リンク
散歩記録

御城印情報

スタンプ情報