103.浪岡城
続100名城基本情報
| 住所 | 青森県青森市浪岡大字浪岡字五所 |
|---|---|
| 電話 | 0172-62-1020(青森市中世の館) |
| 築城年 | 1460年代(応仁期) |
営業情報
| 開館時間 | 9:00〜17:00(青森市中世の館) |
|---|---|
| 入場料 | 一般210円、高校生110円、中学生以下無料 |
| 休館日 | 月曜日(祝日の場合翌日)、第3日曜日、年末年始 |
1. 浪岡城の概要と歴史的地位
浪岡城(なみおかじょう)は、青森県青森市浪岡にあった15世紀後半の中世平山城で、浪岡北畠氏によって築かれました。「浪岡御所」の敬称で呼ばれるほど高い権威を持ち、津軽地方における政治・文化の中心地として機能しました。浪岡川と正平津川の合流点右岸段丘面に築かれた総面積約13万6千平方メートルの大規模な城郭で、1940年2月10日に青森県初の国史跡に指定され、2017年には続日本100名城(103番)に選定されました。
2. 築城の背景と浪岡北畠氏の来住
浪岡城の築城は1460年代の応仁期頃、4代北畠顕義によって本格的に行われたとされています。浪岡北畠氏は建武の新政(1334~1336年)に活躍した北畠親房の子孫で、応永年間(1394~1428年)に岩手県閉伊地方から浪岡へ移住しました。南部氏が津軽支配にその権威を利用しようとして連れてきたと言われ、京都の公卿の日記にも登場するほど朝廷とのつながりを保持し、「御所」として特別の地位を築きました。
3. 城郭構造と立地の特徴
浪岡城は東側から新館、東館、猿楽館、北館、内館、西館、検校館の7つの館と無名館で構成される連郭式の平山城です。各館は幅20メートル、深さ5メートルほどの二重堀で分けられ、内館が城主の居住した本丸に相当し、他の館には武家屋敷が配置されていました。城の南側の急峻な崖下には浪岡川と正平津川が流れ、天然の堀と水源を兼ね、北東へと続く丘陵の南端という要害の地に立地していました。
4. 発掘調査と出土遺物の価値
1977年度から本格的な発掘調査が開始され、食器や調理器具、武器類、農耕具、日用品、宗教用具、建築関係用品など様々な遺物が5万点以上出土しました。その中でも陶磁器が1万6千点と特に多く、その半数以上が中国製であることから浪岡北畠氏の高い文化水準と国際的な交流が明らかになっています。また中国製茶壺なども発見され、浪岡北畠氏の特別な権威を示す貴重な資料として中世の館で保管展示されています。
5. 現在の保存状況と活用
浪岡城跡は現在、史跡公園として整備され、浪岡城跡案内所が設置されています。隣接する青森市中世の館では、浪岡城跡から出土した遺物や推定復元模型から中世の浪岡城の生活を再現し展示しています。1562年の川原御所の乱により勢力が衰え、1578年に大浦(津軽)為信に攻められ落城しましたが、その後約400年間畑や水田として使われてきた城跡が、現在は青森県を代表する中世史跡として保存・活用されています。続日本100名城スタンプは中世の館、浪岡交流センターあぴねす、城跡案内所で押印できます。
アクセスマップ
関連リンク
散歩記録

御城印情報

スタンプ情報
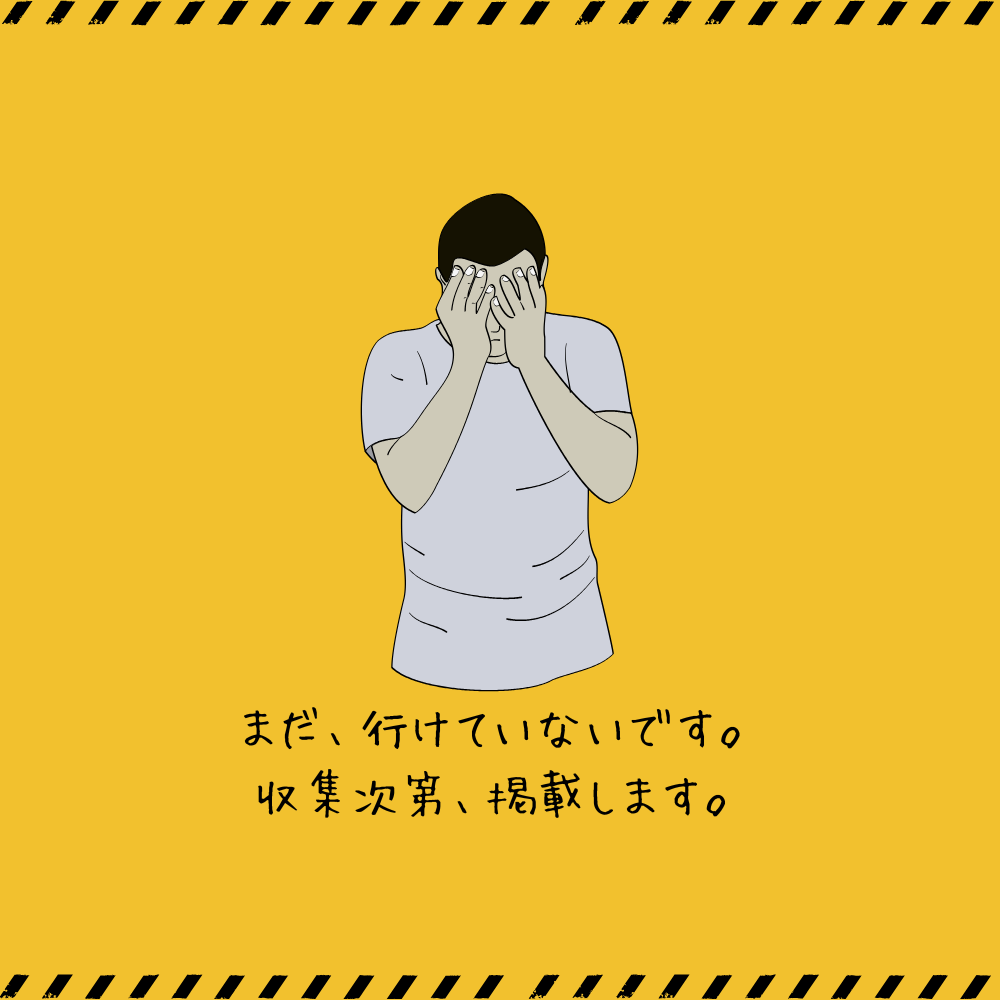
青森市浪岡交流センターあぴねす
浪岡城跡案内所

