121.本佐倉城
続100名城基本情報
| 住所 | 千葉県佐倉市大佐倉・印旛郡酒々井町本佐倉 |
|---|---|
| 電話 | 043-496-1171(酒々井町教育委員会) |
| 築城年 | 文明年間(1469年~1486年) |
営業情報
| 開館時間 | 案内所9:00~16:30(城跡は随時見学可能) |
|---|---|
| 入場料 | 無料 |
| 休館日 | 月曜日(祝日の場合翌日)・祝日翌日・年末年始 |
1. 本佐倉城の歴史と千葉氏
本佐倉城は千葉県佐倉市大佐倉と印旛郡酒々井町本佐倉にまたがる将門山にあった平山城で、千葉氏後期の本拠地となりました。文明年間(1469年~1486年)に千葉輔胤によって築城され、従来の亥鼻城より内陸の要衝である本佐倉に新たな本拠を構えました。16世紀前半には城下町も整備され、下総国の政治・経済・軍事の中心として大いに繁栄し、千葉氏3代勝胤の時代に最盛期を迎えました。
2. 戦国時代の発展と北条氏との関係
戦国時代を通じて本佐倉城は千葉氏の居城として機能し続け、千葉氏は北条氏と姻戚関係を強固に結んで勢力を維持しました。城は南方が谷になっている半島状の丘陵地に築かれ、残る三方が湿地帯に囲まれた天然の要害となっていました。16世紀には城郭として本格的に整備され、複雑な虎口や大規模な空堀・土塁・櫓台に守られた郭群が形成されました。城域は南北2キロメートル、東西1キロメートルに及ぶ巨大な城郭でした。
3. 城郭構造と防御システム
本佐倉城は城山・奥ノ山・東山・セッテイ山などの複数の郭から構成される大規模な城郭で、城山が最も重要な郭として千葉氏の主殿や複数の櫓が建てられていました。東山虎口は特に防御が固く、内と外にそれぞれ門があり、通路は曲がりくねって先が見えないよう工夫されていました。大堀切は城山と奥ノ山を分ける重要な防御施設で、深く巨大な規模を誇っています。妙見宮が置かれた奥ノ山や倉跡と呼ばれる郭なども確認されています。
4. 豊臣政権下での滅亡と廃城
天正18年(1590年)の豊臣秀吉による小田原攻めにおいて、千葉氏は北条氏とともに滅亡し、本佐倉城は千葉氏の居城としての役割を終えました。千葉氏が北条氏に従ったため、豊臣方に敗れて所領を失い、約120年間続いた本佐倉城での千葉氏の支配は終焉を迎えました。その後、城は徳川家康の支配下に入りましたが、慶長年間に土井利勝が新たに佐倉城を築いたため、本佐倉城は廃城となりました。
5. 史跡指定と現在の保存状況
本佐倉城跡は現在でも土塁や空堀などの遺構がほぼ完全な姿で保存されており、平成10年(1998年)に千葉県内の城郭として初めて国の史跡に指定されました。平成29年(2017年)には続日本100名城(121番)に選定され、千葉県では大多喜城とともに選ばれています。国史跡本佐倉城跡案内所では城跡の歴史を解説した展示や出土遺物の展示が行われており、続日本100名城のスタンプは案内所と京成大佐倉駅に24時間押印可能で設置されています。
アクセスマップ
関連リンク
散歩記録

御城印情報

スタンプ情報
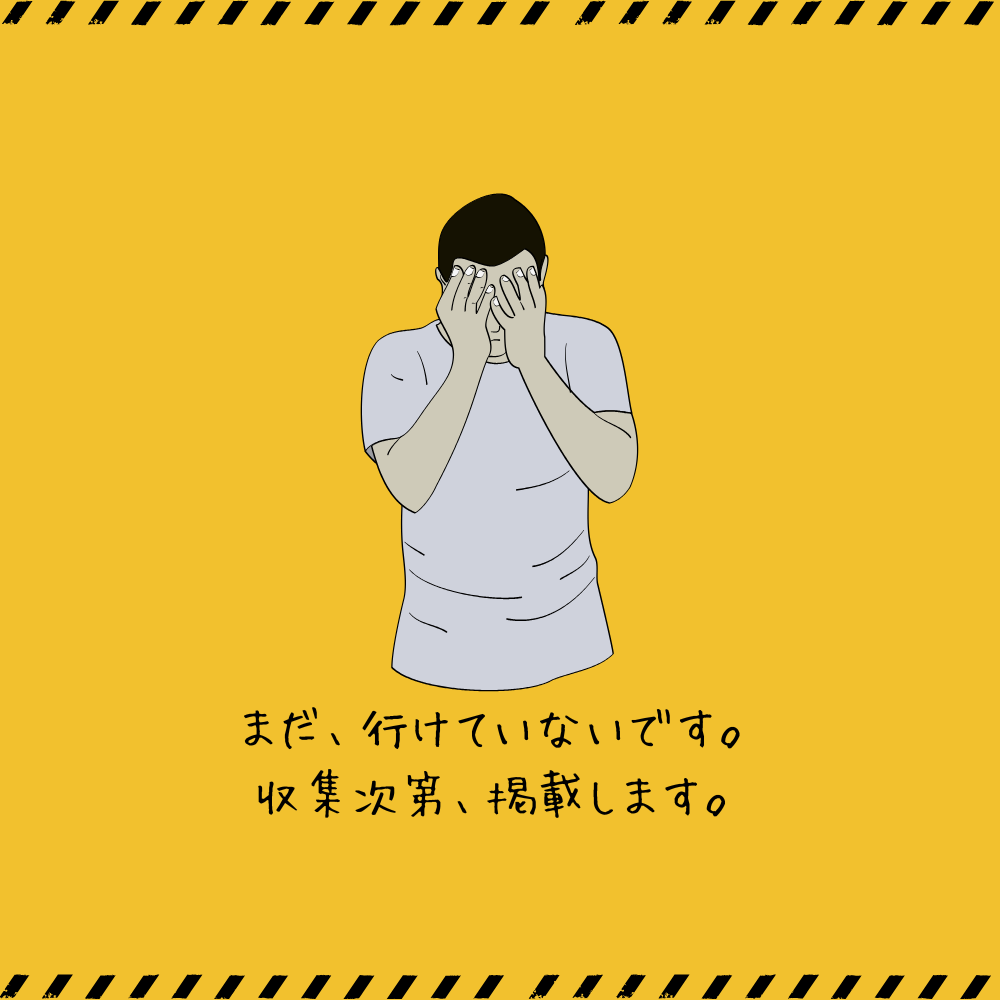
京成大佐倉駅


