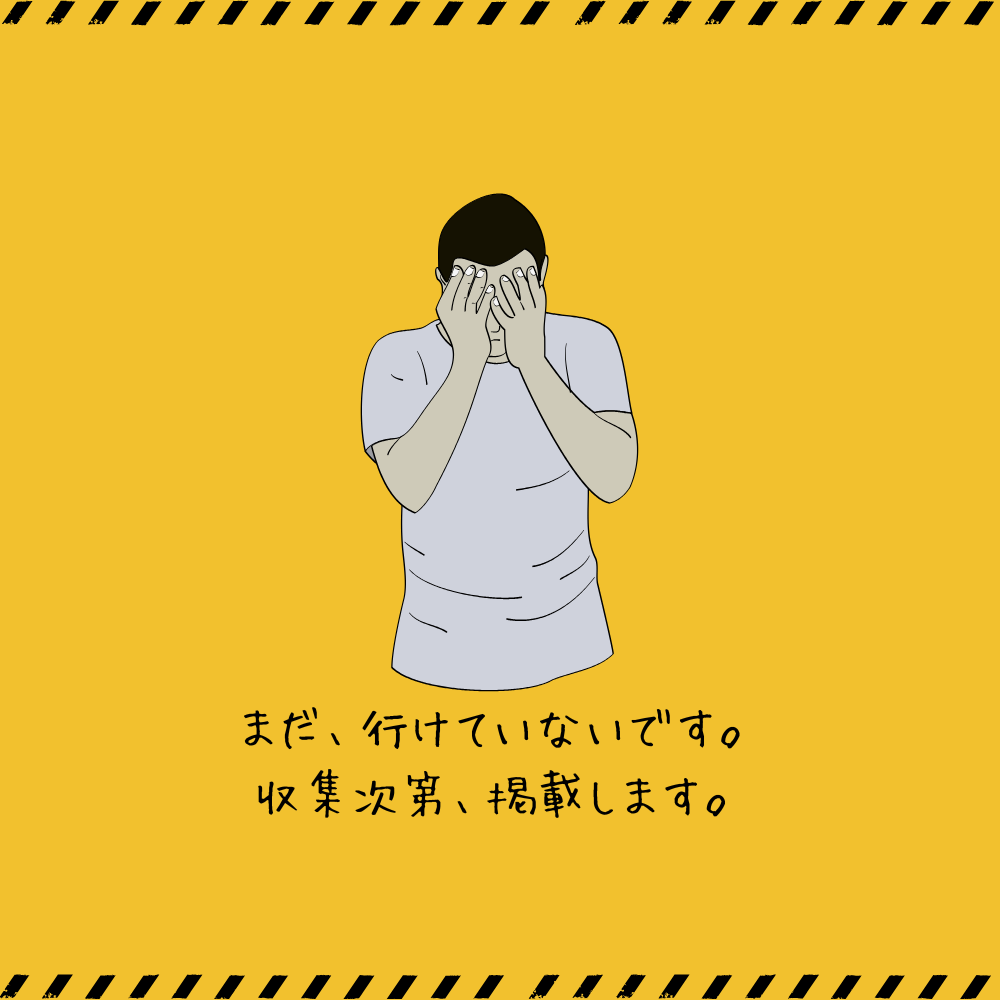14.水戸城
日本100名城基本情報
| 住所 | 茨城県水戸市三の丸1-6-29 |
|---|---|
| 電話 | 029-306-8132(歴史文化財課) |
| 築城年 | 建久年間(1190-1199年) |
営業情報
| 開館時間 | 散策自由(弘道館 9:00-17:00/16:30) |
|---|---|
| 入場料 | 散策無料(弘道館 大人400円、小中学生200円) |
| 休館日 | 無休(弘道館 月曜日・年末年始) |
1. 水戸城の概要と歴史的価値
水戸城は茨城県水戸市に位置する連郭式平山城で、徳川御三家のひとつ水戸徳川家の居城として江戸時代を通じて重要な役割を果たしました。日本最大級の土造りの城として知られ、石垣を用いず土塁と空堀で構成された戦国期東国の典型的な城郭です。水戸黄門で知られる徳川光圀や最後の将軍徳川慶喜ゆかりの地として、また日本最大規模の藩校弘道館の所在地として歴史的価値が高く評価されています。
2. 築城の起源と馬場氏時代
水戸城の歴史は平安時代末期から鎌倉時代初期にまで遡り、馬場小次郎資幹が那珂川と千波湖に挟まれた台地の東端に館を築いたのが始まりとされています。この頃は「馬場城」と呼ばれ、馬場氏が200年以上にわたって居城としていました。三方を水に囲まれた天然の要害を活用した立地で、後の水戸城の基礎となる地形的特徴がすでに認識されていました。
3. 江戸氏による発展と佐竹氏の大改修
室町時代の1416年に江戸通房が馬場城を攻略し、江戸氏の支配が約170年続きました。江戸氏時代には二の丸が築かれ、現在の本丸が内城、二の丸が重臣の屋敷地として機能する基本的な縄張りが形成されました。1590年の小田原征伐で佐竹義宣が江戸氏を滅ぼして入城すると、太田城から本拠を移して大規模な改修を実施し、城名も「水戸城」に改められました。
4. 水戸徳川家の居城としての発展
関ヶ原の戦い後、佐竹氏が秋田に転封されると、徳川家康の五男武田信吉、次いで十男徳川頼宣、そして頼宣の弟頼房が入城し、水戸徳川家の居城となりました。頼房の時代に城門や櫓門が新築され、二の丸を本城として三階の物見櫓が建造されました。しかし参勤交代を行わない江戸定府大名であったため、城内の建築物は他の御三家と比べて質素でした。
5. 弘道館と教育・文化の拠点
天保12年(1841年)、九代藩主徳川斉昭により三の丸に日本最大規模の藩校弘道館が建造されました。弘道館は単なる学問所ではなく、武芸や医学も含む総合教育機関として機能し、幕末の尊王攘夷思想の発信地ともなりました。至善堂では最後の将軍徳川慶喜が幼少期を過ごし、水戸城は江戸時代の教育・文化の重要な拠点として発展しました。
6. 城郭の構造と防御システム
水戸城は東西に長い台地を巧みに利用した連郭式の縄張りで、本丸・二の丸・三の丸が西から東へ一直線に配置されています。各曲輪は巨大な空堀で仕切られ、特に本丸と二の丸間の堀は現在JR水郡線が通るほどの規模を誇ります。石垣を用いない土造りの城として、大規模な土塁と五重の堀により堅固な防衛線を築いていました。
7. 明治以降の変遷と戦災
明治4年(1871年)の廃藩置県により廃城となった水戸城は、翌年放火事件により本丸隅櫓を焼失しました。その後も建物の多くが解体され、昭和20年(1945年)の水戸空襲により三階櫓をはじめとする主要建築物が焼失しました。城跡の多くは学校用地となり、現在も水戸第一高校をはじめ複数の教育機関が立地する文教地区となっています。
8. 復元事業と現在の見どころ
水戸市では水戸城の復元整備事業を進めており、2020年に大手門、2021年に二の丸角櫓がそれぞれ復元されました。大手門は高さ13メートル、幅17メートルの巨大な櫓門で、土塁に取り付く大手門としては国内屈指の規模を誇ります。薬医門は水戸城唯一の現存建築物として水戸第一高校内に移築保存されており、往時の姿を伝える貴重な遺構です。
9. アクセスと観光情報
水戸城跡はJR水戸駅北口から徒歩約10分の好立地にあり、公共交通機関でのアクセスが非常に良好です。車の場合は北関東自動車道水戸南ICから約15分です。弘道館は有料ですが、城跡の散策は無料で楽しむことができます。日本100名城スタンプは弘道館料金所窓口で取得でき、御城印も弘道館内や水戸観光案内所で購入可能です。
10. 水戸城と日本100名城
水戸城は平成18年(2006年)に日本100名城の14番に選定されました。徳川御三家の居城としての歴史的重要性、日本最大級の土造りの城としての城郭史的価値、弘道館をはじめとする教育・文化的遺産が評価されています。偕楽園との組み合わせで日本遺産にも認定されており、水戸の歴史と文化を代表する観光拠点として多くの城郭ファンや歴史愛好家が訪れています。水戸黄門や徳川慶喜ゆかりの地として、江戸時代の政治・文化を学ぶ貴重な史跡でもあります。
アクセスマップ
関連リンク
散歩記録

御城印情報

スタンプ情報