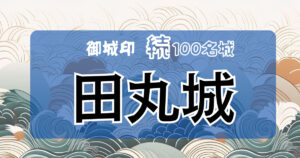36.丸岡城
日本100名城基本情報
| 住所 | 福井県坂井市丸岡町霞町1丁目59 |
|---|---|
| 電話 | 0776-66-0303(丸岡城管理事務所) |
| 築城年 | 1576年(天正4年) |
営業情報
| 開館時間 | 8:30~17:00(最終入館16:30) |
|---|---|
| 入場料 | 大人450円、小中学生150円(丸岡城・一筆啓上日本一短い手紙の館共通券) |
| 休館日 | 年中無休 |
1. 歴史と築城の経緯
丸岡城は天正4年(1576年)、織田信長の命により一向一揆への備えとして、柴田勝家の甥である柴田勝豊によって築かれた。福井平野丸岡市街地の東に位置する小高い独立した丘陵に築かれた平山城で、別名を霞ヶ城という。勝豊は城下町の整備も行い、これが現在の丸岡の都市的起源となった。天正10年(1582年)の本能寺の変後、勝豊は近江国長浜城に移され、安井家清が入城した。
2. 歴代城主の変遷
天正11年(1583年)に柴田勝家が滅ぼされると、越前国は丹羽長秀の所領となり、青山宗勝が城主となった。その後、青山家は関ヶ原の戦いで西軍についたため改易され、結城秀康の家臣今村盛次が入城した。元和元年(1615年)からは本多成重が入り、本多氏が明治まで8代にわたって治めた。最後は有馬氏が短期間城主を務め、明治4年(1871年)の廃藩置県により廃城となった。
3. 現存12天守の価値
丸岡城天守は江戸時代以前に建設された現存12天守の一つで、北陸地方では唯一の現存天守である。外観は2層、内部は3階の独立式望楼型天守で、大入母屋の上に廻り縁のある小さな望楼を載せた古式の外観を持つ。当初は現存最古の天守とされていたが、2019年の調査により江戸期の寛永年間(1624-44年)の建造であることが判明し、国の重要文化財に指定されている。
4. 福井地震と奇跡の修復
昭和23年(1948年)6月28日、マグニチュード7.1の福井地震により丸岡城天守は石垣もろとも完全に倒壊した。甚大な被害により誰もが絶望していたが、修復を願う多くの人々の熱い想いと全国からの寄付により、柱や梁など主要部分の70%以上を再利用してわずか7年で奇跡的な修復を成し遂げた。現存12天守の中で完全に倒壊した状況から修復された天守は丸岡城のみで、まさに奇跡といえる。
5. 建築の特色
丸岡城天守の最大の特徴は全国的にも稀な石瓦(笏谷石製)で葺かれた屋根である。この石瓦は重量が約120トンにも及び、石垣への荷重分散を考慮した設計となっている。石垣は「野面積み」という古い方式で積まれており、隙間が多く粗雑な印象だが排水性に優れ、大雨でも崩れにくい構造となっている。通し柱がない構造で、1階が2・3階を支える独特の建築方式を採用している。
6. 天守内部と見どころ
丸岡城天守内部の階段は現存天守の中でも特に急勾配で、2階、3階への階段はほとんど梯子に近い角度となっている。これは敵の侵入を防ぐ防御機能の一つでもあった。天守最上階からは福井平野を一望でき、戦国時代には周囲を見渡す重要な軍事拠点としての役割を果たしていた。天守入口脇には福井地震で落下した笏谷石製の鯱が展示されており、当時の被災状況を物語っている。
7. 霞ヶ城と桜の名所
丸岡城は「霞ヶ城」という美しい別名を持ち、これは春に満開の桜に包まれる様が薄紅色の霞に包まれたように見えることに由来する。城内には約400本のソメイヨシノが植えられており、「日本さくら名所100選」に認定されている。毎年4月上旬から中旬にかけて「丸岡城桜まつり」が開催され、ライトアップされた夜桜と天守の美しいコントラストを楽しむことができる。
8. アクセスと観光情報
丸岡城へは、北陸新幹線福井駅から京福バス丸岡線で約45分、「丸岡城」バス停下車すぐでアクセスできる。北陸自動車道丸岡ICからは車で約5分の立地にある。霞ヶ城公園内は散策自由で、天守以外にも一筆啓上日本一短い手紙の館などの関連施設がある。無料駐車場も完備されており、観光バスでの来城も可能である。
9. 日本100名城スタンプと御城印
日本100名城スタンプは丸岡城券売所隣の観光案内所に設置されており、営業時間8:30~17:00の間はいつでも押印可能である。御城印は券売所で300円で販売されており、通常版のほか「一筆啓上 火の用心 お仙泣かすな 馬肥やせ」をモチーフにした特別版もある。さらに5種類のスタンプを重ね捺しするオリジナル御城印も楽しめる。
10. 現在の取り組みと未来展望
現在、丸岡城では国宝指定を目指す取り組みが進められており、2013年に坂井市が国宝化推進事業を立ち上げ、2017年には市民の会も発足した。また、2023年には歴史的風致維持向上計画の一環として城山整備が計画され、2025年度から発掘調査が開始予定である。令和7年12月からは耐震対策を含む大規模修理も予定されており、この貴重な文化遺産を後世に確実に継承するための取り組みが続けられている。
アクセスマップ
関連リンク
散歩記録

御城印情報

スタンプ情報