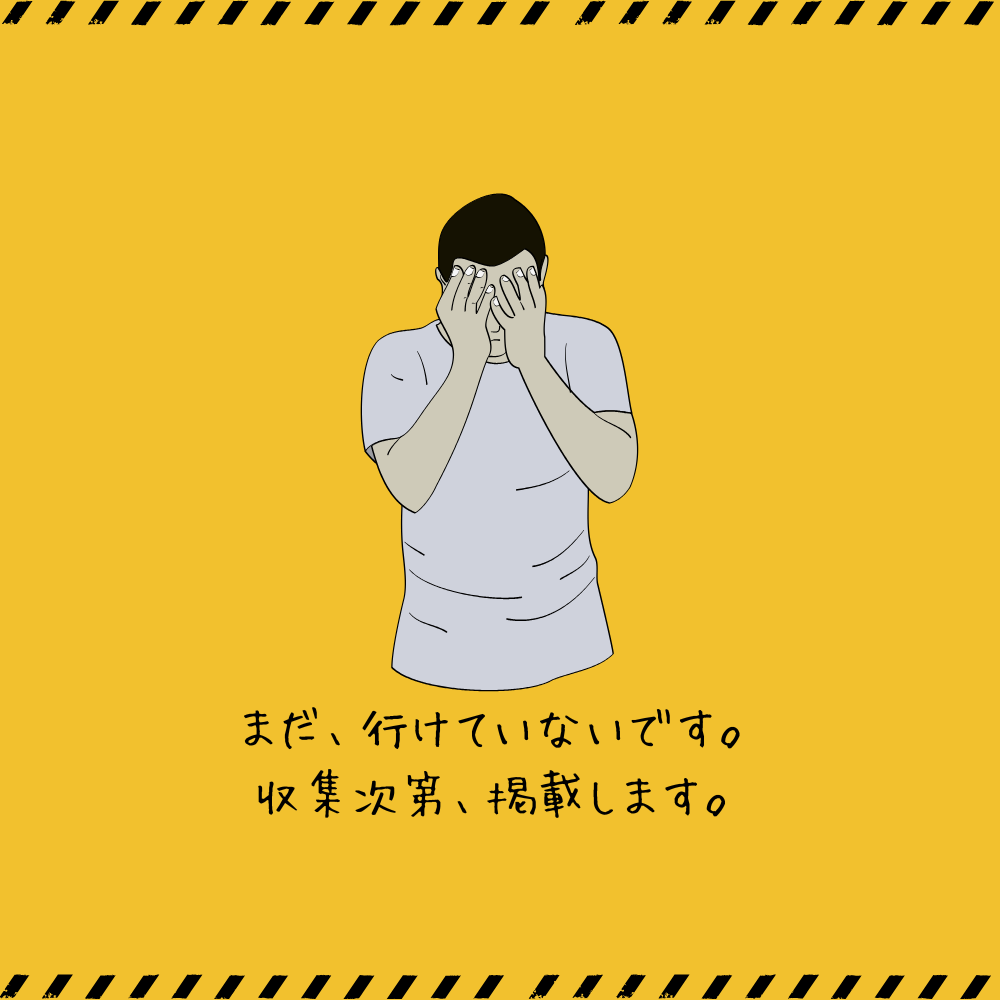112.笠間城
続100名城基本情報
| 住所 | 〒309-1611 茨城県笠間市笠間3616 |
|---|---|
| 電話 | 0296-72-9222(かさま歴史交流館井筒屋) |
| 築城年 | 1219年(承久元年) |
営業情報
| 開館時間 | 9:00~22:00(かさま歴史交流館井筒屋) |
|---|---|
| 入場料 | 無料 |
| 休館日 | 月曜日(祝日の場合は翌日) |
1. 笠間城の概要
笠間城(かさまじょう)は、茨城県笠間市の佐白山にあった日本の城。江戸時代には、笠間藩の藩庁が置かれた。鎌倉時代、この地域は真言宗の正福寺と徳蔵寺の勢力争いが盛んであり、両寺院の僧兵たちが争っていた。劣勢であった正福寺勢が下野守護宇都宮頼綱に援軍を求めたところ、頼綱は甥の笠間時朝(塩谷時朝)を派兵した。時朝は元久2年(1205年)、徳蔵寺の僧兵と戦うための拠点として佐白山山麓に麓城を築城し、徳蔵寺を討った。時朝は結局正福寺と徳蔵寺を滅ぼした後、承久元年(1219年)、堅固な城を佐白頂上に築城した。これが笠間城の起こりとされる。
2. 城の特徴と構造
笠間城は、天守曲輪を持ち、石垣が構築された城郭として注目されている山城である。自然の地形を利用した曲輪、空堀と櫓、門、橋、塀などによって「守るに易く、攻めるに難い」山城であった。浸食谷が複雑に入り組む地形を利用し、本丸から段状に二の丸、三の丸(帯曲輪)が連なり、大手門の先には的場丸が配置されている。本丸よりも高所の独立した場所に天守曲輪があり、天守が築かれていた。天守は2重で、「常盤国笠間之城絵図」(正保城絵図)では天守曲輪にその姿が描かれているが、具体的な外観や構造はわかっていない。
3. 歴史的意義
1590年(天正18年)の豊臣秀吉による小田原征伐の際に笠間綱家が北条氏についたため、滅亡させられた。その後、いったんは宇都宮氏が支配したが、のちに蒲生郷成が入城し、この郷成の手により織豊系城郭に改修された。現在も確認できる石垣遺構はこの時代のものと考えられている。蒲生氏以降も松平、小笠原、永井、浅野、井上、本庄などの諸氏が入れ替わり城主をつとめ、1747年(延享4年)から廃藩までは、牧野氏代々の居城となった。ちなみに忠臣蔵で有名な浅野氏は、ここから赤穂藩に移っている。
4. 現在の状況
山上の遺構は良く旧態を留めており、一部に後世の手が加えられているものの、石垣、堀などが残る。山麓居館部の保存状態は必ずしも良くないが、現在佐山麓公園として整備され公開されている。東日本大震災により、天守曲輪の石垣や石段が崩壊するなど大きな被害があったため、一部仮修復を行ったが、依然として天守付近は「立入禁止区域」を設けている。佐白山頂に築かれた笠間城は、鎌倉時代に笠間時朝(1203~1265)が築いてから約750年間、歴代の笠間領主の居城となってきた。
5. 文化的価値
建造物の遺構としては、本丸八幡台上にあった八幡台櫓が真浄寺に移築され現存し、「笠間城櫓」として茨城県の文化財に指定されている。また、薬医門形式の城門2棟が、市内の民家に移築され現存する。笠間城の明治廃城後、解体を受けた天守の用材は佐志能神社(笠間城天守台に所在)の拝殿に使用されている。中井均は、転用材を使用したという拝殿の状態から、天守をそのまま改築して造ったものと推測している。また、田中嘉彦(笠間史談会会長)は調査によって、天守は移築現存する八幡台櫓とほぼ同一の構造であったと推測している。
アクセスマップ
関連リンク
散歩記録

御城印情報

スタンプ情報