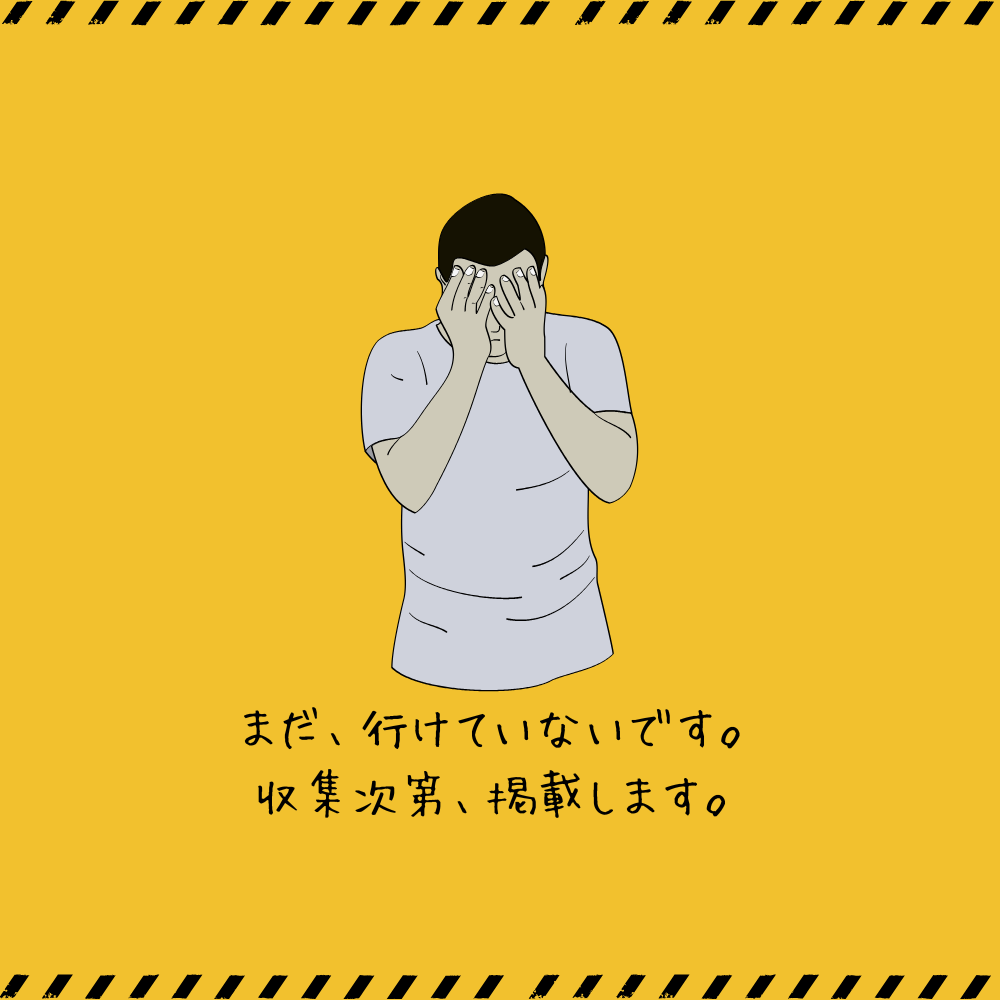114.唐沢山城
続100名城基本情報
| 住所 | 栃木県佐野市富士町・栃本町 |
|---|---|
| 電話 | 0283-24-5111(佐野市教育委員会) |
| 築城年 | 平安時代(延長5年・927年頃)藤原秀郷による築城の伝承、実際は15世紀後半 |
営業情報
| 開館時間 | 24時間(神社社務所は9:00~17:00) |
|---|---|
| 入場料 | 無料 |
| 休館日 | なし |
1. 唐沢山城の歴史
平将門の乱を平定した藤原秀郷が延長5年(927年)頃に築城したという伝承があるが、最近の研究では唐沢山城の起源は15世紀後半までしか遡らないことが明らかにされている。室町時代中期の延徳3年(1491年)には佐野盛綱が城の修築を行った。戦国時代において、佐野氏第15代当主・佐野昌綱による唐沢山城の戦いで有名で、上杉謙信の10度にわたる攻城を受けたが、度々撃退して謙信を悩ませた。1602年(慶長7年)、唐沢山麓に築城された佐野城(春日岡城)に佐野氏が移ったため、唐沢山城は廃城となった。
2. 唐沢山城の構造と特徴
佐野市街地の北方約5キロメートルの唐沢山(247メートル)山頂を本丸として一帯に曲輪が配された連郭式山城である。関東地方の古城には珍しく高い石垣が築かれているのが特徴で、高さ最大8mをこえる石垣を有する城郭となっている。本丸から西側には、二の丸、三の丸、天徳丸などが階段状に造られており、南の尾根には南丸が、北東の尾根には長門丸、金の丸、杉曲輪、北城などが置かれていた。急崖と、複雑に入り組んだ尾根や沢などに囲まれた要害堅固な山城であった。
3. 現在の唐沢山城
現在は栃木県立自然公園として整備され、2014年(平成26年)には国の史跡に指定された。本丸跡には1883年(明治16年)に唐沢山神社が建立され、藤原秀郷が祀られている。堀切や土塁、大手枡形、曲輪などが良好な状態で残されており、かつての姿をイメージすることが可能である。特に貴重な史跡として有名なのが「くい違い虎口」で、石垣や土塁をくい違い状に組み合わせることで、敵が直線的に攻め入れないように工夫されている。
4. 唐沢山城の文化的意義
関東七名城の一つに数えられ、上杉謙信を何度も撃退したことで「関東一の山城」と賞賛された。戦国時代の佐野氏は相模の北条氏、越後の上杉氏の二大勢力に挟まれた立地にあったため、たびたび戦場となった。唐沢山城は謙信においては関東における勢力圏の東端であり、佐竹氏をはじめとする北関東の親上杉派諸将の勢力圏との境界線でもあったため、特に重要視された。関東では希少な織豊系築城技術によって改修が重ねられ、戦国期における城郭発達史上の重要な遺跡である。
5. 唐沢山城の見どころ
戦国時代にも使われていた井戸「大炊井」や城の最大の防御地だった「帯廓」など、見られる遺構の数は全国でも有数の充実ぶりである。また、高石垣からは関東平野一帯が見渡すことができ、天気が良ければ富士山や東京スカイツリーも見ることができる。唐沢山神社では御城印が販売されており、続日本100名城のスタンプも設置されている。春は桜、秋は紅葉の景色を楽しめる自然豊かな史跡である。
アクセスマップ
関連リンク
散歩記録

御城印情報

スタンプ情報