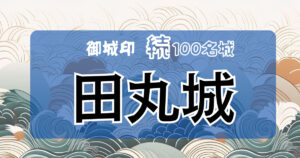38.岩村城
日本100名城基本情報
| 住所 | 岐阜県恵那市岩村町字城山 |
|---|---|
| 電話 | 0573-43-3057(岩村歴史資料館) |
| 築城年 | 1185年(文治元年) |
営業情報
| 開館時間 | 岩村歴史資料館:9:00~17:00(4月~11月)、9:30~16:00(12月~3月) |
|---|---|
| 入場料 | 岩村歴史資料館:一般300円、65歳以上200円、18歳以下無料 |
| 休館日 | 月曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始 |
1. 岩村城の歴史と概要
岩村城は1185年(文治元年)に源頼朝の重臣である加藤景廉によって築かれた山城で、岐阜県恵那市岩村町の標高717mの城山山上にあります。奈良県の高取城、岡山県の備中松山城と並んで「日本三大山城」の一つに数えられ、江戸諸藩の府城の中でも最も高い所に築かれた要害堅固な山城です。鎌倉時代から明治維新まで約700年間にわたって存続し、日本の城史においても稀有な長い歴史を持つ名城として知られています。
2. 遠山氏と女城主おつやの方
加藤景廉の長男景朝が遠山氏を称して岩村城主となって以来、戦国時代まで遠山氏が城主を務めました。戦国時代末期、城主遠山景任が病没すると、織田信長の五男御坊丸を養子として迎えていた夫人(織田信長の叔母)が実質的な城主として領地を治めました。この女城主「おつやの方」は大変聡明で美しく、領民に慕われていたと伝えられています。彼女の存在により、岩村は「女城主の里」と呼ばれるようになりました。
3. 武田氏との攻防と政略結婚
1572年(元亀3年)、武田信玄の24将の一人である秋山虎繁(信友)が大軍を率いて岩村城に侵攻しました。おつやの方は自ら采配を振るい、織田信長の援軍を待って籠城作戦を展開しましたが、信長は他の戦線で忙しく援軍を送ることができませんでした。3ヶ月にわたる籠城の末、食糧不足に陥った城内で、虎繁はおつやの方との政略結婚を条件とした無血開城を提案。おつやの方は城兵や領民の命を守るため、苦渋の決断で敵将との結婚を受け入れました。
4. 織田軍による奪還と悲劇的結末
1575年(天正3年)、長篠の戦いで武田勝頼軍が敗北したことにより、武田と織田の勢力関係が逆転しました。織田信長は嫡男信忠を大将とする大軍を派遣し、半年に及ぶ攻城戦の末に岩村城を奪還しました。信長は最初、領民を守りおつやの方と虎繁の命を助けるという条件で開城を受け入れましたが、その約束を反故にし、夫妻を磔刑に処しました。この出来事は「女城主の悲劇」として後世に語り継がれています。
5. 江戸時代の岩村藩と石垣の整備
1601年(慶長6年)に松平家乗が城主となって岩村藩が立藩されました。家乗は山上にあった城主居館を城の北西山麓に移し、城下町を整備しました。現在見られる見事な石垣の多くはこの時期に築かれたもので、特に本丸周辺の「六段壁」と呼ばれる石垣は岩村城の象徴的な存在となっています。江戸時代を通じて松平氏が城主を務め、1702年には全国で3番目となる藩校「文武所」(後の知新館)が設けられました。
6. 霧ヶ城の異名と霧ヶ井伝説
岩村城は別名「霧ヶ城」とも呼ばれています。この名前の由来となったのが、城内の八幡曲輪にある「霧ヶ井」という井戸です。「巌邑府誌」という書物によると、敵が攻めてきた際に城内秘蔵の大蛇の骨をこの井戸に投じると、たちまちして雲霧が湧き出て城を覆い尽くし、城を守ったと記されています。この井戸は城主専用の霊泉として使用され、山頂に位置しているにもかかわらず現在も湧き続けており、1987年には岐阜県の名水50選にも選ばれています。
7. 石垣の見どころと六段壁
岩村城最大の見どころは、関ヶ原の戦い後に松平家乗によって築かれた壮大な石垣群です。特に本丸北東側にある「六段壁」は、江戸時代後期に崩落を防ぐ補強のために下段に石垣を継ぎ足した結果、現在の6段の石垣となりました。総延長約1.7kmに及ぶ石垣は「東洋のマチュピチュ」とも称され、その荘厳な佇まいは多くの城郭ファンを魅了しています。城内には17箇所もの井戸があり、山城としては異例の豊富な水源を確保していました。
8. 現在の整備状況と見学施設
岩村城跡は1990年に表御門や太鼓櫓が復元され、山麓の岩村藩主居館跡には岩村歴史資料館が建てられています。資料館では城内の八幡神社の棟札、岩村城絵図、佐藤一斎自讃画像軸(いずれも重要文化財)など、岩村城と岩村藩の貴重な史料を収蔵・展示しています。また、城内15ヶ所に設置されたQRコードを読み込むと、享保の岩村城絵図を元に再現したCG映像で当時の城の姿を見ることができる最新の試みも行われています。
9. 城下町と重要伝統的建造物群保存地区
岩村城の麓には江戸時代の面影を残す城下町が広がり、1998年には国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。城下町には木村邸(江戸時代の大問屋)、土佐屋(染物工場)、岩村醸造(創業230年の酒蔵)など、当時の建物が数多く残されています。また、長崎にカステラが伝わった当時と同じ製法で作られるカステラで有名な松浦軒本店や、城の建材を利用した建物なども現存し、城下町全体が生きた歴史博物館となっています。
10. アクセスと観光情報
岩村城へは明知鉄道岩村駅から徒歩約25分、中央自動車道恵那ICから車で約20分でアクセス可能です。岩村歴史資料館前駐車場と本丸下の出丸駐車場があり、いずれも無料で利用できます。100名城スタンプは岩村歴史資料館受付窓口で押印でき、御城印は恵那市観光協会岩村支部(町並みふれあいの舘)と岩村山荘で300円で購入できます。毎年秋には「いわむら秋祭り」が開催され、築城した加藤景朝のご神体を乗せた神輿と時代衣装の行列が城下町を練り歩く勇壮な祭りが楽しめます。
アクセスマップ
関連リンク
散歩記録

御城印情報

スタンプ情報