117.岩櫃城
続100名城基本情報
| 住所 | 群馬県吾妻郡東吾妻町原町 |
|---|---|
| 電話 | 0279-68-2111(東吾妻町役場まちづくり推進課) |
| 築城年 | 室町時代(築城年不明、応永12年・1405年説、大永年間・1521-1528年説など) |
営業情報
| 開館時間 | 24時間(観光案内所:4-11月9:00~16:00) |
|---|---|
| 入場料 | 無料 |
| 休館日 | なし(観光案内所:12-3月休館) |
1. 岩櫃城の歴史
岩櫃城の築年代は不明で、築城者についても諸説ある。鎌倉時代に吾妻太郎助亮によって築城されたと伝わるが、応永12年(1405年)に斎藤憲行が築いたとする説や真田氏による築城だとする説もある。戦国時代、吾妻氏の子孫と称する斉藤憲次が岩櫃城を拠点として吾妻郡一帯の地侍を支配下においた。永禄6年(1563年)、武田信玄の命により真田幸隆が岩櫃城を攻略し、その後真田氏が支配した。真田昌幸の時代、天正10年(1582年)に織田信長・徳川家康勢に攻められて主家武田勝頼が劣勢となると、真田昌幸は武田勝頼を岩櫃城へ迎え入れて武田家の巻き返しを図ろうとしたが、武田家は滅亡した。
2. 岩櫃城の構造と特徴
吾妻川北岸の岩櫃山中腹に位置し、標高802メートルの岩櫃山全体を機能的に活かした巨大な山城である。甲斐の岩殿城、駿河の久能城と並んで、武田の三堅城と呼ばれている。西側、南側は巨岩による絶壁と吾妻川により守られており、主に上杉や北条を意識して東側の防御に重きをおいている。城域は広く、その中を沼田と上田を結ぶ街道を通してある。中心部の曲輪から放射状に壕が整備される特殊な構造で、周囲に出丸、番城、砦を配してあった。本丸の東側に二の丸、更に東側に中城が配置され、各曲輪の周りには横堀や竪堀が巡らされ、堅城となっている。
3. 現在の岩櫃城
現在は国の史跡に指定され、本丸の空堀、中城の竪堀、武田勝頼を迎えようと築いた潜龍院跡の石垣などが残され見どころとなっている。岩櫃山平沢登山口観光案内所が平成28年4月にオープンし、各種パンフレットをそろえ、主に岩櫃山周辺の案内を行っている。平沢登山口から本丸跡まで徒歩約15-20分で到着でき、登山道は整備されているので登りやすい山城となっている。本丸址には東屋があり、本丸には25m×15m程の土台跡があり、展望台や指揮台として利用されていたと考えられている。
4. 岩櫃城の文化的意義
岩櫃城は真田信繫(幸村)が幼少時代を過ごしたとされ、大河ドラマ「真田丸」でも注目を集めた。沼田城・名胡桃城と上田城を結ぶ街道の拠点としても重要な役割を担ってきた。真田昌幸は武田勝頼を岩櫃城へ迎え入れようとし、岩櫃山の麓に潜龍院という御殿を急造したが、勝頼は天目山で自刃したため実現しなかった。慶長19年(1614年)に幕府の一国一城令により岩櫃城は破却され、以後は原町(現在の東吾妻町原町)に陣屋を置いて一帯を統べた。
5. 岩櫃城の見どころ
本丸の空堀は本丸と二の丸の間の堀切、竪堀が繋がったもので、技巧的で規模が大きく見応えがある。中城の竪堀はV字型の薬研堀状となっていて、深さは2-3m程あり、全長100m以上にも及ぶ圧巻の遺構である。潜龍院跡の石垣は戦国時代の歴史ロマンを感じることができる見どころで、古谷登山口の駐車場から歩いて10-15分程で来ることができる。御城印は岩櫃城、密岩神社、金剛院のセットで500円で購入することができ、続日本100名城のスタンプも平沢登山口観光案内所に設置されている。
アクセスマップ
関連リンク
散歩記録

御城印情報

スタンプ情報
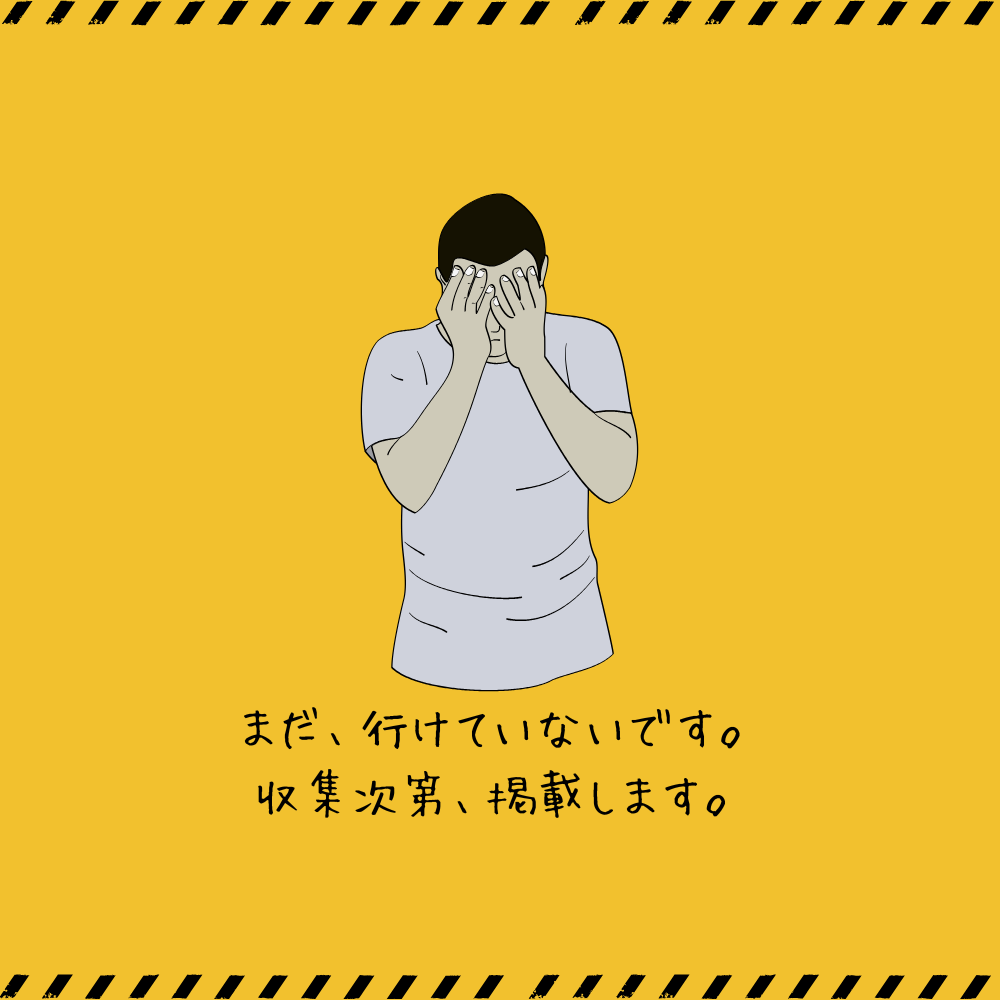
東吾妻町観光協会(12-3月)


