107.秋田城
続100名城基本情報
| 住所 | 秋田県秋田市寺内焼山9-6 |
|---|---|
| 電話 | 018-845-1837(秋田城跡歴史資料館) |
| 築城年 | 天平5年(733年) |
営業情報
| 開館時間 | 9:00〜16:30(秋田城跡歴史資料館) |
|---|---|
| 入場料 | 一般310円、高校生以下無料(歴史資料館) |
| 休館日 | 年末年始(12月29日〜1月3日) |
1. 秋田城の概要と歴史的地位
秋田城(あきたじょう/あきたのき)は、出羽国秋田(現在の秋田県秋田市)にあった天平5年(733年)創建の古代城柵で、朝廷によって設置された城柵の中でも最北に位置する重要な拠点でした。当初は「出羽柵(いではのき)」と呼ばれていましたが、天平宝字4年(760年)頃に「秋田城」に改称されました。秋田市寺内地区の雄物川河口近く、標高約40メートルの高清水丘陵上に立地し、1939年(昭和14年)に国史跡に指定され、2017年には続日本100名城(107番)に選定されました。
2. 出羽柵移転の背景と築城の経緯
秋田城の創建は、733年(天平5年)に出羽柵が山形県庄内地方から秋田村高清水岡に移転したことに始まります。7世紀中葉から9世紀初頭にかけて、朝廷は東北地方の蝦夷を制圧し、柵戸移民を扶植して支配域拡大を図っており、日本海側では708年(和銅元年)に庄内地方を越後国出羽郡として建郡、712年(和銅5年)には出羽国に昇格させていました。出羽柵の秋田移転は、庄内地方から一挙100キロメートルも北進した大胆な政策で、蝦夷制圧と北方経営の前進基地として位置づけられました。
3. 渤海との外交拠点としての機能
8世紀には沿海州付近にあった渤海国からの使節がたびたび出羽国へ来着し、秋田城は渤海使や北方民族との外交施設としての役割を担ったと考えられています。渤海使は沿海州・サハリン・北海道の沿岸部伝いに航行して本州日本海側に達する北回り航路を取っており、秋田城は海上交流の拠点として機能しました。発掘調査結果からも渤海との交流をうかがわせる複数の事実が指摘されており、奈良時代を通じて渤海使の受け入れが秋田城において行われた可能性が高いとされています。
4. 城郭構造と政庁機能
秋田城は東西・南北ともに550メートルの規模を持つ不整な多角形状の外郭線で囲まれ、外郭施設は当初幅2メートルほどの瓦葺きの築地で、後に掘立柱の塀に作り替えられました。政庁は東西94メートル、南北77メートルで、築地または材木塀で区画され、正殿や広場を配していました。政庁から外郭東門まで幅12メートルの大路が続き、古代水洗厠舎など当時としては先進的な設備も備えていました。出羽国の政治を行う国府が置かれ、東北の日本海側における政治・文化・軍事の中心地として機能しました。
5. 現在の保存状況と活用
秋田城は奈良時代の創建から10世紀中頃までの平安時代にかけて城柵としての機能を維持し、804年(延暦23年)の一時停廃や878年(元慶2年)の元慶の乱による被害を経ながらも、出羽国北部の軍事・行政拠点として存続しました。現在は高清水公園として整備され、秋田城の東門や築地塀の一部が復元されています。2016年に開館した秋田城跡歴史資料館では充実した展示により古代城柵の理解を深めることができ、2022年には歩行者用連絡橋が完成してAR・VR技術による往時の再現サービスも提供されています。
アクセスマップ
関連リンク
散歩記録

御城印情報

スタンプ情報
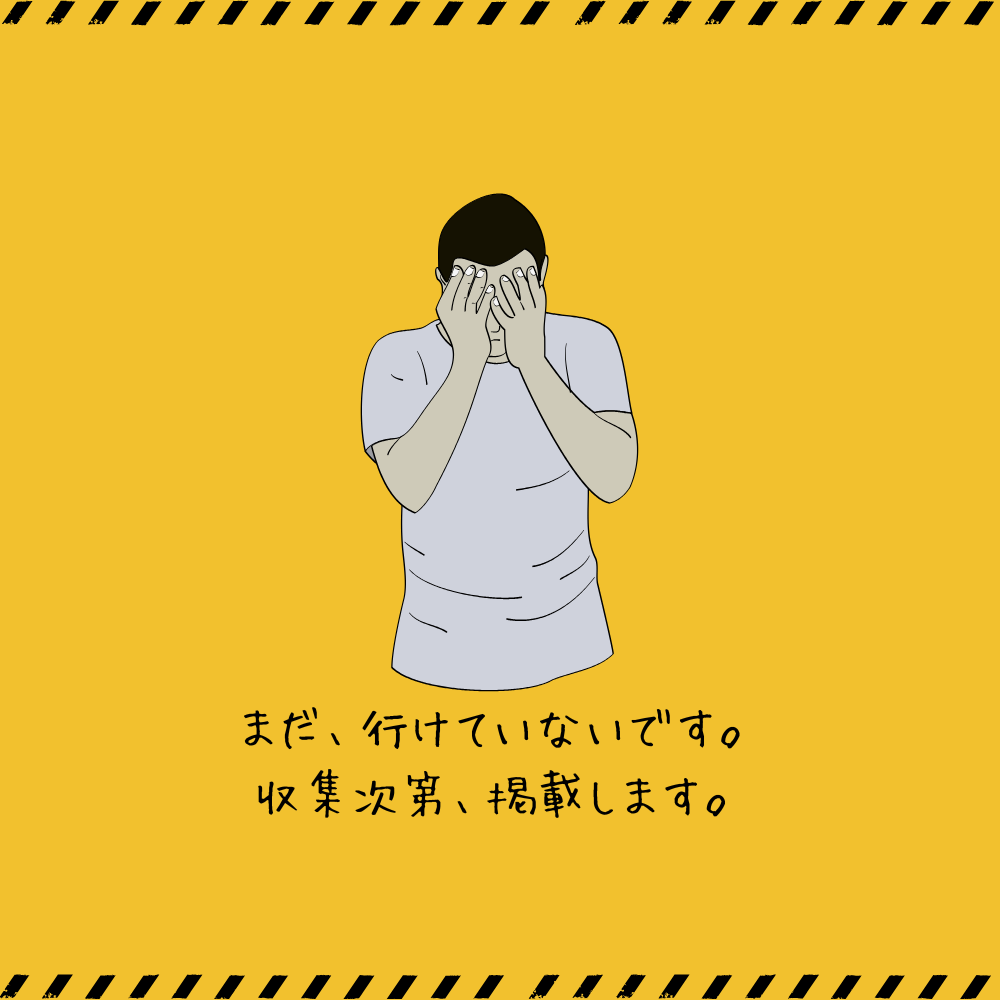
史跡公園管理棟

