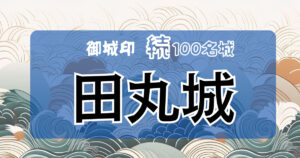32.春日山城
日本100名城基本情報
| 住所 | 新潟県上越市大字中屋敷 |
|---|---|
| 電話 | 025-545-9269(上越市文化行政課) |
| 築城年 | 南北朝時代(14世紀後半) |
営業情報
| 開館時間 | 24時間見学自由(ものがたり館は9:00〜16:30) |
|---|---|
| 入場料 | 無料 |
| 休館日 | なし(ものがたり館は月曜・冬季休館) |
1. 春日山城の概要と歴史的価値
春日山城は新潟県上越市に位置する山城で、標高182メートルの春日山全体を城郭化した戦国時代屈指の要塞です。南北朝時代に越後国守護上杉氏が築城し、長尾為景による大改修を経て上杉謙信の居城となりました。複雑な自然地形を巧みに利用した空堀や土塁が数多く配され、山全体が難攻不落の城塞として機能していました。現在は国の史跡に指定され、日本100名城にも選定されています。
2. 築城の経緯と長尾氏による拡充
春日山城は南北朝時代に越後国守護上杉氏が越後府中の詰城として築城したのが始まりとされます。永正4年(1507年)に守護代長尾為景が城主となり、既存の要害に大改修を施して本格的な山城として拡充・増強を実施しました。この改修により、春日山城は越後支配の重要拠点として戦国時代第一の要害に生まれ変わりました。
3. 城郭の構造と縄張り
春日山城は春日山の尾根北先端に本丸を中心とした「実城」と呼ばれる主郭部を置き、周辺に多くの曲輪を階段状に展開させて全山にわたって城郭化しています。本丸、二の丸、三の丸、南三の丸、千貫門、景勝屋敷、直江屋敷などが配置され、近接する山々には多数の支城を巡らして防備を固めていました。山の裾野には延長1.2キロメートルにも及ぶ堀と土塁で総構が築かれています。
4. 上杉謙信の居城として
長尾景虎(後の上杉謙信)は父為景から春日山城を受け継ぎ、関東管領を名乗って関東出兵の拠点として活用しました。謙信は毘沙門天を篤く信仰し、城内に毘沙門堂を建立して戦の前には必ず籠もって戦勝を祈願したといわれています。川中島の戦いをはじめとする数々の合戦において、春日山城は謙信の根拠地として重要な役割を果たしました。
5. 御館の乱と上杉景勝
天正6年(1578年)の上杉謙信死後、養子の上杉景勝と上杉景虎(北条氏康の子)が家督を争う「御館の乱」が勃発しました。春日山城と城下の御館(関東管領館)を舞台とした激しい争いの末、景勝が勝利して春日山城の城主となりました。景勝は豊臣秀吉に臣従し、春日山城で羽柴秀吉との会談も行われました。
6. 廃城と福島城への移転
慶長3年(1598年)に上杉景勝が会津120万石に移封されると、堀秀治が春日山城に入城しました。しかし堀氏は政治を取り仕切るに不便として、慶長12年(1607年)に直江津港近くに福島城を新築して移転し、春日山城はその役目を終えて廃城となりました。以後、春日山城は二度と居城として使われることはありませんでした。
7. 現存する遺構と見どころ
春日山城には戦国時代の山城の特徴である空堀や土塁、曲輪群が良好に保存されています。本丸跡からは頸城平野と日本海を一望でき、標高150メートルの場所にある直径10メートルの大井戸は今もなお水が湧き出しています。毘沙門堂は昭和6年に復元され、昭和44年には上杉謙信公銅像が建立されました。林泉寺の惣門は春日山城の搦手門を移築したものといわれています。
8. 春日山神社と林泉寺
春日山城周辺には謙信公ゆかりの史跡が点在しています。春日山神社は明治34年に創建され、山形県米沢市の上杉神社から分霊されて謙信公を祭神として祀っています。林泉寺は謙信公の祖父長尾能景が建立した菩提寺で、謙信公は7歳から14歳まで名僧天室光育の下でここで過ごしました。現在も謙信公の墓所があり多くの参拝者が訪れています。
9. アクセスと観光情報
春日山城跡は北陸自動車道上越ICから車で15分、えちごトキめき鉄道春日山駅から徒歩40分です。春日山城史跡広場・ものがたり館では復元された土塁や堀、川中島合戦図屏風などが展示され、春日山城の歴史を詳しく学ぶことができます。上越市埋蔵文化財センターでは謙信公の生涯や春日山城についてジオラマ展示やタッチパネルで紹介しています。
10. 春日山城と日本100名城
春日山城は平成18年(2006年)に日本100名城の32番に選定されました。戦国時代最強の武将といわれる上杉謙信の居城として、また日本五大山城の一つとして高い歴史的価値が評価されています。スタンプは春日山城跡ものがたり館(冬季は上越市埋蔵文化財センター)で押印でき、御城印は上越市埋蔵文化財センターで300円で販売されています。越後の雄大な自然と戦国の歴史ロマンを同時に楽しめる名城として、年間を通じて多くの城郭ファンが訪れています。